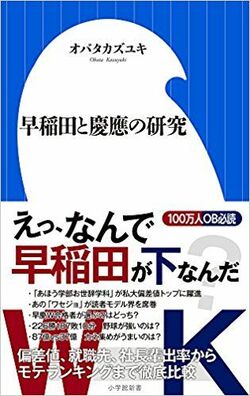1980年代、ブレザーに慶應のワッペンをつけてディスコでナンパすると女子大生に非常にモテた、という逸話がある。豊かになって、さらなる豊かさを求める人々が、「慶應ボーイ」というブランドを物語の中でだけでなく、実生活においても消費し始めたのだ。
1988年に文学部(日本史学専攻)を卒業した慶大OBは、「私は、まったくもって派手な遊びはしていませんでしたが」と前置きした上で、こう話す。
「バブルど真ん中だったこともあり、金持ちは金持ちらしい遊び方をしていました。同級生にジャーナリストの竹田圭吾(故人)がいたんですが、彼は東京タワーのすぐそばにある芝中・高出身で、新富町に住んでいて、ゼミ合宿に(トヨタ自動車の)ソアラで現れることで有名でした。
卒業アルバムを開いても、別格のバブリーな雰囲気を醸し出している。ページを開けると、どこにいるかすぐわかるんですよ」
1989年に文学部(仏文学専攻)を卒業した女性も次のように語る。
「学生時代は、よく同級生の男子の車で横浜に連れてってもらいましたねー。当時の慶應の男子の中には、お金持ちなのに貧乏学生ぶる、『貧乏プレイ』を楽しんでいる人までいました。今振り返ると、ちょっとイヤミに感じるかな」
ちょっとでなく、かなりイヤミなプレイである。だが、当時はそんなことをしても炎上することなく、面白ネタとして語られていたのだ。感覚がおかしくなっていたともいえる。
現代では負のレッテル
それからまた四半世紀が過ぎた。現在の私たちの多くは、戦後何番目かの好景気だといわれても、さっぱり実感がわかない。大半は、未だデフレ社会の中で疲弊している。
その平均的な目線からすると、今の「慶應ボーイ」は存在からしてイヤミに感じられてもおかしくない。自分に向けられたら、負のレッテル貼りと感じるのだろう。
「垢抜けない地味な男子ばかり」ともされる、バブリーとは無縁の普通の男子慶大生からしたら一線を引く対象であり概念。世間もだいぶ地に足が着いたというのに、うちの大学にはなぜいつまでも同じようにイメージされているのか。そこまでの金持ちなんてほんの一部の連中なのに……。
「慶應ボーイ」と一括りにされると、そういう理不尽さを覚えるのだろう。そりゃ、当然のことだ。こちらも無意識に色眼鏡で見ていたところがある。悪いことをした。
※「慶應ボーイ」=「幼稚舎からの内部生」と定義する説もあるが、本稿では慶大生や慶大卒業生をすべて「慶應ボーイ」とした。
オバタ カズユキ(おばた かずゆき)◎ライター・編集者 『大学図鑑!』監修者。1964年、東京都生まれ。大学卒業後、一瞬の出版社勤務を経て、フリーライターになる。社会時評、取材レポート、聞き書きなど幅広く活躍。