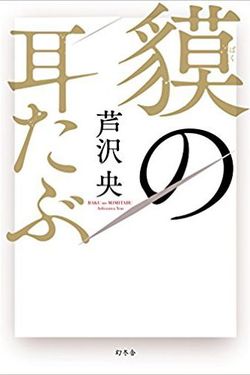3年ほど前に発覚した、子どもの取り違え事件を覚えていますか?
本来は裕福な家庭で育つはずだった男性は、取り違えにより貧しい家庭で育つことに。その結果、人生にさまざまな不利が生じました。東京地方裁判所は産院の過失を認め、男性に、総額3800万円の賠償金を支払うことを命じたのです。
こんな子どもの取り違えを、産んだ母親みずからが行ったら、親は、子どもはどうなるのか? 犯行に至るまでの心理と、その後の生活を、緊迫感あふれる小説に仕上げたのが『貘の耳たぶ』(幻冬舎)です。
取り違えを実の母親がしたとしたら……

本書執筆の動機を、著者の芦沢央さんが語ります。
「女性って、子どもを産めば、すぐ母性が芽生えるものと思われがちですよね。“本当にそうだろうか?”と疑問に思ったのが、執筆の出発点でした」
冒頭で描かれるのは、帝王切開で出産した繭子が、術後の痛みに耐えながら新生児室へと向かうシーン。並んだ新生児の中で一番小さなわが子と対峙した繭子が抱いたのは、退院後に待つ子育てへの不安でした。
そして繭子は、いくつかの要因が重なったことで、妊娠中に両親学級で知り合って以来、親しくしていた郁絵の赤ちゃんと自分の子を取り替えてしまうのです。
衝撃的なこのシーンには、自身の2回の出産体験が反映されていると芦沢さん。
「私自身、1人目の子を出産した際に“こんなにもか弱い生き物を自分が育てることができるんだろうか”と不安を覚えたことがありました。その産院では産婦同士の交流が盛んだったこともあって、互いに不安や悩みを共有しているうちに気持ちを切り替えられたんですが、2人目を産んだときは他の産婦と話す機会がほとんどなかったんです。
2人目だったこともあってそれほど不安を覚えることも少なかったのですが、もしこれが1人目のときだったらもう少し追い詰められていたかもしれないと思ったとき、たまたま自分の子どもの足首からネームタグがはずれていたんですね。その瞬間、いろんなことが紙一重だったんじゃないかと思うようになって、それまで温めていたアイデアが動き始めたんです」
最後の最後に訪れる破滅と救い
さて、繭子は取り違えをした直後から後悔の念に苛まれ、何回も告白を試みますが思うようにいきません。
誰にも相談できず、他人の子と知りつつ育てる苦悩と、芽生え始める本当の母性。繭子は本当は郁絵の子である航太に対し“こうやってひとつひとつ成長していくところをこの目で見たい”と思いつめ、熱い涙を流すほど愛情を感じ始めます。このへんの徐々に真の母性に目覚めていくリアリティーある描写に関しては、
「繭子のパートの表現に関しては、赤ちゃんの匂いだとか、手をぎゅっと握られる感覚だとか、理屈よりも肌感覚を描きたかったんです。出産直後のホルモンバランスは、たとえて言うなら普段の生理がビルの高さなら、出産直後はエベレストの頂上ぐらいまで変わるもの。繭子の問題はそんな身体の問題からきたものでもあり、身体の変化が心の変化に直結していることも描きたかった」
一方、理想の母親に見えた郁絵も葛藤がありました。
「保育士を続けるために、郁絵は子どもを保育園に預けてきました。けれど、そのわが子を手放さなければならないと知って、自分の中にある子どもの記憶があまりにも少ないことにガク然とするんです」
芦沢さんが複雑な表情で語ります。
「私も、子どもを預けてこの話を書いているんですよね。私自身が、“子どものかわいい姿を見逃している。子どもとの時間は限られているのに”と感じながらです。それでも書き続けずにいられない業の深さを感じています」
著者自身がそう語るように、繭子と郁絵の悩みや負い目は、出産と子育てを経験した女性なら誰しもきっと抱くものでしょう。それゆえ繭子の過ちに怒りは感じても、“自分はゼッタイに彼女のようなことはしない”とは言い切れない自分自身に気づきます。本書を読んでいる自分自身を含め、完全なる悪人もいなければ完全なる善人、あるいは完璧な母親もいないことに気づくのです。
この“完全にはなりきれない人間”は、本書を貫く主題でもあるようです。
「繭子の夫にしても、彼は彼なりに子どもや妻を一生懸命愛しているんですよね。わかりやすい嫌な人がいるわけじゃないぶん、こうしたつらいことが起こったとき、お互いつらいなあというのがあると思います。
本書に限らず、私が小説を書いていく根幹に“生きづらさと向き合いたい”という思いがあるんです。繭子は自分の弱さや生きづらさから道を間違えてしまいますが、間違えるのも人間なら、間違いや弱さに向き合うのもまた人間。人間の弱さや強さ、ずるさや優しさといった多面性を描きたいというのがあります」
著者のこの言葉どおり、母性ゆえに犯した罪は、最後の最後で母性ゆえに破滅を迎えます。弱さゆえ犯された犯罪は、強さゆえ終わるのです。
“これで本当によかったの!? このあといったいこの家族は……?”
驚愕のラストに震え、そして考え込んでください。
取材・文/村名若菜
<プロフィール>
あしざわ・よう 1984年、東京都生まれ。小説家 推理作家。千葉大学文学部卒業後、出版社勤務を経て、2012年『罪の余白』で第3回野性時代フロンティア文学賞を受賞し、デビュー(角川書店/KADOKAWA)。同作は、'15年に映画化された。'16年には『許されようとは思いません』(新潮社)が第68回日本推理作家協会賞(短編部門)と、第38回吉川英治文学新人賞候補に。