認知症の症状が改善されたり、難病と闘う力を与えてもらったり。「看取り犬」に寄り添われ、おだやかに旅立つ人もいる。日本初の「ペットと一緒に入れる老人ホーム」の毎日は、動物たちとの温かな触れ合いが引き起こす、やさしい“奇跡”であふれている。施設長の若山さんが目指すのは、わが家のような居場所。愛犬や愛猫たちとの暮らしも、腕によりをかけた食事も、小旅行も、すべては高齢者の夢を叶えるために──。

癒しや温もりを与えてくれる大切な愛犬や愛猫は、飼い主にとっては家族同然の存在。しかし、ペットの寿命が延び、飼い主も高齢化するなかで「自分にもしものことがあったとき、この子はどうなるのだろう」と、不安に思う人は少なくない。
人間が不可能なことを動物が可能にする
そんな高齢者の心配に応える老人ホームが神奈川県横須賀市にある。特別養護老人ホーム『さくらの里 山科』は飼い主とペットが一緒に入居でき、ともにのびのびと暮らしている、稀有で温かい施設だ。動物たちとの触れ合いを通して、難病と闘う力をもらった高齢者がいる。息子の名前さえ忘れていた認知症の女性が記憶を取り戻したこともある。人間が不可能なことを動物が可能にする、そんな小さな奇跡が、ここではたくさん起きている。
施設長の若山三千彦さんは言う。
「ペットと暮らす生活をあきらめて、生きる気力を失う高齢者がこれ以上出ないためにも、うちの施設のような老人ホームが全国に広がってほしいです」
「あきらめない福祉」を掲げる若山さん。その熱意はどこからきて、どのように形にされていったのだろうか。
昭和40年、若山三千彦さんはサラリーマンの父と専業主婦の母との間に生まれた。2つ下の弟と、6つ下の妹、そして近所の子どもたちと一緒に山で遊ぶ、ごく普通の子どもだった。
両親は動物が大好きで、若山さんが小学生のころからうさぎを飼っていた。中学生になると犬も飼い、動物がいることが当たり前の暮らし。また両親はボランティア活動にも熱心で、若山さんは小学生のころ、母親に連れられて老人ホームや障害者施設に通うこともあったという。
幼い若山さんは、比較的おとなしく、SFが大好きで、黙々と本を読む子どもだった。SF好きは、のちの進路にも影響することになる。若山さんは宇宙について学びたいと考え物理系の大学へ進学。物理を学んだ若山さんは、違う学問にも関心を広げ大学院の環境科学系へと進み、都市計画を専攻した。
その後、大学院を卒業し、今度はアイルランドにある日本人高等学校の教師となる。
「めずらしい国での教師の仕事は、おもしろそうだな、という感じで行ったんです」
周囲の友人たちは、好奇心のままに行動する若山さんを見て、あきれていたと笑って話す。
「やりたいことがあったら自然に動いてしまうんです」
アイルランドの教師生活では、高校生に物理と化学を教えていた。当時のアイルランドには日本人はほとんどいなかった。小さな学校で1学年に1クラスしかなく、20人くらいの生徒たちと、校内の寮でのんびり暮らしていた。
「思えば、私自身の“職業人スピリット”のようなものは、ここで培ったのだと思います。最初に“教師とは、生徒の夢を叶える仕事だ”と教えられ、ずっとそれを目指していましたから」
この「誰かの夢を叶える仕事」という思いが、高齢者の夢を叶える現在につながっている。
浅草・雷門で涙して、中ジョッキに男泣き
5年の勤務を経て、日本に帰国。茨城県の常総学院で教師を始めた。1998年、高校3年生を受け持っていた年、若山さんのクラスの生徒が朝の通学時に交通事故で亡くなってしまった。ムードメーカーであり、親しまれていた生徒の死。クラスメートも、深く悲しんでいたが、しばらくすると、「その子の分まで、自分たちが頑張らなくては」と、全員が必死になって受験勉強を始めた。
ほとんどの生徒が朝7時半に登校し、夜9時まで残って勉強する姿に、若山さんも毎日付き合った。悲しみを抱えた特別な状態で、それでもクラスが一体となって、目標に向かう生徒たち。そして、全員が、第1志望、第2志望校に現役で合格したのだ。
「このとき、同僚からは“奇跡だね”と言われました。この体験は、私には特別なものでしたし、“もう、ほかのクラスは持ちたくないな”と思ってしまったんです」
ちょうどそのころ、若山さんは両親から相談を持ちかけられていた。「退職金と、家を売却して、自分たちの理想の老人ホームを作りたいと思っているけれど、いいか」というものだった。「好きにしていいよ」と答え、当時は手伝うつもりもなかった。しかし、行政とのやりとりなどが両親の手に負えなくなってきたことと、クラスの生徒たちの卒業のタイミングとがちょうど重なり、若山さんは教師生活を終えようと決意した。
1999年、両親が思い描く老人ホームを立ち上げるため、本格的な準備が始まった。高齢者グループホームとして『さくらの家 壱番館』、デイサービスセンター『さくらの里』、障害者の就労支援施設『あすなろ学園』の、3つの小さな複合施設。2000年からは高齢の両親を支え、経営者として福祉施設を運営していくことになった。
福祉や介護を学びながらの経営。若山さんは、デイサービスセンターを視察することもあったが、実のところ、高齢者が何をするところなのかわからなかった。家族の代わりに食事や排泄、入浴のお手伝いをする施設、ということはわかったが、高齢者にとって何が楽しみとなっているのか、わからなかったのだ。
「デイサービスに来た高齢者が、どんな夢を叶えるのか」という視点が必要だと考えた若山さんは、自分の運営するデイサービスセンター『さくらの里』では、外出に力を入れることにした。1年目は近場にしたが、2年目からは浅草などへ遠出をするようになった。

「利用者の中に浅草生まれの方がいらっしゃったんです。その方は、小旅行で浅草に行ったときに、雷門の前で“死ぬまでにもう1度、浅草を見られるなんて思わなかった”と言って、ポロポロ泣き出したんです。電車で1時間の故郷にすら遊びに行けない。高齢で、車椅子であることで“あきらめるしかない”と思っていたのだと知りました」
デイサービスでは前代未聞の、みんなで夜に居酒屋に行くというイベントを開催。入居者の男性が中ジョッキのビールを飲み、「うれしい! 」と声をあげて男泣きしたこともあった。看護師が判断した飲酒許容量を超えないよう、スタッフが付き添って見守りながらの飲酒だが、中ジョッキの1杯に、感極まってしまうほど喜んだのだ。
会社勤めをしていたころ、毎晩のように飲み歩いていた男性は、定年退職後に脳梗塞を患い、夜の宴会や居酒屋に行くことは2度とないとあきらめていた。
高齢者が、最期まで人生を楽しめるように支えていきたい……。若山さんの心に、そんな決意が宿る出来事が増えていった。『さくらの里 山科』が掲げる「あきらめない福祉」「あきらめない介護」という理念は、ここからスタートしたのだ。
いつ起きてもOK、豪華おせちも登場する理由
デイサービスセンター『さくらの里』では、在宅介護にも力を入れていた。しかし、自分の家で最期まで過ごせる人は少ない。重い介護が必要になると、家族で世話をするには限界が訪れて、老人ホームや病院などへ頼らざるをえなくなる。そのようにして在宅介護から介護施設などへ移るとき、やむなくペットをあきらめなくてはならない現実があった。ひとり暮らしの高齢者であれば、なおさらだ。
ある男性は、要介護になりたったひとりの家族だったペットを保健所に引き渡すしかなく、その後、入居先の老人ホームで生きる力をなくし、わずか半年で亡くなってしまった。そういった現実に、『さくらの里』のスタッフも心を痛めていた。
高齢者にとって“最後の受け皿”となる居場所が欲しいと若山さんは考えていた。そうして誕生したのが特別養護老人ホーム『さくらの里 山科』だ。自治体の地域福祉計画に沿って'10年から準備し、’12年に設立。法人化を待望していた両親の夢を、特別養護老人ホームの設立で叶えることができた。
そのころ、若山さんの母親はがんで闘病中だったが、ホームの認可が下りたことにとても喜んでいた。しかし、残念ながら、ホーム完成の直前に亡くなった。
『さくらの里 山科』では、高齢者が住む10LDKのマンションをイメージした。旅行行事やホーム内での公演、手工芸などを行い、食事にも力を入れる。お正月には、ひとりひとりに本物の漆塗りの重箱に入ったおせち料理を出し、伊勢海老を用意したこともある。夏はウナギや鮎、冬にはフグやあんこう鍋がふるまわれる。起床時間も消灯時間も決まりはなく、ゆっくり寝て、遅く起きてもかまわない。夜遅くまでタブレットでインターネットをしたり、テレビを見ていたりする人がいてもいいのだ。

食事の時間も、一斉に「いただきます」をするスタイルではなく、2時間の幅で自由に食べることができる。そして、ペットと一緒に入居することも可能とした。「あきらめない介護」のひとつとして、日常の自由を守ることを決めていたからだ。そのイメージは、「わが家」だと若山さんは言う。
「老人ホームの世界は、この10〜20年で大きく変化したんです。それ以前は、国の高齢者福祉政策は“老人の保護・収容”という発想でした。でも、今は、高齢者の人権にも意識が届くようになってきています」
それまでは、高齢者の最低限の生活を保障するという「生存権」の考え方だったが、自由に暮らす権利を守る「幸福追求権」を目指すようになってきているという。「生存権」の考え方でいえば、3大ケアといわれる「食事」「排泄」「風呂」さえ介護すれば人は死なない、という発想だった。しかし若山さんには、「ひとりひとりの生活の質を高めたい」という思いがある。だからこそ、家族であるペットとの生活もあきらめない。最期まで愛犬や愛猫と一緒に暮らせる環境は、「生活の質」の中に当然、含まれるべきものだった。

こうして生まれた『さくらの里 山科』は、4階建ての120床、完全個室制・ユニット型。1ユニットは、イメージとしては、10LDKのマンションに近い。居室10室(10名)とリビング、キッチン、3か所のトイレ、お風呂からできていて、それが全部で12ユニットある。
そのうち、2階部分に犬と暮らせる2つのユニット、猫と暮らせる2つのユニットがある。現在、ここで暮らす動物たちは、犬11匹(入居者の飼い犬8匹、保護犬3匹)、猫も9匹(入居者の飼い猫5匹、保護猫4匹)。3階と4階には、動物が苦手な人も入居できるようになっている。
生きる気力を与え、病さえ癒す犬猫たち
'12年から現在に至るまで、ペットと高齢者との暮らしを見続けてきた若山さん。そこには、さまざまな出会いがあった。
施設の入居者である沢田富與子さん(76)は、60代で病を患い、たったひとりの家族である愛猫の祐介を遺したまま自宅で自分が死んでしまったら、どうしようと考え続けていた。祐介とともに自死を考え、病院からもらってきた睡眠薬をふたり分、蓄えたこともある。そして、思い詰めるあまり、身体を壊して入院してしまったのだ。
しかし、『さくらの里 山科』に出合い、祐介とともに入居したことで、生きる力を取り戻した。沢田さんは「今がいちばん幸せ」と言うほど、ここでの祐介とのおだやかな暮らしに満ち足りていた。
沢田さんは幼いころから犬や猫、メジロを飼い、セグロセキレイを保護したこともある。小さな動物園のような家で育ち、動物のいない世界など、信じられなかった。自分の子どもと同じだと思って祐介も育ててきた。
「自分が好きで飼っていた動物は、自分が面倒を見られなくなったとしても、本当はそばにいたいし、癒される存在なんですよね」(沢田さん)
だが、独居の高齢者には、それは叶わないのが現実だ。かつての沢田さんのような不安を抱える高齢者は、いまもどこかにいるのかもしれない。最期のときまでペットと暮らせる、そして、自分が先に死ぬことがあっても、施設が大切に飼い続けてくれる──。そんな安心感が、沢田さんの生きる力になった。
「その祐介が、実は、先日、亡くなりました」
沢田さんが大きな悲しみの中でも気丈に取材に応じてくれたのは、「小さな命のことも大切にしてほしい」、そして「こういった施設が増えてほしい」という思いからだった。
「きれいな顔で、苦しまずに14歳で逝きました。小さな命にも、温かく向き合ってくれるこのホームに、祐介が私を導いてくれたんです。このホームで、たくさんの方に大切にされて、祐介は本当に幸せでした。こんな施設が増えてほしい。そう、(記事を通じて)伝えてほしいんです」

祐介くんへの深い愛情と死の悲しみとを、心を込めて、そう語ってくれた。
一方、沢田さんは友人たちから、「きっと料金が高い施設なんでしょう?」と言われることもある。
「“入居費は私の年金だけよ”と言うと、驚かれます。高級な老人ホームでも、動物はダメというところが多いんですよね。それに、豪華なことより、安心できることが大切です。ここは職員さんも動物好きな人たちばかりだから、安心して託せるんです」
動物虐待や、捨て猫・捨て犬の存在に心を痛める沢田さんは、以前、リハビリ室の外に放置されていた猫を、「さくらの里 山科」の職員が「私が引き取ります」と言って連れて帰ったことを、よく覚えている。
「この施設で本当によかった、と思いました。信頼できますよね」
動物たちが与えた影響
また、動物たちの持つ力を借りて、病気の症状が改善された高齢者もいる。
大の猫好きだった斎藤幸助さん(仮名)は、認知症を患っていた。『さくらの里 山科』を知った斎藤さんの息子は、猫ユニットへの入居を申し込んだ。初めて猫ユニットの玄関の扉を開けたとき、小さな猫が斎藤さんの足に体をこすりつけ、可愛い声で鳴いた。その瞬間、斎藤さんの顔が輝いたのを職員は見ていたそうだ。
認知症になると、無気力・無感情のような症状が出る。しかし、斎藤さんは、猫との暮らしで表情を取り戻し、生きる希望を取り戻し、歌を歌い、リハビリにも意欲的になっていった。
斎藤さんは、トラという猫と仲よしになった。床にあぐらをかいて歌う斎藤さんの脚のあいだに、トラがちょこんと座る。歩行訓練に使うシルバーカートにトラがちょこんと座り、斎藤さんはそのカートを押す。気まぐれなはずの猫が、何十分もそのカートに座る姿は、斎藤さんのリハビリを応援しているかのように見えたそうだ。
動物に励まされた入居者は、斎藤さんだけではなかった。愛犬のナナと入居した渡辺優子さん(仮名)は、進行性核上性麻痺という難病だった。ナナと離れたくないという思いで、ギリギリまで自宅での生活をしていた渡辺さんは、ナナと入居し、十分な介護を受けたことで衰弱した身体が劇的に回復したものの、少しずつ進行する病気に治療法はなかった。しかし、リハビリは有効な手段だ。
実際の肉体の苦痛は、気力だけでは乗り越えられない。「ナナのために頑張る」と口癖のように言っていたが、平行棒を3メートル歩いて、苦しむ渡辺さんの様子に、作業療法士も悩んでいた。
「ナナと一緒にリハビリしてもらったらいいんじゃない?」
と提案したのは、介護職員の出田恵子さん(犬ユニットリーダー担当)だ。作業療法士はそれを聞き、ナナを乗せた車椅子を渡辺さんに押してもらう方法を思いついた。
初めてナナと歩行訓練をした渡辺さんは、3メートルどころか、50メートル以上ある長い廊下を歩き切ることができた。1か月後には、廊下を2往復できるまでになり、口の動きはさらに回復し、単語を明瞭に言えるようになった。ナナは、難病と闘う力を与えたのだ。
渡辺さんは、その後、医師も驚くほど回復をしたが、少しずつ病が進行し、残念ながら亡くなってしまった。ナナは渡辺さんをベッドで看取ったあとも、今もホームの愛犬として元気に暮らしている。職員の出田さんの後ろをついて回ることもある。
介護職歴19年で猫ユニットのリーダーを務める安田ゆきよさんは、入居者が動物と一緒に暮らすことで「介護だけでは味わえない、ケアの方法が増えたと思います」と話す。動物のいない施設では経験のないようなことが『さくらの里 山科』では、たくさん起きているという。

「生き物の力を感じます。入居者さんも、職員も、喜怒哀楽のある刺激のある暮らしです。単調ではないことが、活力の一部にもなっています」
例えば、体力が衰え、ふらつきがちでつかまり立ちだった入居者が「猫を触りたい」「なでたい」という思いで屈伸するようになり、筋力がついて、猫が背中に乗っても、おんぶができるようになったこともある。そして、歩けるようになっていく。
「そういったことは、人間のケアではできない。動物たちが与えた影響なんです」(安田さん)
元・保護犬の「看取り犬」文福が起こした奇跡
『さくらの里 山科』では、飼い主と入居したペットのほかに、保護犬や保護猫も一緒に暮らしている。そのうちの1匹が、「看取り犬」である文福だ。
文福は推定年齢12歳。「推定」なのは、殺処分寸前の保護犬だったからだ。入居当時は、自分が殺されるかもしれないことを察知していたのか、神経質な状態で来た。
今はおだやかな気性の犬だが、ここへ来た当初、職員には「ウーッ」とうなっていた。しかし、入居している高齢者には、絶対にうならなかった。おそらく“守るべき存在”ということが、文福にはわかっていたのだろう。
その文福は、すぐにホームに慣れ、入居者にまぎれてちょこんと椅子に座っていたり、さりげなく隣に行ってなでてもらったりするホームの人気者になった。
文福が「看取り犬」であることを発見したのは、前出の介護職員・出田さんだ。
『さくらの里 山科』では例年、年間30人ほどが亡くなる。看取り期に入る入居者が出ると、なぜか文福は、その入居者の居室のドアの前にぺたっと悲しそうに座り、ずっと寄り添うのだ。出田さんは、いつも元気な文福の物悲しい姿に「あれ?」と不思議に思っていたが、その入居者は翌日に亡くなった。

また別の入居者が亡くなったときも、文福は同じ行動をとった。亡くなる2〜3日前になると、居室のドアに座り、すっと部屋に入り、ベッドに上ってペロペロと顔をなめる。職員が「文福、出ないの?」と声をかけても、じっと入居者のそばにとどまり、見守り続ける。そのしぐさは、普段、入居者とじゃれ合う文福の雰囲気とは違っていた。
これが自分の愛犬・愛猫がいる入居者の場合、文福は少し遠慮する。まるで、「ここには、看取るペットがいるから大丈夫だろう」と察するかのようだった。しかし、それでも死期が近くなると、入居者の部屋の近くにいようとすると出田さんは言う。
前出の斎藤さんに寄り添う猫のトラも、文福のような力があったという。トラは看取りの力というよりは、弱っていることを察知する力を持っていて、寄り添って癒す行動をとっていた。ペットセラピーの専門家がトラと入居者の様子を見て、「どんな訓練を受けたセラピードッグもかなわないアニマルセラピーを行っている」と、感嘆したこともあるそうだ。
文福は、看取り犬としての奇跡だけではなく、認知症の佐藤トキさん(仮名)との間でも奇跡を起こした。重度の認知症で入居した佐藤さんは、理解力や判断力の低下に伴い、無表情な状態だった。佐藤さんの息子は、長年犬を飼っていた母親が『さくらの里 山科』で犬と暮らせば、何か変化があるのではないか、と望みをかけて託したのだ。
入居した佐藤さんは当初、文福をかつて飼っていた「ポチ」と思い、「ポチ」と呼びかけ、次第に表情を取り戻していった。文福は、「ポチ」と呼ばれても、佐藤さんの元に行くやさしい犬だ。佐藤さんは、そんな文福をやさしくなで、抱きしめ、3週間後には、「ポチ」ではなく「文福」であることを理解していった。
そして、入居1か月後に面会に来た息子に、「あら、幸一、来てくれたの?」と呼びかけたのだ。わが子の存在を忘れてしまっていたかに見えた母が名前を呼んだ奇跡に、息子は絶句していたという。

それから1年半、佐藤さんは、文福と幸せに暮らした。「70を過ぎて犬をあきらめたのに、こうして犬と一緒に暮らせるなんて夢みたい」と話し、そして、「息子たちには悪いけれど、文福に看取ってもらいたい」といたずらっぽく笑って話すこともあったそうだ。その願いどおり、佐藤さんは文福と息子さんに囲まれて亡くなった。
「亡くなってしまうことは、この施設では日常なんです」
と若山さんは言う。介護とは、常に命と向き合う仕事でもある。
「看取りにペットが加わっていても、本当は特別なことではなく、普通のこと。ペットも家族ですから、最期まで一緒にいられて当たり前なんですよ」(若山さん)
「あきらめない福祉」を叶えるために
飼い主とともに入居したペットも、保護犬や保護猫たちも、動物たちの世話はすべて職員が行っている。そもそも介護の現場は深刻な人手不足に加えて、不規則な勤務形態や給料の安さなどから離職率が問題になることも多い。『さくらの里 山科』の職員たちは、負担をどう感じているのだろうか?
「猫の食事、トイレ掃除や病院受診など、プラスアルファの仕事は増えますが、生活の一部になっているので、そんなに負担は感じていません」
と、ベテラン介護職員の安田さんは言う。動物が好きだからという理由で、犬猫ユニットを希望するスタッフもいるそうだ。
前出の出田さんは、「私たち職員も、動物に癒されている面もあるんです」と話す。「それに、一斉に食事をするスタイルだと大変かもしれませんが、ここでは、○○さんは8時ごろ、××さんは9時ごろに食べる、と、それぞれのスタイルに合わせて食事の用意をするので、バタバタしないメリットもあります」

実際、『さくらの里 山科』では職員の定着率も高く、動物がいる職場で働きたいと、求人に応募してくるケースも少なくないという。
若山さんは、「犬や猫へのオヤツ禁止令を出したこともあるんです」と笑って話す。職員や入居者が、ホームの動物たちをかわいがるあまり、太ってしまうほどオヤツを食べさせてしまうからだ。色とりどりの洋服やおもちゃも増えた。
「犬たちは、入居者の食事の時間だけは、それぞれのケージで過ごすようにしています。入居者さんも、自分の食べているものを、ついかわいくてあげてしまうんですね。“あげないでください”と言わなくてすむように、そうしているんですよ」

家族の一員であるペットとともに、おだやかで安心できる、当たり前の日常が過ごせるよう力を尽くしてきた若山さん。しかし、長引くコロナ禍はそんな日常を一変させ、高齢者施設に大きな影響を及ぼしている。『さくらの里 山科』も、例外ではない。
「この施設では、面会時間の制限がなくて、いつでも何人でも来てくださいという自由な決まりだったんです。なので、日ごろから面会の多いホームでした」
しかし、感染拡大の中では、そうはいかなくなってしまった。
「毎日立ち寄る方、仕事帰りの19時とか20時とかにちょっと立ち寄る方もいましたが、それが今はまったくできないのが残念です」
現在は、入居者の家族のみ、1階の入り口で、窓越しに携帯電話で話すという面会スタイルになってしまった。
施設内の感染対策はマスクの着用は当然のこと、消毒用アルコールも常時設置するなど以前から徹底していたが、「コロナ以降は感染対策のレベルを上げました」(若山さん)
職員は勤務にあたり、自宅での検温が必須になった。37・5度以上あれば出勤できなくなるため、調整に奔走しなければならない。
これまでは、外出行事にも力を入れていたが、すべてできなくなってしまった。比較的体力のある入居者の誕生日には、本人が望む食事を、職員と一緒に寿司店やレストランなどへ食べに出かけてお祝いをするが、それも今はできない。家族に会えない1年間を過ごした入居者は、活気がなくなり、認知症の進行が早まった高齢者もいると、若山さんは心配している。
「それでも、犬や猫がいることで、救われている入居者もいると思います」(前出・安田さん)
その人らしく生きることをあきらめない
出田さんは、高齢者施設に動物と入居できることが当たり前になれば、殺処分も減らせるかもしれない、と考えている。ペットが飼い主より長生きして自治体に保護されるケースでは、他人に長く飼われた高齢の犬や猫ほど引き取り手が少なくなり、殺処分されてしまうからだ。
「最期まで一緒にいられることが当たり前になれば、高齢になってからも、安心してペットを飼えますよね」
そう言って、出田さんは期待を込める。
「これからは、ひとり暮らしの高齢者が今以上に増えていく。ペットと暮らせる老人ホームのニーズは、必ず高まっていきます」
と、若山さんは断言する。そしてペットと暮らすことを含め、何かをあきらめていた高齢者の夢が叶って喜ぶ姿に、「やってよかった」と感じられることが、大きな原動力だと話す。
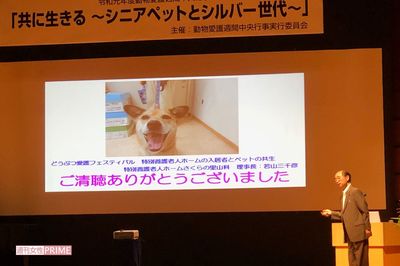
「同じ業界の方々からの見学には、これまでもできる限り応え、施設をオープンに見てもらってきました。有料老人ホームでは、ペットと暮らせるところが増えていますが、特別養護老人ホームでペット入居可の施設は、なかなか実現に至らなかったんです。でも先日、九州の特養から“実現しそうです”という知らせがあって、そのことを本当にうれしく思っているんです」
ひとりひとりの生活の質を高め、最期まで、その人らしく生きることをあきらめない。その思いで、若山さんは取り組みを続けている。
フリーライター。1977年生まれ。福島第一原発事故で引き起こされたさまざまな問題や、その被害者を精力的に取材している。『孤塁 双葉郡消防士たちの3・11』(岩波書店)で講談社ノンフィクション賞を受賞。
(撮影/伊藤和幸)

