
終戦から76年──。戦争の怖さや苦しさ、悲しみなどを語り継ぐため、過去の週刊女性PRIMEや週刊女性の誌面から戦争体験者の記事を再掲載する。語り手の年齢やインタビュー写真などは取材当時のもの。取材年は文末に記した。(【特集:戦争体験】第9回)
◇
「僕が10歳で終戦の年を迎えたのは、大分・佐伯防備隊の軍港からひと山越え、あまり空襲のなかった下堅田村というところでした」
当時、いまの小学校にあたる国民学校4年生だった高橋照美さん(77)は、いつも“マーちゃん”という同級生と遊んでいた。マーちゃんは農家の息子で、笑うと細い目がより細くなり、一緒に山に登ってアケビや野いちごをとって食べた。
「どういうわけか気が合ったんです。標高約600メートルの山の頂上からは佐伯の軍港が望め、制空権をとったアメリカの戦闘機が山より低いところを飛んで爆弾を落としていくのが見えるんです。滑走路は穴ボコだらけにされて離着陸できなくなり、“あそこはもうダメだ”とか、不謹慎ですが見ていておもしろかったんです」
終戦1か月前の7月上旬、
「おい、川に泳ぎに行こうや」
とマーちゃんを誘った。
暑い日で、ふんどし一丁でイナダをモリで突いていた。
マーちゃんも結婚しとったかもね
遠くから爆音が聞こえてきた。見上げると飛行機が近づいてきた。高度100メートル以下の低空飛行だった。
「グラマンだ! 敵機だ!」
操縦席には鼻の高いアメリカ兵が、白いスカーフをなびかせていた。顔まではっきりみえた。
「伏せっ!」
と河原の茂みに隠れた。
素通りしたグラマンは、旋回して戻ってきた。
「ダダダダッと機銃掃射してきたんです。銃弾がキンキンと河原の石を弾きました。通り過ぎたあとマーちゃんは伏せたまま何も言わない。背中に出血の跡はなかったので“おいっ!”と身体を起こすと、お腹に大きな穴が開いていて腸が飛び出していた。身体の下は血まみれでした。どんな気持ちだったか、ショックで覚えていません。僕はマーちゃんの家に走り、“おばちゃん、たいへんだ!”と告げ、一緒に河原に戻りました」
撃たれると、弾の入り口の傷は小さく、出口の傷が大きいことをあとで知った。ふたりが隠れた茂みは、背の低い五三竹で上空から丸見えだった。
「おばちゃんはワンワン泣いたりせず、マーちゃんを抱きかかえて帰りました。僕はそのあとについていきました」
大学卒業後、高橋さんは朝日新聞の記者になり、結婚したときに同村を訪ねた。マーちゃんの母親に結婚を報告し、「お墓参りをしたい」と言うと、「生きとったらマーちゃんも結婚しとったかもね」と自分の息子のことのように喜んでくれたという。
「動くものならば犬でも人間でも撃つ。一瞬で死ぬ。それが戦争です。テレビゲームとは違う。平和憲法は絶対変えちゃいけない」
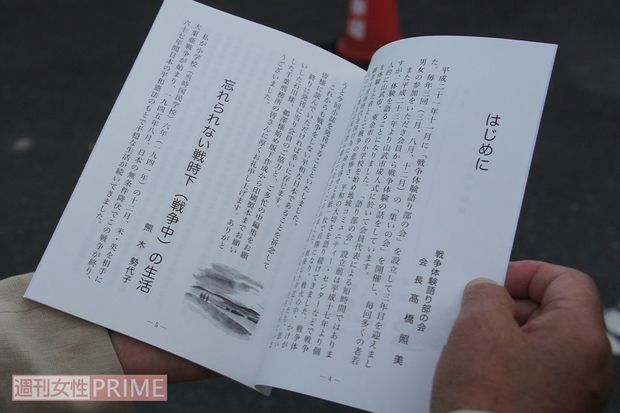
※高橋さんの「高」は「はしごだか」が正式表記
※2013年取材(初出:週刊女性2013年8月20・27日合併号)
◎取材・文/渡辺高嗣(フリージャーナリスト)
〈PROFILE〉法曹界の専門紙『法律新聞』記者を経て、夕刊紙『内外タイムス』報道部で事件、政治、行政、流行などを取材。2010年2月より『週刊女性』で社会分野担当記者として取材・執筆する
