
気温が上がり湿度も高くなる6月は一年で最も食中毒が発生する。本格的に暑くなってくると保冷剤などで対策をとるが、この時季は中途半端で食材への温度管理が甘くなるのも一因だ。「つけない」「増やさない」「やっつける」…細菌対策の3原則の実践を。
食中毒の原因は1つじゃない
梅雨から夏にかけて、気温、湿度の上昇とともに高まるのが食中毒のリスク。食中毒の原因は一つではなく、家庭での何げない習慣の中に、実は危険が潜んでいる場合もある。
これからの季節に覚えておきたい食中毒の予防ポイントを、感染症を専門とする内科医の田中雅之先生と、食事指導を行う管理栄養士の三城円さんに話を伺った。
「食中毒の主な原因には、ウイルス性、細菌性、動物や植物の自然毒、寄生虫などがあります。ノロウイルスなどのウイルス性の食中毒は乾燥した寒い時季に発生しやすいですが、カンピロバクター、サルモネラ菌、黄色ブドウ球菌、ウェルシュ菌などの細菌は、高温多湿の環境で繁殖しやすいため、梅雨から夏場は注意が必要です」(田中先生)
加熱不十分な生肉で食中毒を引き起こすカンピロバクターや腸管出血性大腸菌О157はよく知られる食中毒だが「生肉を食べなきゃ大丈夫、加熱すれば感染しない」
というワケではない。

時間をかけて加熱しているカレーやシチューなどの煮込み料理にも食中毒リスクがある。
「よく“カレーは一晩寝かせたほうがおいしい”と言いますが、実は室内で数時間放置しているだけで、ウェルシュ菌という細菌から発生する毒素が増殖し、食中毒の原因に。
また、黄色ブドウ球菌は人の手指から、食品が菌に汚染されるため、おにぎりやサンドイッチなど、手で触れることの多い調理法は、感染リスクが高まるので調理用の使い捨て手袋の使用をおすすめします」(田中先生)
調理器具や調理環境にも感染リスクは潜んでいる。
「特に生肉を扱うときは要注意。肉の入ったトレーのラップをはがすときに、その肉汁がはねて他の食材に菌が付着することがあり、肉を切った包丁やまな板で生野菜を切って、そこから菌が付着する場合も。調理器具は使うたびに洗うようにして、生肉用と生野菜用に分けてもいいと思います」(田中先生)
管理栄養士の三城さんは、
「煮込み料理は、調理後なるべく早く冷蔵や冷凍することで、感染リスクが減りますが、“すばやく冷ます”ことも大事です。まだ熱いうちに冷蔵庫や冷凍庫に入れると、冷えるまで時間がかかり、その間に菌が増殖したり、庫内の温度が上がって他の食品に悪影響を与えることがあります。
広げて冷ます、小分けにして容器に入れ、保冷剤を上に置き、粗熱を取ってから冷蔵、冷凍を。温め直しをする場合は、電子レンジは加熱にムラが生じやすいため、加熱後に一度かき混ぜて再加熱する、耐熱皿に広げてムラができないように加熱するなどの工夫をしましょう」
とアドバイス。
お弁当はバランや使い捨てカップを活用
調理から食べるまで、時間が空いてしまうお弁当は、特に注意が必要だ。
「水分が多い野菜は菌が繁殖しやすいため、加熱したほうが安全です。彩りによく使うミニトマトは洗ったあと、ヘタに水分がたまりやすいため、取るのがベター。レタスなどの葉野菜を仕切りに使う人もいますが、バランや使い捨てカップの活用を。
水分の多い具材とマヨネーズを組み合わせたポテトサラダやマカロニサラダは、よく冷ましてから詰めること。肉類、魚類はよく火を通し、半熟卵もサルモネラ菌が繁殖するリスクがあるため、中心までしっかりと火を通してください」(三城さん)

食材だけではなく、お弁当箱の殺菌も心がけたい。
「お弁当箱はきれいに洗ったとしても、目に見えない菌や油分、手指からの雑菌が残っている場合があります。使用前に熱湯をかけて自然乾燥したり、殺菌効果のあるお酢でサッと拭いてから詰めると安心です。特にふたのパッキン部分は雑菌がたまりやすい部分のため入念に」(三城さん)
原因やその人の体調によって発症までの時間や症状には差があるが、食中毒に感染すると24時間以内に吐き気、嘔吐、腹痛、下痢、発熱といった症状が見られる。
「下痢や嘔吐は細菌やウイルスを体外へ排出するための防御反応の一つなので、下痢止めや吐き気止めの薬を自己判断で服用するのはおすすめしません。症状が出ている間は無理に食事をとる必要はありませんが、脱水症状にならないように水分はとり、栄養ゼリーなどを摂取。
大抵の場合は数日で症状が治まりますが、体調不良が続く場合は医療機関を受診してください。まれに後遺症を発症する食中毒もあり、カンピロバクターは感染すると、手足のしびれや麻痺を引き起こす神経系の病気『ギラン・バレー症候群』を発症する場合があります」(田中先生)
普段から感染対策として有効なのが手洗いだが、一つ気をつけたいのが手を拭くタオル。
タオルは家族で共有しない
「家族で同じタオルを使ったり、数日間使用を続けるのは感染の原因になります。タオルは共有せず、使い捨てのペーパータオルを使用するのもいいでしょう。アルコール消毒は感染予防に役立ちますが、ノロウイルスはアルコール消毒では死滅させることができません。
ウイルスは下痢や吐しゃ物から感染するため、家族など身近な人に感染が起きたときは、使用したトイレなどは次亜塩素酸で消毒を行い、二次感染を防ぎます」(田中先生)
今年の夏も猛暑の予想。暑さが増すほどに食中毒のリスクも高まる。身近なことから感染対策をし、家族と自分の食の安全を守っていきたい。
実はキケンお弁当箱に入れると食中毒の可能性がある食材
・チーズやちくわ、かまぼこ
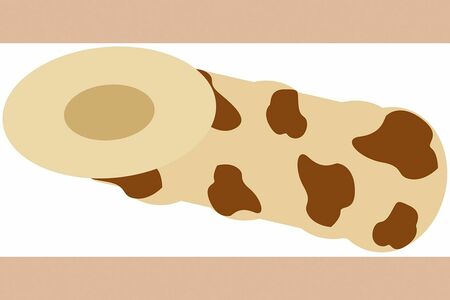
魚肉加工品などの要冷蔵食品をそのままお弁当に入れると、腐りやすく危険。ちくわならゆでる、炒める。チーズならグラタンにするなど、一度加熱すれば常温での持ち運びも低リスクに。
・炊き込みご飯

普通のご飯と比べ水分量が多く蒸し暑い季節は傷みやすい。殺菌効果のある梅干しや、ふりかけ、のりなど水分量が少ないもので味つけを。
・もやし
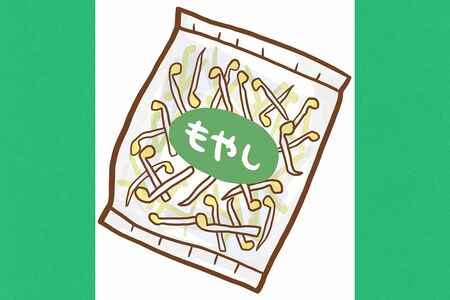
加熱後も水分が出やすいため蒸し暑い季節にお弁当に入れると菌などが繁殖しやすく、食中毒になる可能性も
取材・文/小林賢恵
三城 円さん 管理栄養士。芸能人や一般の方のダイエットなど延べ1万人以上の食事コンサルティングを実施。「食べながらキレイになるダイエット」を基本とした食事の大切さと内臓力を高める食べ方を伝えている。
田中雅之先生 医学博士、日本感染症学会専門医。KARADA内科クリニック渋谷院長。著書に『「コロナ」がもたらした倫理的ジレンマ』(日本看護協会出版)などがある。
