
今年は原爆投下・終戦から80年と節目の年。世界ではロシアとウクライナの戦争・ガザ地区での紛争が起きており、核戦争の可能性もある不穏な情勢だ。作者・中沢啓治さんの被爆体験が描かれた漫画『はだしのゲン』で、原爆について知った人も多いだろう。そんな作品が今、教育現場から消えつつある現状について、啓治さんの妻・ミサヨさんの心境は……。誰よりもそばで見てきた夫の苦悩、被爆差別、『はだしのゲン』誕生秘話について語ってもらった。
「やけどで皮膚がケロイドになって垂れたり、身体にウジ虫がたくさん湧いてハエになったり─。『あんまりひどく描くと子どもたちが怖がって読まなくなるから、少し抑えたらどう?』って夫に言ったんです。
そうしたら『何言ってんだっ、これでもまだ抑えているんだ。これくらい描かなかったら、原爆の恐ろしさがわからない』と、怒られてしまいました」
そう話すのは、漫画『はだしのゲン』の作者、故・中沢啓治さんの妻のミサヨさん(82)。
『はだしのゲン』は啓治さんの自伝的漫画で、6歳のとき広島で被爆。父と姉、弟を原爆で亡くしている。ただ当初、啓治さんが手がけていたのは娯楽漫画で、被爆者であることを公言していなかったという。
「被爆者に対する差別がすごくあったんです。なのでなるべく被爆者だとは言わないように、原爆の話は敬遠していました。だから、お母さんの死はよほど大きかったのでしょう」(ミサヨさん、以下同)
原爆漫画のきっかけは啓治さんの母の遺骨
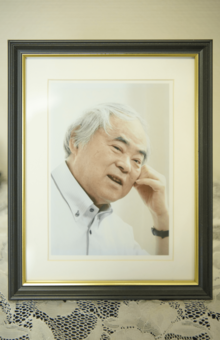
ミサヨさんが3つ年上の啓治さんと結婚したのは終戦から20年余り、1966年のこと。その年、啓治さんの最愛の母が亡くなった。
「夫と一緒に広島へお葬式に行きました。火葬すると遺骨がもうボロボロで、すべて灰になっていました。頭蓋骨すらありません。
原爆に対する怒りがそこで新たに生まれたのでしょう。広島から東京の自宅に帰る間じっと黙り込んで、ひと言も話さないんです。苦しいんだろうなと思い、私も何も言わずにいました。葬儀から2週間ほどたったころ、『原稿ができたから読んでみて』と夫に言われて。それが『黒い雨にうたれて』でした」
母の死に直面し、啓治さんが初めて手がけた原爆漫画である。しかし編集部に持ち込むと、「作品はいいんだけど、テーマが……」と言われてしまう。また別の編集部に持ち込むと、やはり「作品はいいんだけど……」と腰の引けた反応だ。掲載が決まったのはそれから1年後のことだった。
「『漫画パンチ』に持ち込んだら、すごくいい作品だからやらせてくださいと言われた、と。何かあったら一緒に責任を取りましょう、と編集長と言い合ったそうです」
『黒い雨にうたれて』は評判を呼び、『黒い川の流れに』『黒い鳩の群れに』と続く「黒い」シリーズに発展。原爆をテーマに短編を次々発表し、1972年には漫画雑誌の企画で自伝漫画『おれは見た』を描き上げている。
時にはベタを塗り、背景を描き、見よう見まねで啓治さんのアシスタントを務めていたというミサヨさん。啓治さんのいちばんの理解者であり、最初の読者でもある。
「私が初めて夫の被爆体験を知ったのは、自伝漫画を描いたその現場でした。夫が被爆したのは知っていたけれど、それまで私にも自分の体験を話さずにいたんです。
夫の体験はもう想像以上でした。被爆したのは爆心地から1・3キロの地点で、かなり近かった。何もない焼け野原で生きるということがどんなに大変か。まだ6歳の子どもがよく助かったなと思いましたね」
ある日、啓治さんのもとに長編漫画のオファーが届く。自身の原爆体験をベースにした連載だ。しかし当時はまだ被爆者に対する差別が根強く残っていたころ。「被爆者と接するとうつる」など根拠のない噂が流れ、蔓延していた。単発の読み切り企画とは違い、長期連載となると、被爆体験が世に広く知られることになる。
「私としてみれば、もう不安で不安でしょうがなかったですね。子どももこれから結婚や何やらいろいろあります。実際、生命保険の人に『中沢さんは被爆しているからお子さんも病気になる確率が高い』と勧誘されたことがありました。みなさん口に出さずとも、そう思っているんです」
しかし、啓治さんの意志は固かった。すでに覚悟を決めていた。
「知らないから差別があるんだ。だから子どもたちにわかるように教えなきゃいけない。次世代の子どもたちに知らせなければいけない。俺は今描かなくちゃいけない。記憶が残ってるうちに描かなければいけないんだ、と言っていました。今しかない、という思いが強くあったようです」
1973年、少年誌『週刊少年ジャンプ』で連載をスタート。少年誌での連載は啓治さんのかねての望みで、子どもたちに原爆のむごさを伝えたい、という願いも叶う。
『はだしのゲン』命名の秘話

「ずらっとタイトルの候補を並べて、『おまえ、どれがいい?』と聞かれました。漢字で書いたもの、カタカナで書いたもの、全部ひらがなで書いたものとさまざまです。ひらがなばかりだとちょっと物足りないし、カタカナばかりでもちょっと違う。
『これなら小学3年生でも読めるし、いちばん目立つんじゃないの?』と言ったら、夫は『俺もそう思う』と言って、『はだしのゲン』になりました」
原爆投下の1945年8月6日、ゲンは広島で被爆。奇跡的に助かるも、父と姉、弟はつぶれた家の下敷きになり、そのまま焼かれてしまう。母は原爆のショックで被爆当日に女児を出産し、ゲンは何もない焼け野原の町で母と力を合わせて生きていく。
「あのときは戦争孤児がたくさんいたんです。でも夫には母親がいた。『俺は母親が生きていたからまともな人生を送ることができた、もしあのとき母親が死んだら俺は野垂れ死んでいただろう』とよく言っていました。だから母親の存在は夫にとって特別だったんです」
漫画に描かれる家族構成やエピソードは啓治さん自身のもの。原爆の恐ろしさを知ってほしいと、自らのつらい記憶を直視し、身を削るようにして一コマずつ描き上げた。

「描いていると、お父さんたちの顔が甦るんでしょうね。痛かったろうな、熱かっただろうな、こういう死に方はつらいよなと言っては、ペンが止まっちゃうんです。
でも夫は決して手を抜きませんでしたね。自分の体験だから、嘘は書けないと言っていました。これは俺の勝負なんだ、この作品に命を懸けているんだ、戦争というのは想像以上に残酷なんだ。それを子どもたちに知らせなくてはいけない、という思いがありました」
伝えたいことは山ほどあるが、誌面には限りがある。連載当初は紙不足も重なり、与えられるページ数は絞られた。
「少ないページにストーリーを詰め込まなければいけなくて、コマがどうしても小さくなってしまう。だからなかなか迫力が生まれない。
そんな悩みをぶつけながら描いていました。少年漫画ということで、少しは娯楽性を加えなければと、読みやすいよういろいろ工夫も凝らしていましたね。当時流行っていた歌や、恋の話を入れたりもして」
創作活動にも影響を及ぼした被爆の後遺症
被爆の後遺症に悩まされ、創作活動にも影響を及ぼした。まず30代と若くして糖尿病を発症している。
「眠い、だるいと言っては、すごくたくさん水を飲むんです。ある日机に向かって漫画を描いていたら、そのまま意識を失い、ずるずると椅子から滑り落ちたことがありました」
原爆に焼かれた広島の町で、どんな困難に遭おうとも、ゲンはたくましく生きていく。それはまた啓治さん自身の生きざまでもあったという。

「漫画の中でお父さんが『ふまれてもふまれてもたくましい芽を出す麦になれ』と言うけれど、あれは実際に亡くなったお父さんから言われた言葉だそうです。助け合い、励まし合いながら何がなんでも生きていく。それが夫の本当に言いたいことでした」
1987年、14年の歳月をかけ、『はだしのゲン』はついに完結。被爆者自身による原爆漫画は珍しく、マスコミが大きく取り上げ話題を呼んだ。注目が高まると、講演会の依頼が舞い込むようになる。
「俺、講演なんかできないよと言って、最初は断っていたんですけど。どうしてもと言われて引き受けたら、やっぱり迫力が違う、すごくわかりやすい、と言われて。体験者自身の話を聞くことはそれまでなかったのでしょうね。
学校の先生方に『はだしのゲン』は引っぱりだこで、学級文庫に全巻そろったことがなく、もうボロボロになっていると言われました。うれしかったですね。漫画家冥利に尽きるというものです」
子どものころ学校や図書館で『はだしのゲン』を読んだ、という人は多いはず。
完結後もなお漫画の人気は高まり、連載継続の話が持ち上がる。期待に応えたいと再びペンを執るも、眼底出血により連載を断念。啓治さんは肺がんを患い、2012年に73歳でこの世を去った。生前はさまざまな被爆の後遺症との闘いが続き、がんもそのひとつといわれている。
現在『はだしのゲン』は25か国で出版され、世界中で読まれている。ミサヨさんのもとには今も海外の読者から反響が届くという。さらに昨年はアメリカ漫画界のアカデミー賞といわれる漫画賞『アイズナー賞』のコミックの殿堂入りを果たした。
「殿堂入りということで、トロフィーが送られてきました。アメリカからもらったということに意義がありますよね。日本だけではなく、海外の人も読んで、理解してもらえているということがうれしい」
教育現場から作品が見えなくなりつつある

一方で、日本国内では子どもたちの目から遠ざけられつつあるのが現状だ。広島市の平和教育副教材「ひろしま平和ノート」から『はだしのゲン』が削除され、また図書室での閲覧制限をかける学校も出現している。描写が過激だ、今の時代にそぐわない、などを理由としているが─。
「上のほうでいろいろ言う人はいるけれど、読者の方たちは好意的に受け止めてくれています。実際、子どもだってちゃんと読めばわかるんですよね」
市民の中から「『はだしのゲン』削除の撤回」を求める署名活動が起こり、多くの署名が集まった。NPO法人「はだしのゲンを広める会」も活発に活動を行い、漫画の精神の普及に尽力している。
『はだしのゲン』を語ること、それは原爆を語ることだ。
「夫が『はだしのゲン』を描く前は、原爆という言葉を口にすることすら難しかったのが、今は被爆者自身が実体験を話せるようになりました。これは大きな違い。話せるということは、平和が続いているということだから、どんどん話していただきたい」
戦後80年がたつ今、戦争をリアルに知る日本人は少ない。しかし国外へ目を向けると、ロシアのウクライナ侵攻に、ガザでの紛争と、近年は不穏な動きが目立つ。
「日本では戦争が起こらないと思ったら大間違い。油断できない、だからしっかり世の中を見て、上の人間が間違っていたら市民が怒らなくちゃいけないんだと、夫がよく言っていました。
いちばん先に被害を受けるのは市民です。実際、80年前の原爆で子どもたちは夢も未来もみんな閉ざされて死んでいった。けれど次の世代の人たちはその事実を全然知らない。みなさんにぜひ『はだしのゲン』を読んでもらいたい。原爆の怖さを知り、夫の思いを引き継いでもらえたらと願っています」
