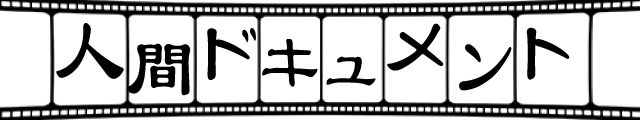山中しのぶさんが若年性認知症と診断されたのは6年前。当時は高校3年生を筆頭に3人兄弟を女手ひとつで育てていた。診断後、自殺も考えるほどのどん底を味わうが、そこから抜け出し、2022年に地元の高知県でデイサービス施設を開設。最近では多い月で12回の講演を引き受け、全国を飛び回っている。
笑顔があふれる取材当日

取材当日も、石川県での講演、千葉県で行われた学会のシンポジウムという連日の仕事を終え、羽田空港から高知に戻るタイミングだった。
取材時間ちょうどに空港のカフェに現れたしのぶさん(本人はこの呼び方がピンとくるというので以下同)。横にはデイサービスの介護職が座っている。しのぶさんは介護職に目をやりながら、こう笑い飛ばした。
「今回はこの、まりちゃんが同行してきてくれたんですけど、私が彼女をサポートする側になっているからね(笑)。道案内とかもいろいろ。それから島ちゃんも!」
視線の先には、初めての著書『ひとりじゃないき』(中央法規出版)の編集者・島影真奈美さんがいた。
「島ちゃんを信用して後ろを歩いていると、いつもの道を行くはずなのに、通ってない道を行こうとするから、私が、“島ちゃん、何か景色違うで”と言ってたら、やっぱり違う道やったこと、1日に2回ぐらいあったよね(笑)」
つられてみんなが笑っている。しのぶさんの周りはこんなふうに、笑顔があふれる。
しのぶさんと話していると、“認知症には見えない”と口にしてしまいそうになる瞬間がある。記憶は正確だし、話していても違和感がない。それは正直な実感なのだが、何度かそう言われ、そのたび傷ついたりやりきれなさを感じたりしてきたという。
「できないことが増える中で、たくさんの失敗を重ね、たびたび混乱し、死んでしまいたいこともあった。でも、なんとか生活できるように必死で工夫しているんです。それだけ必死の思いをしているのに、理解してもらえない。それがわかったとき、孤独感を感じたのです」
しのぶさんは、その苦しい思いを、身近な人が偶然実感したというエピソードを話し始めた。その人とは、5年前に再婚した夫である。
今年6月、夫と車で大阪に行ったときのことだ。買い物を終えて駐車場に戻ろうとしたとき、夫の様子がおかしい。焦っているのだ。
「どうかした?」と聞くと、「駐車券をなくした」と。急いで係の人に事の次第を説明すると、無料で再発行してくれ、喜んでいた。
一件落着かと思われたが、カフェでコーヒーを飲んでいるとき、またしても夫がカバンの中をがさごそ捜し始めた。
「どうした? 落ち着いて」
と話しかけると、
「また駐車券がない」
と言う。カバンの中のものを全部出して捜したがないと。
「落ち着いて。そういうことあるき、落ち着いたら出てくるき」
と言って財布を見せてもらったら、中にあった。
ホッとひと息ついていると、今度は「車の鍵を閉めたかどうかわからん」と言い出した。額に汗をかいて焦っている。一緒に駐車場に行き確認すると鍵は閉まっていた。しのぶさんはこう言った。
「まこちゃん(夫)、しんどかったね。でも私はね、毎日こんな混乱状態になるがで。わかった? 私の気持ち」
すると間髪を入れず言った。
「わかった。怖かった、ほんまにおまえの気持ちわかった」
そして握手を求めてきた。
「一緒に頑張ってやっていこうね。まこちゃんもいずれはなるかもしれんから」
しのぶさんは講演会などを通じて、認知症本人にしかわからない苦しさを伝えるとともに、自分が味わったつらい体験や孤独感を、ほかの認知症の人が味わうことがないようにしたいと考えている。デイサービス施設を営むモチベーションもそこにある。
会議の時間を忘れ、顧客の好みも忘れ……

しのぶさんが、「あれ? おかしい」と思い始めたのは、'16年のころのことだった。
当時、高校生だった長男・蓮さんがアメリカに短期留学していたので、内緒で渡米して驚かせようとした。アメリカでは楽しく過ごしたが、帰国した直後から身体がだるく、頭がぼんやりしている。例えば朝10時に待ち合わせ場所に行くには、何時に起きて何時に家を出るというような逆算が難しくなった。時差ボケだろう、寝たら治るだろうと思ったが、いくら寝ても良くならなかった。
それどころか、水道の蛇口を閉め忘れたり、当時は携帯電話販売会社で働いていたが、会議の時間を忘れたりすることも何度かあった。
しのぶさんは法人営業を担当していて、会社を訪ね、何げない会話の中から、機種変更のニーズを探ったり、業務効率が上がるシステムを提案したりする仕事だった。
「お客さんのことが大好きだから、以前は好きなスマホの機種や色、好きなケースやアプリなどは頭に入っていたんです、メモなんかとらなくても。ところが思い出せなくなったんですよ。機種名さえも出てこなくなって」
自宅でも「おかあ、また約束忘れちゅうで」と言われることが増え、三男を30分早く小学校に送り、校門が開くのを待ったこともあった。
不安が募り、脳神経外科で診てもらった。MRIなど複数の検査を受けたが、「(65歳未満で発症する)若年性認知症ではない」と診断。ただ、渡された書類には「境界線です」と書かれていた。
それ以降も物忘れは続いた。冷蔵庫に買った覚えのないものがあったり、冷蔵庫にあるのに同じ食品を買ったり、ネット通販で買ったのを忘れ、送られてきた商品に驚いたり。
再受診のきっかけは、テレビドラマを見ていたときだった。'18年秋に放送された『大恋愛~僕を忘れる君と』(TBS系)─戸田恵梨香演じる医師が若年性認知症になり、小説家の彼(ムロツヨシ)が10年にわたって支えるラブストーリーだ。
「一緒にドラマを見ていた蓮が言ったんです。“おかあ、この主人公と絶対同じ病気やき、病院に行って”と。自分の症状に似ているなという感覚はあったんですが、やっぱりそうなんやと」
今度は認知症専門クリニックを受診した。診断は「若年性アルツハイマー型認知症」。ショックで頭の中は真っ白に。傍らで説明を聞いていた母親も自分のことのように衝撃を受け、帰りの車の中でずっと泣いていた。
「ごめんね、こんな身体に産んでしまって。お母さんやったらよかったのに、代わってあげたい」
それに対ししのぶさんは、
「そんなふうに思わんといて。お母さんやなくてよかった。忘れられるほうがつらいき、私がいい」
言いながらわんわん泣いた。
高校を中退したりして親に心配をかけることが多かった。ようやく親孝行ができる年齢になったと思っていたら、またしても泣かせている自分が情けなかったのだ。
息子たちにもすぐに診断結果を報告した。すると蓮さんは「診断されたのは仕方ないきね」。次男の修矢さんからはLINEで「認知症に負けるな」という応援メッセージが送られてきた。
家族や職場の人たちに支えられたのだが─

しかしそれからはどん底だった。どうしてもインターネットで「認知症」を検索してしまう。すると「徘徊」「寝たきりになる」「何もかもわからなくなる」「家族に迷惑をかける」「寿命は数年」といった怖くなる情報ばかりが目に飛び込んできた。
たまらず涙を流しながら「忘れたくないリスト」を作った。まず書いたのは、わが子の名前と誕生日だった。
もし仕事ができなくなったら女手ひとつで子どもを育てられるのか。不安は増すばかりだった。その気持ちを察して、数か月後に大学入学を控える蓮さんが言ってきた。
「大学に行くのやめるき、おかあと一緒におる」
それに対ししのぶさんは、
「いや、蓮の人生やき。大学は行きたくて志願しちゅうき、行きや」
しかし先々のことを考えれば考えるほど不安になる。うつ症状も出てきて、夜、生命保険の証券を見ては、自殺でも保険金が下りるのかを確認することがあった。
そんな苦しい状況でありながらも仕事は続けた。直属の上司の協力もあったからだ。認知症になったことを報告したとき上司はこう言った。
「俺は認知症のことは知らんけど、仕事は続けてほしい。カバーするから何でも言ってくれたらいい」
仕事には厳しく、普段は怖いが、気持ちに熱いものがある上司はこう続けた。
「(認知症になったからと)色眼鏡で見られとうないき、ほかの部署には言わんといてほしい。もしヘンなことを言われたら俺が我慢できんから」
しのぶさんを必死で守ろうとしてくれる気持ちがうれしかった。同僚の中には、認知症になったことを自分のことのように受け止め、涙を流す女性もいた。
ありがたいことに周囲は快くサポートをしてくれた。
上司はまず、しのぶさんが担当していた約200ある得意先をほかの社員に振り替えた。さらに電話をかける予定を聞き、かけたかどうかを確認する。仕事を終えて日報を書いているときに、上司が仕事の進捗状況を確認する。
ほかの同僚数人も、例えば「今日持っていった充電器、売れた?」などと確認してくれた。捜しものをしている様子を察したら、「何、捜している?」と声をかけてくれる。とはいえ、完璧なフォローは難しい。顧客への訪問アポを忘れ、得意先から契約を解除するとクレームが来たことがあった。それでも仕事を続けさせてくれた。
「みんなさりげないサポートで、助けてくれました。認知症サポーター養成講座を受けたこともない、それほど認知症について知っているわけでもない人たちです。でも私の周りには一人も悪い人がいない。そんなお花畑があるのかと疑われるかもしれんけど」
子どもの学校の担任もさりげないサポートをしてくれた。例えば中学校から来る便り。さほど長い文章が書かれているわけではないのに、文意が頭に入ってこなくなったのだ。
「改行がない文章を読むのがしんどくなったんです。このころはうつ症状がひどくて、不安とか怒り、焦りが強かったので、毎日、頭がパニック状態ということもあったのだと思います」
担任に認知症であることを打ち明けた。するとその先生、「明日はお弁当の日です」とか「三者面談の日はどの日がいいですか?」と、重要なメッセージだけを選んで、ショートメールで送ってくれるようになった。
「これはすごく助かりました。先生もたぶん認知症の理解はない方です。でも認知症を理解するというよりも、私や家族が置かれている状況を理解しようとしてくれた。“認知症の私”ではなく、困っている私に“人として”対応してくれた。もし“認知症の人”扱いで“大丈夫ですか?”だけ言うような先生だったら、傷ついていたと思います」
家では、大阪の大学に行った蓮さんに代わり、修矢さんが母親をフォローした。
炊事をすると火が危ないけれど、炊事全般を奪ってしまうと母親は何もできなくなると修矢さんは考えた。そこで火は消しているか、冷蔵庫のドアを閉めたか、風呂の栓をしないまま湯をためていないかなどを、あるときはテレビを見ながら、また、トイレに行くふりをして確認していた。
認知症の診断後もしばらくは仕事を続けられた。が、職場で無理に明るく振る舞う分、家ではその反動でドッと疲れが出て苦しくなった。「どうして私ばっかりこんな思いをせないかんが」と泣いたこともあった。診断から数か月すると、出社できない日が増えていく。蓮さんに弟・修矢さんから電話があった。
「コンビニで、支払いを済ませていない商品を店内で食べようとしたり、虫を見ては、“私はこの虫のようにつぶされるがや”とつぶやいたりしていると。当時はうつ症状も強かったので布団から出てこない日が多くなっていたんですが、その電話を受けてすぐに高知に帰りました」
「笑顔で生きる」この言葉に助けられて
そんな状態がしばらく続いたあと、しのぶさんはネットの記事で、一人の若年性認知症の男性を知ることになる。宮城県に住む丹野智文さんである。自動車のトップセールスマンだったが、39歳でアルツハイマー型認知症と診断。絶望するが、職場の理解を得て仕事を続け、認知症本人たちとの出会いや、自身の工夫により日常生活を送り、著書を出版したり、講演活動をしたりしていた。
しのぶさんはSNSで丹野さんにメッセージを送った。
《今の私は嫌いです》
《なんとかしたいです》
すると著書を送ってくれ、すぐに読んだ。自分と同じような失敗に笑え、「笑顔で生きる」という丹野さんの姿勢に勇気づけられ、自分も笑顔になりたいと思った。
もうひとつ役立ったのは、スマホの活用法だ。丹野さんの方法を参考に、冷蔵庫の中の写真を撮れば、買うべきものがわかった。
客先でスマホの操作手順や設定画面を説明するときに備えて、説明画面を写真に撮っておくこともあった。記憶代わりにほぼ毎日撮り続け、スマホに残る写真枚数だけで、今年6月段階で3万4000枚を超えていた。
グーグルカレンダーも活用した。日程を書きアラーム設定しておけば、予定を忘れることはない。
乗り換え案内とマップ機能を使えば、知らない場所でも、目的地さえ決めておけば進むべき方向を示してくれて、迷わずに移動できた。
「スマホは自分の脳の一部ですね。自分の代わりに記憶してくれる機械。自分が足りない部分をうまくサポートしてくれる存在でもある。これを使いこなすことで、仕事も生活もしやすくなりました」
ただ、襲ってくる「孤独感」はスマホでは解決しなかった。親思いの子どもたちがいるのになぜかと思うが……。
「家でいるとね、子どもたちは学校に行き、バイトに行き、友達と遊びに行くから、家で一人になるんです。その時間がすごい孤独やった。仲のいい家族がおるから大丈夫という問題でもないんです」
そのころからしのぶさんは、自身が感じる孤独感を何とかできないかと考えるようになった。そして、「認知症であることを隠さずに生きる」のが最善だと思うようになる。助けてほしいとき「助けて」と言えないのも不安だった。しかし認知症であることをオープンにしたら、会社に迷惑がかかる。ここが潮時と'21年6月、退職を決意した。
学校に通う子どもがいる中で、仕事を辞めるのは勇気がいるが、前年3月に母校の同級生と再婚したことが決断をしやすくした。
「しのぶちゃんはしのぶちゃんで変わりない」

認知症であることをいつ公表するべきかタイミングを見計らっているとき、それは思いがけない形でやってきた。
'21年11月、「世界アルツハイマーデー記念講演会」が高知で開かれた。その日、丹野さんが講演をする予定だったのだが、あいにく体調を崩し、欠席することに。急きょ、丹野さんの講演原稿を代読して対処することになったとき、代読をしのぶさんが行うことになったのだ。丹野さんの欠席がわかったとき、ちょうど講演会の主催者と会っていたのも偶然だった。
「代読しているうちに、ふいにカミングアウトしようと思ったんです。丹野さんの原稿を読みながら涙が流れてきて、最後に、“私も同じ病気です”と付け加えました」
ただ、突発的にカミングアウトしたために、メディアには報道しないよう依頼した。というのは、両親や息子に許可を得ていなかったからだ。
「私がいろいろ言われるのはかまわないけど、家族が攻撃されるのは嫌だったから」
まず両親は、「何を言われても全然気にせん」という答え。しかし子どもたちの反応には拍子抜けした。
「え、もう俺、友達に言うちゅうで」
しのぶさんは「お母さんに確認せんが?」と言ったが、
「“そんなの関係ない。しのぶちゃんはしのぶちゃんやき、変わりないき、いいんじゃない”と、みんな言いよった」
蓮さんが、友達としのぶさんの関係を教えてくれた。
「うちには、僕が所属する野球部員とか、弟の部活の子らがよく来るんです、10人以上で。母親はみんなにごはんを食べさせ、恋の相談に乗ることもあり、おまけに泊まらせたりしていた。布団はコミュニティーセンターから借りてきて。だから友達は母をよく知っているんです」
蓮さんによると、カミングアウトしたことで、しのぶさんに笑顔が戻ってきたという。人がたくさん寄ってきて、「何がしたい?」とか「夢を叶えよう」と、明るい話をしてくれたのだという。
実は、会社を辞めたあと、しのぶさんは、デイサービスを運営しようと思い始めていた。幼いころから、“おせっかい”なぐらい人のお世話をするのが好き、という性格も関係しているかもしれない。
「小学生、中学生のころまで、私の大切な人を傷つけたりしたら、相手がたとえ男の子でも相手が降参するまでケンカしていました」
現在放送中のNHK朝ドラ『あんぱん』で話題になった“はちきん”。男勝りの女性を意味する土佐弁だが、しのぶさんはまさにはちきんだった。大切な人を全力で守る、人の世話が大好き─介護の仕事に就くのは自然な流れだったかもしれない。
しばらくして、若年性認知症の女性から、東京にある社会参加型デイサービス「DAYS BLG! はちおうじ」(以下BLG)を教えてもらい見学に行った。この施設では利用者を「メンバー」と呼び、認知症本人とスタッフがポスティングなどの仕事を一緒にしていた。
「間違ったら、誰かが教えてあげて、助け合っていました。スタッフとメンバーが立場を越えて、人と人との関係性の中で社会と関わっていた。私のやりたいのはこれだ、と」
自分が入りたいと思う施設をつくりたい

決めたら行動は早かった。介護のことはまったく知らなかったので、一から勉強し、法人をつくるために司法書士、社会保険労務士に依頼した。法人名は最初「ストーリー」にしようと考えていた。
「認知症でどん底のころによく聴いていたのが、AIさんの『Story』だったんです。〈ムリして笑うコトもしなくていい〉〈疲れた時は肩をかすから〉〈私がキミを守るから〉という歌詞を聴いて、“私、一人じゃないんだ”って勇気づけられたんです」
「いや、『セカンド・ストーリー』にすれば」と提案してきたのは蓮さんだった。理由は「認知症になってから新しい人生が始まったから」。即採用となった。
デイサービスが目指す方向性も明確だった。
「誰一人、私が味わったような孤独感とか、つらい思いをしてほしくない。住み慣れた地域に、自分でいられる居場所をつくる。第二、第三の家族みたいな存在になる。いつか私も施設のお世話になるときに、自分が入りたいと思える施設をつくりたい」

施設の名前は「でいさぁびす はっぴぃ」。オープンは'22年10月だった。しかし初日は閑古鳥が鳴き、従業員5人と一緒にふて寝したという。その後、ケアマネジャーや地域包括支援センターからの紹介で徐々に利用者が増加していったが、最初は“素人集団”と言われた。介護の経験が3年未満の人を集めたからだ。経験豊富な人だと対立する可能性がある施設運営をしようとしていたためだった。
例えば時間割をつくらない。折り紙、歌といったものはやらないと決めていた。しのぶさんは、
「何をするかではなく、誰と何をしたいかを大事にしたいからです。集まったメンバーで“今日は何しよう”と話し合いながら決めていく。でも折り紙したい人がいたらやりますよ」
最初はお弁当を取ろうと思っていた。しかし、やり始めてから変更した。自分たちで食べたいものを話し合って、自分たちが作るのが楽しいし、おいしいと気づいたのだ。
マグロが食べたいという要望に応えた日のことだ。
「私がマグロを料理しているとき、“そんな包丁の使い方いかん”と言うメンバーさんがいたんです。その人、包丁を持って上手にさばいてくれた。私が“(若いころ)何しよったが?”と聞くと“漁師しよった”と。骨についた赤身を捨てていたら、もったいないと注意されて、“スプーンを持ってきなさい”って」
前出の編集者・島影さんは、たこ焼きパーティーが印象深いという。それぞれのメンバーが食べやすいたこのサイズを聞いて作るのだ。
「はっぴぃは“勝手に決めず、本人さんに聞く”を徹底しています。しのぶさんが言うには、“家族や友達だったら、これぐらいの大きさでいい?と聞くでしょ”と。それと同じことをやっているだけよって」
BLG(前出)で学んだ「働くことで社会に参加する楽しさ」を感じてもらうプログラムも行った。
働くことは社会とつながるツールのひとつ

自動車ディーラーでの洗車とお客様へのプレゼント包装、マンションや製薬会社の掃除、ミカンの収穫、デイサービスの中でやる内職として、身体を拭くシートを密封する仕事。これらは、しのぶさんが営業して開拓したものだ。
島影さんによると、洗車ははっぴぃのメンバーだけでなく、ディーラーで働く人たちも一緒に行うという。“丸投げ”ではないのだ。
「すると、ディーラーの人たちもはっぴぃのメンバーに対する理解が深まって、これもお願いできるんじゃないかと仕事も広がるんです。例えば“こどもの日”にショールームで配るお菓子の袋詰めとか、花壇の手入れとか。“認知症の人”ではなく仲間として理解し“共に生きる”を一緒に考え、実践する場になっているんです」(島影さん)
ボランティアは、希望したメンバーが参加するのだが、しのぶさんによると、メンバーがボランティアをすることで変わることがあるという。それまであまり意欲がなかった人が目標ができて活動的になったりするのだ。
「うちは有償ボランティアなので、ディーラーさんで働くと1回830円をもらえるんです。90歳のメンバーは、この年で人様からお金をもらえることはすごく大きな経験だったようで、830円を握りしめ喜んで帰っていかれました。有償ボランティアのお金を1年間貯めて、孫へのお年玉にしている人もいます。今までは家族に世話してもらって“ありがとう”“ごめんね”と言っていたのが、家族からの“ありがとう”をもらえるのはうれしいものです」
ただ、「働くことが目的じゃない」とも言う。
「働くことは社会とつながるツールのひとつなんです。働きに行かなくても、明日、またはっぴぃに行きたいと思える居場所であり続けたい」
しのぶさんは、自分の意見をはっきり言うが、しかしそれにこだわらず、「すり合わせる」ことを大事にする。メンバーの反応を見て、一番いい表情や反応が返ってくる方法を柔軟に考えていく。スタッフとの意見の食い違いも話し合いで妥協点を見いだす。
現在、施設は2つある。最初の香南市の施設と'24年に高知市に開設したそれ。メンバーは2施設合わせて49人、スタッフも27人。当初、誰も来なかったのが嘘のようだ。
しのぶさんの息子たちもはっぴぃに関わっている。蓮さんは不動産会社で働きながら、セカンド・ストーリーの副理事を務め、修矢さんは介護職として働いている。
冒頭に書いたように、しのぶさんは、はっぴぃ以外の仕事も増えてきた。講演会のほかにも、'22年には、高知県から、認知症本人大使「高知家希望大使」に任命され、認知症の普及啓発活動などに協力することに。
さらに'24年には、世界アルツハイマー病協会の国際認知症専門家委員会の委員に就任した。しのぶさんと親しく、国際会議にも一緒に参加したことがある、看護師の鷲巣典代さん(日本認知症国際交流プラットフォーム国際交流委員)は、海外でのしのぶさんの様子をこう話す。
「しのぶさんは少しの英単語と身ぶり手ぶりを使ってコミュニケーションしています。彼女はオープンマインドで駆け引きみたいなものがなくて直球勝負。人と通じ合う力があるから、国境や人種を超えてすぐに仲良くなるんです」
今年、しのぶさんを主人公にした映画が製作されることが決まり(来年公開予定)、日本認知症本人ワーキンググループ(JDWG)の代表理事に就任した。海外の学会や講演会もあって、今年は韓国、台湾、香港、来年はフランスに行く。鷲巣さんは言う。
「いろんな仕事をしてプレッシャーもあると思うけど、彼女はめげないし、ブレない。それははっぴぃにいる人を幸せにするという信念があるから。その軸足がある限り、彼女は大丈夫ですよ」
しのぶさんは、これからの活動についてこう話す。
「人生の最終章まで一緒におれる場所をつくるために動きます。講演会で行く各地でも仲間ができて、それぞれで居場所をつくってくれたらなと思っています。それが全国に広がればいいなと」
若年性認知症の人の数は約3万5700人('19~'20年調査)。また厚生労働省によると、認知症の人の数は'25年中に700万人に達すると推計されている。しのぶさんが発するメッセージや活動は今後さらに貴重になる。
<取材・文/西所正道>