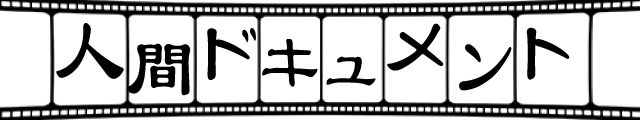ゴールデンウイークでにぎわう大阪・関西万博。「未来医療」をテーマとした国際赤十字・赤新月運動のイベント会場で、ひときわ注目を集めていたのが、フェイシャルセラピスト・かづきれいこさん(73)の体験ブース。やけど痕や傷痕を目立たぬように隠す“リハビリメイク”という独自の技術を紹介していた。
フェイシャルセラピストの仕事

「この傷でも隠せますか?」
不安そうな表情でブースを訪れたのは、北海道から来場していた40代のAさん。
BCG接種痕がきっかけとなった二の腕にある7センチ四方のケロイドを見せ、かづきさんに悩みを打ち明けた。
「幼稚園のころからケロイドが出始めて、今は手のひら5つ分ほど全身に広がっています。痛み、痒みはつらいですが、それより醜悪な外見を見られたくなくて。隠せる服装を選んで生活しています」
もともとケロイド体質で、ケガややけどなど皮膚の炎症をきっかけに赤く盛り上がった傷痕ができやすいという。この病気の特徴は、もとの傷の範囲を超えて広がり、時間の経過とともに赤く盛り上がって、ひきつれを起こす可能性があることで、当人の不安は尽きない。
「今、気がかりなのは、胸のケロイドが顔のほうへ広がってこないかということです」
かづきさんは、Aさんの傷を優しくなでると、「大丈夫よ。ちゃんと隠れるからね」と微笑み、肌に密着する超薄型の「かづき・デザインテープ」を傷痕の上に貼った。
「ちょっと触ってみて」と促されたAさんが、テープが貼られた部分に手を添えると、「デコボコしてない!」と思わず声を上げた。
これは、手術痕やリストカット痕などの肌の傷痕を目立たなくする目的でかづきさんが約13年かけて企業と開発したものだ。傷痕は凹凸があることで光反射などの影響を受けて目立ちやすいため、まずは無色透明のテープで皮膚をなだらかにするという。
かづきさんは、テープの上から「かづきイエロー」といわれる黄色のファンデーションをスポンジに取ると、ベージュ色と混ぜながら、軽いタッチで塗り広げ、仕上げにフェイスパウダーを少しずつ重ねていった。
施術時間は、わずか10分ほど。あっという間に、ケロイドと普通の肌との境目はわからないほど自然になった。「はい、完成! 水に濡れても崩れないから、プールや温泉も入れるわよ!」
かづきさんが言うと、Aさんの目から涙がこぼれた。
「メイクでここまできれいになるなんて。今まで自分の中で抑えてきた気持ちが込み上げてきてしまって……。胸や腕にあるケロイドは特に憎たらしくて、Vネックやノースリーブは到底無理。いつも隠れる服を選び、それが私の宿命で、ほかに選択肢はないと思ってたから……」

かづきさんは「よく頑張ってきたね。よかったね」と優しくAさんの肩を抱いた。
「リハビリメイクは、事故やがん、口唇裂・口蓋裂の手術痕など、さまざまな外傷に悩む方が社会に一歩踏み出すために習得するメイクなんです。医療で処置した後、残ってしまう傷痕に心理的ストレスを抱える方はたくさんいます。人前に出る仕事を諦めたり、外出を控えたり、そこに心のケアと課題があるんです」
大学病院にリハビリメイク外来

かづきさんは、医療の専門家と連携し、大学病院に「リハビリメイク外来」を設け、患者の施術をしている。
そのほか、百貨店への店舗出店、自身のサロンなどでも施術を行うことで、多くの患者と出会ってきた。
「最初は私が施術をしますが、自分でメイクできるようになると、いつでも隠せるという安心感から、次第に気にならなくなり、メイクなしで出かけられるようになる方もいます。最終的なゴールは、傷を隠すことではなく、受け入れ、『もう気にならない』と思えるようになることなんです」
Aさんからは後日、こんな便りが届いた。
〈ケロイドによって傷ついていたのは体だけではなかったと実感しました。リハビリメイクで、マイナスの自己肯定感を出発地へ立たせることができ、未来や可能性を大きく感じる、そんな体験でした〉
5年ぶりにメイクした難病の妻と夫の願い

大阪・関西万博のブースで順番待ちをしていた中に、車いすに乗って夫に付き添われた60代の女性、Bさんがいた。夫に「僕も頬にできたシミをカバーしたいから、一緒にやってみよう」と誘われて、立ち寄ったという。自らが抱える病についても話してくれた。
「ネマリンミオパチーという筋力が低下していく難病を患っています。手が上がりにくくなってきたので、顔を洗うのも不自由ですし、メイクはもう5年くらいしていません。会社員だったころは毎日してたんですけどね。お化粧をしなくなったら、外出するのも億劫になって……」
万博会場の近くに住む夫妻は「朝の散歩がてら通ってみよう」という夫の提案で通期パスを購入。その日は7回目の来訪で、たまたま前を通りかかったという。
かづきさんはBさんの話に耳を傾けながら、目のまわりと頬骨、顎、首筋にかけて強弱をつけながらマッサージを行った。「気持ちいいです」とリラックスしているBさんのフェイスラインは、むくみが解消されたのか、すっきりとした印象になった。
続けて、耳の後ろやこめかみに細いデザインテープを貼ってシワやたるみを引き上げ、眉を整え、ナチュラルメイクが加えられた。
「わぁ、すごい! お化粧をしたのは本当に久しぶりですけど、やっぱりいいですね。このテープ、自分でもできるようになりたいです」
鏡を見て喜んでいるBさんを見守っていた夫が言う。
「妻が前向きに毎日を過ごせれば、病気の進行を遅らせることができるかもしれないし、そのうち再生医療など新しい治療を受けられるようになるんじゃないかと期待しているんです。メイクは気軽にできて、とてもいいですね」

夫もシミをカバーするメイクを体験し、夫妻はお互いの顔をのぞき込みながら、笑顔で会場をあとにした。
リハビリメイク向上のため、開発された「かづき・デザインテープ」は、シワやたるみを引き上げるリフトアップ効果も期待できると思わぬ話題を呼び、シリーズ累計販売84万個となっているベストセラー商品でもある。
傷痕に限らず、加齢による顔の悩みをケアするメイクもまた、かづきさんが大切にしてきた活動のひとつだ。
「『顔じゃないよ、心だよ』ってよく言われますけど、それはきれいごとだと思っています。顔に悩みがあると、本当に元気になれないんです。
リハビリメイクには、一人ひとりの物語があります。私は何万人もの悩みに向き合って、技術を身につけてきました。最初は『たかが化粧』と言われましたけれど、これは医療だと思っているんです」
持病を抱え、「生きるためのメイク」が必要だった、かづきさんの軌跡をたどった。
「赤デメキン」と言われないための厚化粧

小学生のころのあだ名は、「赤デメキン」。この名に深く傷ついた経験こそが、かづきさんの原点である。
1952年7月、大阪府に生まれた。銀行員の父と専業主婦の母のもと、何不自由ない家庭で育ったが、身体が弱く、運動するとすぐ息が苦しくなった。冬は血流が滞り、顔が赤くむくんだため、悲しいあだ名がつけられた。
「今では笑って話せますが、当時は本当に嫌でしたね」
思春期になると、悩みはさらに深刻に。春から夏は元気に過ごせるのに、冬になると顔の赤みが強くなるとともに気分も沈み、成績も落ち込んだ。まるで二重人格のようだったという。
高校2年のある日、赤い顔を隠そうとファンデーションを塗って登校したところ、教師に「すぐ落としなさい」と叱られた。「みんなと同じ肌色に近づけたかっただけなのに」と心の中で叫んだが、思いを言葉にできなかった。
母のすすめで短大へ進学。肌の赤みを隠すメイクに夢中になる。
「周りから、厚化粧だとか白すぎると言われても、赤い顔を見せるよりは、ずっと心が楽だったんです。外見のコンプレックスが性格や体調、社会生活にも影響すると身をもって知りました」
21歳で内科医の夫と結婚し、2年後には長男を出産。育児に追われる中でも、冬になると厚化粧をする習慣は変わらなかった。
転機は30歳。母の死と夫の開業が重なり、過労で倒れてしまう。検査の結果、心臓に穴があいている「心房中隔欠損症(ASD)」と判明。緊急で受けた手術は無事成功し、血流が改善されて、長年悩んできた顔の赤みも消えた。
「真っ赤な顔から解放されて、今なら何か始められるかもしれない、と思いました。それまで、母の望んだ“良き妻、良き母”としての人生を歩んできたけれど、母の死をきっかけに、初めて“自分の人生を生きたい”と思ったのかもしれません」
素人主婦の“当たって砕けろ精神”

進む道に迷いはなかった。苦しかった時期に自分を支えてくれたメイクの力を信じ、本格的に学ぶ決意をする。
大阪の美容学校に入学し、10代の若者たちと机を並べた。しかしそこで教えられていたのは、女優やモデル向けの華やかなメイクばかり。
「きれいな人のためのメイクは世の中にあふれていました。でも、肌にトラブルを抱えた人が元気になれるメイクを学べる場所は、どこにもなかったんです。それなら自分で始めようと思いました」
地元の兵庫県芦屋市のカルチャーセンターに電話をかけ、無謀にも、メイク講座を開きたいと申し出た。
「前向きに生きる力になる“普段着メイク”を広めたい」
そう熱弁したが、「無名の主婦に講座を任せるのは難しい」とあっさり断られて落胆。しかし後に、「1日限定なら」とチャンスが舞い込む。
「私はがぜん張り切って、全力で準備をして臨みました」
講座は大好評で、翌期から正式に開講されることに。
「この“当たって砕けろ精神”で、ずっとやってきたんです。素人のくせにずうずうしいとか、断られたらみっともないなんて考えずに、やりたいことがあるならまず動く。それが私のやり方なんです」
講座には20代から70代まで、幅広い年代の女性が集まった。小さい目、低い鼻、ニキビ痕、アトピー、加齢によるシミやたるみなど、それぞれに悩みを抱えていた。かづきさんは顔立ちやライフスタイルに寄り添い、「その人らしさ」を大切にするメイクを提案した。
当時の受講生で現マネージャーの渡辺聡子さん(55)はこう振り返る。
「派手な神戸ファッションで、いつも明るくて元気なんです。講座の半分以上、世間話や冗談ばかりで、『先生、そろそろメイクを』って言われるほど(笑)。『思い切り笑いたくて来てる』という人もいましたね」
受講生たちの心をほぐし、前向きな気持ちを鼓舞する。そんな笑顔あふれる講座はたちまち評判となり、2年後には東京でも開講が決まる。
青山にスタジオを開設すると、次第に顔の傷痕に悩む人の受講も増え、「誰もが安心して学べる場所をつくりたい」と、地方からもアクセスしやすい四谷へ移転した。
顔の悩みで命を絶った20代女性

ある日、東京のカルチャーセンターに20代後半のCさんが訪れた。深くうつむき、最前列に座ったCさんは、高校1年生のときに脳の難病を発症。その影響で顔全体に重度の吹き出物ができていた。顔が原因で高校を中退。就職先は帽子とマスクで顔を隠せて、誰とも会話をする必要がない清掃の仕事しか選べなかった。
肌は赤みが強く、凹凸も目立ち、一般的なメイクでは隠せなかった。かづきさんは当時持てる限りの技術を尽くしてメイクをし、Cさんはその仕上がりを喜んだ。だが、かづきさんにとっては満足のいくものではなかった。
「どうしたらいいか、一緒に考えてあげることしかできなかったんです。でも、彼女からたくさんのことを教わりました。例えば、顔に悩みを抱える女性にとって、姉妹など身近な同性との比較がどれほどつらいか。身体は健康なのに、顔の悩みによって社会に出ていけないことがどれほどストレスになるか……」
その後、Cさんは形成外科で手術を受けたが、半年もたたないうちに再発。病気が完治しない限り顔も元に戻らないことを知ると、精神面が不安定になっていった。かづきさんは頻繁にかかってくる電話に応じ続けたという。
後に、形成外科医から精神科医を紹介されたと聞き、ただCさんの回復を願っていた。
しかし1年後、Cさんは自ら命を絶つ。
「本当にショックで、救えなかったことを悔やみました。医療に託したという安心感で、その後の社会復帰まで支援するという心構えが欠けていたんです」
顔の悩みが、人の命を奪うこともある─かづきさんは、そんな現実を思い知った。
生きていくために必要なメイク
約30年前、かづきさんがメディアで注目され始めたころ、ある看護師が全身にやけどを負った20歳の女性を連れてきた。
彼女は手術により医療的な治療を終えたが、顔にやけどの痕が残っていた。看護師は「外見のリハビリも必要」と、痕が目立たなくなるメイクを教えてほしいと頼みにきたのだ。
「このとき、“リハビリメイク”という言葉が生まれました。医療従事者が私のメイクをリハビリの一環と捉えてくれたことが、医療とメイクの連携に取り組む原点になったのです」
かづきさんは、メイクだけでは難しい傷痕や凹凸をどこまで自然にカバーできるかという課題に直面していた。
「メイクだけでは傷痕が浮いて見えたり、光ってしまうので、人工皮膚のようなシートが欲しいと思ったんです」
テープ材メーカー勤務の親戚がいることを思い出して相談してみたが、「そんな極薄のテープは前例がないし、無理だ」と言われる。しかし、粘り強く交渉し続け、試作を重ねた。
「13年の月日が過ぎて、もう諦めかけたころ、『これ、使えるかな?』と持ってきてくれたのが、まさに私が思い描いたテープだったんです。光らず透明で、肌との段差ができないほど極薄で、負担も少なく、上からメイクできるもの。鳥肌が立つほどうれしかったですね」
冒頭で紹介した、かづき・デザインテープ誕生の瞬間だ。それ以降、リハビリメイクで対応できる症例も増えた。
そして、Cさんの痛ましい出来事を教訓に、1999年からは大学病院の形成外科や歯科外来で調査研究のため、リハビリメイクを開始。医療現場との連携を本格化させた。
スタージ・ウェーバー症候群で顔に血管腫のあるDさん(64)も、かづきさんに救われたひとりだ。皮膚移植の経験に加え、右目の視力を失い、公共の乗り物で人に顔を見られることに強い苦痛を感じていたという。
「以前の隠すメイクは厚ぼったくて気が滅入りました。でも先生のメイクは軽やかで、自分らしさを大切にできる。イエローのベースを塗れば、ほとんどナチュラルで済むんですよ。人の目が少し気にならなくなりました」
現在、Dさんは社会福祉の仕事をしながらひとり暮らしを続け、娘や孫の成長を見守る。自分の力で生活し、好きなことを楽しめる今が幸せと語る。
Eさん(58)も2歳のときに負った口元の傷に長年悩み続けてきた。美容整形手術を考えたこともあったという。
「先生はまず、私の傷にいっぱい触れて、鼻の下に線が2本あるように見えるよねって、私の悩みをそのまま言葉にしてくださったんです。『年齢とともにたるみで傷が目立ちやすくなるけど、これを続ければ変わってくるからね』とマッサージしてくださって」
傷痕が薄くなるよう上から小さなテープを貼り、ファンデーションで整えた後、ピンク系メイクで仕上げた。
「整形しなくても、こんなに変われるなんて……と涙が出ました。もうすぐ還暦だからマスクで隠して生きようと思ってたと話したら、『なに言ってんの? まだ若いじゃない、これからよ!』って先生が励ましてくださって」
その後、Eさんは髪形を変え、心機一転したという。
「顔はどうしても人の目につきます。私のようにずっとひとりで悩んでいる人は多いと思います。そんな方こそ、かづき先生の“魔法のメイク”を試してみてはと思います」
美容整形が身近になった今こそ、「女性の顔を守りたい」とかづきさんは声を強める。
「否定するつもりはないけど、気軽に繰り返すことには注意が必要ですね。美容整形って“家の増改築”に似ていて、何度も繰り返すとバランスが崩れるように、顔も自然な感じがなくなっちゃう」
手術を繰り返す人の背景には、外見への強い執着や精神的な不安もあるため、精神科との連携も大切だという。
「顔は一生に一つしかない大切なもの。だからこそ、メスを入れる前に、まずはメイクで理想に近づく方法を試してほしいと願っています」
大学病院に「メイク外来」を新設

2000年、かづきさんは精神科医や形成外科医などと連携した多角的な研究を進めるため、「顔と心と体研究会」を設立。2014年には公益社団法人となった。
活動を共にしてきた日本医科大学形成外科学教室主任教授・小川令さん(51)は、「リハビリメイクは医療の限界を補う重要な存在」だと話す。
「医療の進歩で手術によって命が救われても、外見の傷に悩み、人前に出られず、社会から孤立する患者さんは少なくありません。まさに“生き地獄”ともいえる状況です。かづき先生は、外見に悩む患者さんの生きる意欲や、再び社会とつながる力を引き出してこられました」
設立当初は、「化粧が医療になるのか?」という懐疑的な声も多かったそうだ。
「先生は逆風にも一切ブレず、現場で患者さんと丁寧に向き合い、“結果”で示し続けてこられました。例えば、熱傷で顔に瘢痕が残った患者さんが、リハビリメイクによって外出する勇気を得て笑顔を取り戻した姿は、医師や医学生に強い感銘を与えました」
こうした実績が評価され、日本医科大学付属病院など複数の大学病院で「リハビリメイク外来」が新設されていく。かづきさんは、日本形成外科学会や日本美容外科学会などでも研究成果を学会や論文で発表。メイク外来の増設や保険適用化なども目指している。
「リハビリメイクを求めて来る患者さんと向き合う時間こそ、自分らしくいられる瞬間。肩書のない私に悩みを打ち明け、傷を見せ、顔を触らせてくれた患者さんから、今の技術や考え方が生まれました。だから患者さんこそが、私の先生なんです」
高齢者の笑顔を生むボランティア
梅雨入り前の休日、神奈川県横浜市の特別養護老人ホーム「緑の郷」には、入所者の笑顔があふれていた。かづきさんが8人のボランティアとともに訪れ、高齢者にメイクをしていたのだ。
脳の病を乗り越え、最近入所した頼明美さん(88)を見るや、「あら、肌きれい! 明美ちゃん? よろしくね」と瞬時に緊張を解く声かけをしたかづきさん。まずハンドマッサージを行い、手のシミをカバー。丁寧なスキンケアのあと、ファンデーションを塗り、仕上げにチークとピンクオレンジの口紅を塗ると、鏡を見た頼さんは「あら~すごいわね。別人! 帝国ホテルに行かなきゃ!」と華やいだ笑顔を見せた。そばにいた娘さんが「昔、父とデートでよく行っていたのを思い出したのかな? 今日は頭がはっきりしていて、笑顔が違う」と驚いた。
施設の理事・古川幸子さん(75)はこう話す。
「先生が温かい声かけをしてくださるので、会話も弾んで、先生に会えるのを楽しみにする方が増えていきました」
1992年、40歳のときからこの活動を始めたかづきさんも、今では入所者の世代に近づいてきた。
「老人同士のメイクになってきたねって笑っています。私の母は56歳のときに亡くなったので、高齢の方を見ると、生きていたらこのくらいだったかなと思って。『してあげたいと思ったときに、その人はいない』っていうじゃないですか。だからこちらでのメイクは、母にできなかったことをしているようで、私も幸せな気持ちになるんです」
続けていれば、必ず評価される
会社を立ち上げて36年。企業の30年生存率が0・02%ともいわれる中、かづきさんは「ほそぼそとやってきただけなのに、奇跡みたい」と笑う。
「主婦だった私は、ビジネスなんて全然わからなかったし、借金もできなかった。夫からの援助も一切なし。それでも、時代の流れとスタッフの支えがあって、ここまでこられたんです。感謝しかないですね」
秘訣があるとすれば、「とにかく続けたこと、それだけ」と言い切る。
「どんなに小さなことでも続けていると、評価してもらえます。どんな大きな花火を上げても途中で終わったら、やっぱりねって言われちゃう。仕事もボランティアも、やると決めたらライフワークとしてずっと続ける、それが大事だと思うんです」
30歳で美容学校に入った当時、周囲の目は冷ややかなものだった。
「いい年して何考えてるの?と言われました。でも2年後には『まだやってるの?』、5年後には『よく続くわね』、10年後には『私にもメイク教えて』と変わっていった。人の見方なんて、そんなもの。どう思われるかより、どう生きたいか。人生の主役は、いつだって自分なんです」
そう話した後、ポツリとこう付け足し、目を細めた。
「仕事一筋の人生で、気づいたら、本名・内田嘉壽子の友達はほとんどいなくなっていたの。かづきれいことしての仲間は増えたけれどね」
息抜きは書道や華道に没頭したり、孫娘と語らうことだという。そして、最後にこう語ってくれた。
「私はとにかく人の顔が好き。目鼻立ちよりも笑顔に惹かれるんです。ご高齢の方のきれいな笑顔には、人生の素晴らしさがにじみ出ている気がしますよね。私の憧れです。
そしてとにかくメイクも大好き! いつか『ご臨終です』なんて言われても、棺桶をのぞき込んできた人の眉がボサボサだったら、手が伸びちゃうかもしれないわ~(笑)」
「赤デメキン」と呼ばれた少女は、やがて幾千もの顔と向き合い、涙を笑顔へ変える“魔法のメイク”を生み出した。七十の齢を重ねた今もなお、最前線に立ち、生きる力を届けている。
<取材・文/森きわこ>