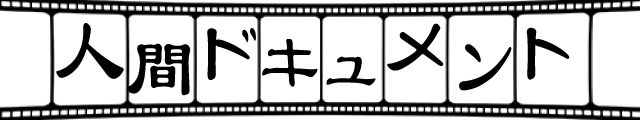暴力のサバイバーであり、摂食障害や引きこもりも経験したエッセイストの石田月美さん(42)は、主治医の助言をきっかけに婚活し、結婚した。そして出産し、現在2人の子どもを育てている。彼女の家には近所の子どもたちが遊びに来る。主婦として忙しい一方で、自身の生きづらさの話を中心に執筆活動をしている。
引きこもり時代から一転して婚活をし、結婚するまでの話として、デビュー作『ウツ婚!!─死にたい私が生き延びるための婚活』(晶文社)を執筆した。「ビョーキ」のまま社会とつながることが、「ビョーキ」からの回復に有効として、「ウツ婚!!」というセミナーも立ち上げ、精神科病院の施設で講座を開いた。
自伝的エッセイ『まだ、うまく眠れない』で綴った滑稽さ

自伝的エッセイ『まだ、うまく眠れない』(文藝春秋)でもシリアスな状況を明かしながらも自身の滑稽さも綴った。生きづらさの回復と恋愛や結婚、家族という物語を結びつけるのは、福祉や医療の支援の現場ではなかなか肯定されない話だ。ただ、石田さんは作品で挑戦をしている。
「私が婚活セミナーをしていたときも、さまざまなシンポジウムや学会に行きましたが、支援者たちと話すと、鼻で笑われました。『変なことやっていますね』って。婚活や恋愛って、(生きづらさが)ひどくなるイメージがあって。でもセミナーに来てくれる彼女たちは私の話を求めてくれたんです」
精神科に行くと、こころの話ばかりになるが、生活の立て直しが先ではないかとも感じた。
「精神科の患者仲間と話していると、“暑くても生活保護なのでエアコンをつけちゃダメ”とか言う人が多いんです。布団乾燥機を持っているのに、“(自分には)使う資格がない”と思ってしまうんですね。そういう話を聞いていると、日常生活を見直すことが、こころ(の回復)につながるんじゃないかと思ったんです」
そうした思いもあって、恋愛や結婚を回復の手段として考えたものが、『好きで一緒になったから』(晶文社)にまとめられた。福祉の現場では、恋愛や結婚を回復の手段として位置づけるのはタブーな面がある。そんなテーマの本を、これまでに『家のない少女たち』などを書き、高次脳機能障害があるライターの鈴木大介さんと共に出した。鈴木さんは石田さんのことを、
「これまで取材してきた人と時期が違いますが、“取材してきた子たち”の延長線上にいる人だなと思いました。それに、僕自身が高次脳機能障害の当事者で、妻も障害があります。だからか、石田さんには学ぶことが多いんです。(困難な道を)先に行った人という意味で、『月美先輩』と呼ぶことがあります」
アルコール依存症の父。暴力を必死に止める母
石田さんはフランスで生まれた。両親は現在、共に翻訳業だが、石田さんが幼いころの父は、ドーバー海峡のトンネルまで行き、通訳をして出稼ぎをした。小学校に入学する前に日本に越してきたという。
「多忙だったこともあり、父はほとんど家にいませんでした。東京に住むようになっても父は海外で単身赴任でした。両親2人で翻訳会社を営んでいて、母は東京の事務所で、父から上がってきた通訳の原稿を手直しして校正をかけるということをしていました。
小さいころ、父が日本に戻ってくると、トランクの中にたくさんのお土産が入っていたのを覚えています。ただ、逆に、父との毎日の思い出はないですね」
父親はずっとお酒を飲んでいる人だった。
「お土産と父の帰りはうれしかったです。でも落ち着いた後で飲酒が始まります。それはつらいですよね。暴力もありますから。殴られますよ、普通に。私、前歯のほとんどが入れ歯なんです。殴られてうずくまると蹴られます。『巨人の星』を読んでいましたが、まさに、ちゃぶ台がひっくり返る家でした。広い家ではなかったので、テレビの画面が割れるんですよ。
今考えれば、父はアルコール依存症だったんですよね。暴力を母は必死に止めていたという印象があります。それが当たり前でした。教育面でもしつけが厳しい。覚えているのは5歳のとき、それまでフランスでの生活だったんですが、お箸が持てないと、朝まで指導されるということもありました」
また、父は幼いころから将来について訓示をしてきた。
「『頭の中に不動産を持て。それがおまえたちの身を助ける』と言われていました。簡単に言うと、勉強が大事だということでした。父はユダヤ人を尊敬していて、自分がフランス圏ではマイノリティーで、そのなかを転々としていったのです。だから『おまえたちもいつそうなるかわからないから、きちんと勉強をしておけ』と言っていました」
そんな父からの言葉を苦に思わずに聞いていた。
「私は『へえ』と思っていました。人間関係は苦手ですが、勉強は得意でしたから。だって、私にとって勉強はすごく楽なんです。ドリルは何も言わないですから。『おかしくない?』とか『もっと好きでいてよ』とか言わないじゃないですか(笑)。それに勉強は練習法が決まっている。どうすればいいのかは明確です。しかも、努力が報われます。でも、人間関係は何を求められているのかわからない」
母親とはずっと一緒だった。厳しい父と反対に優しく、4歳上の姉と2歳下の弟と、3人の子どもを育てるパワフルママだったという。
「母は子どもが大好きでしたが、ワンオペで子育てをしていたので、ものすごく忙しかったんです。よく料理を作っていました。覚えているのは餃子です。3人きょうだいで、1人30個くらい食べていました。
家にあるものでパッと作るような、時短料理が得意でした。(子どもの身体を)大きくするのが好きなんです。大きい人が好きみたいで」
家族の思い出というと、'90年代に放送されていた、フジテレビ系のクイズ番組『平成教育委員会』だ。
「テレビのチャンネルを選ぶ権利は父親にあったんです。ただ、番組が始まると、親から裏が白色のチラシが配られました。みんなで解いて、チラシの裏に解答を書いたんです。めちゃくちゃ楽しかったです。きょうだい3人で解いていました。
それを見ていた父はお酒を飲み、母はつまみを出していました。解ければ父親に褒められました。当時の父はお酒が入らないと一言も話しませんでした」
グレた中学時代。高校は退学し家出少女に─

中学に入ると、問題行動を繰り返すようになった。
「学校生活はうまくいきませんでしたね。わかりやすくグレて、途中から学校に行かなくなりました。練馬の公立学校だったんですが、両親ともに地方出身でしたので、方言を話さないように育てられました。
その結果、NHKのアナウンサーみたいな話し方になったんです。すると、『話し方が変だ』と言われ、いじめられるようになったんです。ハブられたり、放課後に呼び出されたりしました。そこで、引きこもりの方向ではなく、グレました」
中学のときは流行りものに飛びついた。フリッパーズ・ギターの曲を聴きながら、ギャル雑誌『egg』を読むというアンビバレントさ。ただ、人間関係も学校生活もうまくいかなかったという。中学ではどんな生活だったのか。
「タバコとか……。ただ、違法薬物はやらなかったし、お酒も飲みませんでした。アレルギーなので。クラブキッズでしたが、このころはまだ家出はしていなくて、深夜遅くになっても帰宅していました。学校には、中学の途中からほとんど行っていません」
高校に入ったものの、すぐに退学になった。
「『高校くらいは行かないと』と思い、受験しました。とにかく家を出たかった。全寮制の高校も考えましたが、規則が厳しい。だから、普通の私立に行きました。制服が規定のものであれば、金髪にしようが、ガングロにしようがなんでもよかったんです。でも、このころは荒れ狂っていましたので、退学になりました。停学、停学、停学、無期停学みたいな……」
'90年代後半、渋谷をメインに流行ったヤマンバギャルに石田さんもなっていた。日焼けサロンで肌を焼いて、真っ青のアイシャドウ、派手な髪形、厚底ブーツを履いた少女たちの1人だ。
「遊び場のメインは渋谷でした。当時、ヤンキーは池袋、ギャルは渋谷でしたから。『egg』やストニュー(『東京ストリートニュース!』)にも載ったけど、読者モデルにはなりませんでした。だって、定期的に連絡が取れないと読モにはなれないんですよ。私は当時、家出少女だったので(笑)」
また、女子高生ブーム、援助交際ブームの時期でもあった。
「エンコーしている友達はいました。好きなものを買えていたので、シンプルにお金が入るのは羨ましくも思っていました。『プリクラ20枚連続で撮れていいな』とか。でも、私はエンコーができませんでした。高校からこの顔、老け顔なんです。おじさんに人気がない。靴下くらいは売れるかな?と思っていたんですが、ブルセラで売れないんです」
当時、援助交際をしていた女の子の心情としては、どのくらい高く売れるのか、ということで自分の価値を測っていたということもあったが、石田さんはどうだったのか。
「彼氏以外と性的関係を持ったらフルボッコという感じでした。自分自身の“性的な商品価値”は感じていませんでした。老け顔でオジ受けも悪かったし自分に商品価値は感じていなかったですね」
性被害はあったものの、加害者は公表しない

実は、石田さんは小学生時代、性被害に遭っている。相手のことは語っていない。
「高校時代、私はすごく奔放で、(性的なことに関して)経験豊富に見られていました。『月美ちゃんは性病じゃないか』という噂が流れるくらいでした。『そうだよ』と言っていたこともありました(笑)。
でも、彼氏と初めて性体験をするまで、性被害を除けば、経験していなかったんです。周りからは『まさか、月美ちゃんが処女とは』と思われていたのかも。彼氏にも被害を言いませんでした。黙っていたというよりも、自分に何が起きているのかわかっていなかったんだと思います。記憶を封印していたというか、考えたくなかったんです」
性被害について、詳細に話したことはある。医師の講演会で当事者として登壇したときだ。
「幼少期に繰り返しの性被害に遭っていた、ということまでは公表しています。医師の講演では、うつなどが性被害に起因しているわかりやすいケースとして取り上げられました。当時は、同じような経験をした人の役に立つのかもしれないと思っていました。
しかし、話しているうちに(自分は)見世物小屋のフリークスだと思うようになったんですよね。加害の相手を公表しない理由は復讐心がないから。その相手には、絶対真っ当に生きていてほしい。誰よりも真っ当に生きろよ、と。それに、私は『性被害に遭った人』として生きていきたくない」
そうした感覚が、《私は私に貼り付けられたすべてのラベルを破いてしまいたい》(『まだ、うまく眠れない』より)という言葉に表れている。そうしたつらい経験がある中、石田さんの心の支えは何だったのか。
「何もないですね。でも、支えがあるとすれば、姉がいてくれたこと。性被害に遭っていた当時、ものすごく本を読んだけど、何もハマりませんでした。やみくもに情報を入れて、(性被害の現実から)気をそらしていました。それは勉強をすることも当てはまる。考えるよりも、情報を取り入れていたんです」
考えることを避けるために情報を取り入れる。これは、のちにストレスをため込まないために食べ物を口にし続け過食症になるのと似ている。
家出はもがいている感じ。引きこもりは暗闇に定住
高校中退後は大阪へ移った。
「姉が大阪の大学に進学して『寮生活で自由がない』と聞いていたんです。そのため、姉に『一緒に暮らしてくれないか』と。それまで友達の家を転々とするか、路上生活だったので、とにかく屋根のあるところで寝たい。両親も『姉と一緒で住所がわかるならいい』ということだったんです」
大阪では、バイトばかりしていた。
「当時は、ショップ店員ブームで昼間はアパレルショップで働いていました。夜はお好み焼き屋さん風の居酒屋で働きました。人間関係は広がりませんでしたが、バイトもこなす中で、路上生活をしていたときよりは安心を得られた」
しかし安心できても、将来のことは不安だった。
「家出生活と大阪のバイト生活では、先が見えない。いつもお金の心配ばかりしているんです。宿ができたらお金のことでいっぱいいっぱいになる。この先、どうなっていくんだろう?と考えると、行きづまりました」
そうしているうちに摂食障害になった。
「もう無理と思っていたら、過食症になったんです。体質的に吐けないので、食べてばかり。昼も夜も接客業でしたし、特に夜の居酒屋の仕事では東京弁は嫌われました。なので、ストレスがたまり、自分に麻酔をかけるように食べていました。食事は合法だし、安いものを買えばいいと思っていました。すると、昼のショップの店長から『うちの店の服を着られなくなる』とたしなめられたりしました」
結局、実家に戻ることになり、それから引きこもり生活に突入する。
「完全に引きこもりのときは、最大で90キロにもなりました。廃人みたいだったんです。まずい状態なのがひと目でわかるぐらい。実家にいても、私は父と接したくない。父も接し方がわからない。お互い、いないかのようにしていました。母は『どこの病院に行けば治るんだろう』とオロオロして。この時代がいちばんつらかったですね」
家出時代と引きこもり時代のつらさは種類が違うという。
「家出少女時代は輩に絡まれたり、レイプされそうになったりしました。路上生活をすると足がむくむんですよ。24時間、さまよいながらずっと外にいるのは相当キツい。
でも、家出のときは、人に会えるじゃないですか。引きこもりのときは、始まりも終わりもないんです。記憶に残らないくらいのただの暗闇。どっぷり定住している感じです」
暗闇の中でどう生活していたのか。
「親の動きで時間の感覚がわかるんです。『仕事に行ったんだな』とか。あとは一日中、寝ているか、食べているか。食べるものも菓子パンがメイン。安くて甘くて不安が満たされる。お金があればコーラを買います。炭酸じゃないと胃に入っていかないんですよね。胃の中に詰め込めればなんでもいいんです。味わっていません。詰め込むだけです」
月に一回、精神科に通う前だけ、お風呂に入っていたという。
「鏡を見たくないので洗顔は基本的にしません。手の感覚で肌が荒れていることや、どれくらい顔に肉がついているかわかってしまう。夜中に人目を忍んでコンビニに行くんですが自動ドアの部分に鏡みたいに映るところがあります。それが嫌で嫌で。もう何も考えたくない。少しでも考えると、『死にたい』が襲ってくるんですよ」
25歳のとき、石田さんは自殺未遂をした。
「近所の公園で首をつったんですが、木の枝が折れたんです。『太っていると死ねないんだ』と思いました。マジかって(笑)。なんで死にたいのか、って? ずっと『死にたい』と思っているんですが、微妙にお金がなくなると、食べ物が買えない。そうすると麻酔が切れる。今の絶望的な心の痛みに向き合わないといけなくて、希死念慮に襲われます。実家に引きこもって、食べてばかり。そんなときに両親から今後のことを聞かれたりするともう絶望的に死にたくなって」
主治医のひと言で婚活を始める

90キロの体重と精神科通院。職歴も貯金もない27歳のある日、主治医から「結婚すれば?」と言われた。その言葉がきっかけで婚活を始めた。
「主治医のことはそれなりに信頼していました。心の底から“良く”なりたかったんです。そのころの私がイメージしていた“良くなる”というのはいわゆるレールに乗るというか、普通の営みをできるようになりたいってことなのかな。
母の毎日は、どこか行くところがあって、帰ってきて、寝るという繰り返しですが、そういうことができるようになりたかった。やらなければならないことがあって、行くべき場所があって。そういう普通のことがどうして私にはできないの?って羨ましかったんです。母のようになりたいわけじゃない。多くの人がやっていると思われる営みを私もしたかったんです」
婚活のイメージは、相談所に行き、見合いするとか、お見合いパーティーに参加する、というものだった。
「マッチングサイトやアプリは危ないと思っていました。ようやく婚活をするために外に出ようとして、久しぶりに鏡を見たんですが、『力士がいる』と思いました(笑)。眉もつながっていて。体重は婚活がキツすぎて、過活動で痩せていきました」
結局、婚活には8か月間、集中して取り組んだ。
「逆ナンもしたことがあるんですが、しゃべることがないんです。何をしているかという話になっても、『精神科に通って婚活しています』とは言えない。聞かれてもいいように、バイトをするようになりました。
稼ぐことが目的ではないので、収入にこだわらない。引きこもりや対人恐怖は、継続的な関係を築くのは苦手ですが、初対面には強い」
その結果、結婚相手が見つかった。今の夫である。
「婚活に励む私を見た仲間が紹介してくれたのが夫です。彼は高校生のときに交通事故に遭い、足にケガを負って身体障害者となりました。でもそのことで誰かに寄りかかろうともせず、自分のことは自分でなんとかする、というタイプ。彼は“なんだか一生懸命な人だな”というのが私への第一印象みたいです。夫の実家は駅から2時間近くかかる田舎で農業を営んでいます。みんなよく笑いよく食べケンカをしていて心底まぶしくて。彼の家族の一員になりたい!と強く思ったんです」
婚活の次は妊活。体外受精で長女、そして長男を授かった。
「妊娠がわかってすぐに区役所で『特定妊婦』に指定してください、と頼みました。特定妊婦とは支援が必要な妊婦のことです。虐待などの被害を生まないために保健師さんが要注意な妊婦を必死に探しているので“自分から名乗り出る人は初めて”と驚かれました(笑)」
結果、さまざまな支援やサービスとつながった。
「子育てに関してもやりすぎてしまうところがあるんです。ハロウィンの日に恐竜の着ぐるみを着て息子や子どもたちを脅かしたりしていたら通報されたり(笑)。
今も子どもたちは何より大事な存在です。だからしがみついてしまうのではないかと怖い。仕事という居場所ができて子どもから精神的に距離を置ける時間は私にとっても子どもにとっても良かったと思いますね」
書くことで世界とつながる。まだマシに生きていける
元引きこもりの主婦が本を出すことになったきっかけは、貧困を扱った講演会だった。質疑応答コーナーで石田さんが講師に質問をしたところ、会場にいた編集者の目に留まったという。
「質問コーナーなのに自分の経験をバーッと話す私を見て“何か書かせたら面白いかも”と考えてくれたみたいです。私はすぐ飛びつきました」
声をかけてきた編集者に、「書籍発売前に『note』に公開してもいいか」と許可を取り、それが前出の鈴木さんの目に留まった。鈴木さんは、
「精神疾患、発達特性、暴力のサバイバー……当事者が自身を語るって難しい。苦しさや孤独の訴えとか。他者への申し訳なさとか。そこから這い上がったストーリーを語る人が多いんですけど、どれも曖昧な像でしかない。しかし、石田さんは全部を内包した文章を書いていて、突出した人が出てきたなと思ったんです」
次回作の出版も決まっているといい、石田さんは目を輝かせる。
「まだまだ稼げていないし、夫には認められていません。でも、私は書き続けたいんですよね、自分のためにも、子どものためにも。今でもフラッシュバックが起きたり、うつに引っぱられたりと、乗り越えたわけではない。
それでも私の夢は150歳まで生きること(笑)。生きて作品をたくさん書きたい。なんで150歳かというと、私は物書きデビューが40歳近くと遅かったので、いろんなものを見て、たくさん書きたいんです」
引きこもっていた時間を取り戻すように石田さんは貪欲に走り続ける──。
<取材・文/渋井哲也>