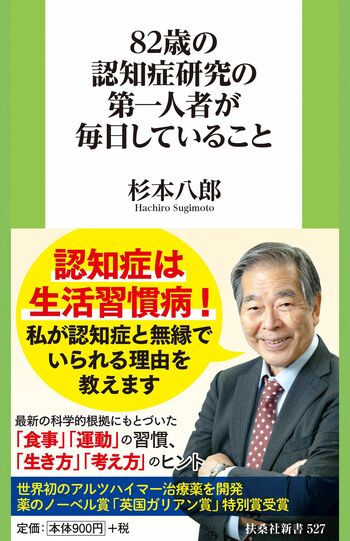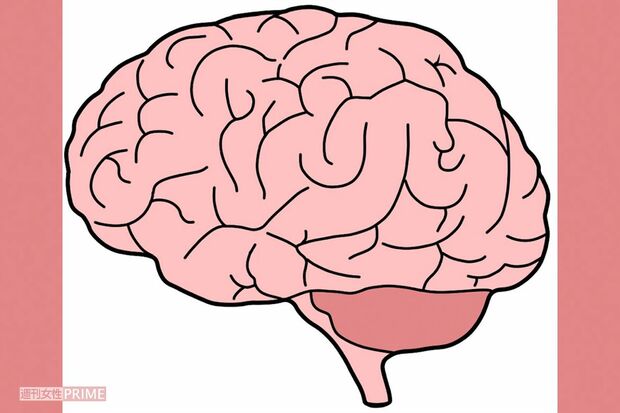
現在、65歳以上の4分の1が認知症とその予備群とされる。誰もが発症しうる身近な病に不安を抱える人も多いが、実は予防することも可能だ。アルツハイマー治療薬「アリセプト」の開発者であり、82歳の今もなお第一線で認知症研究を続ける杉本八郎先生が実践する、認知症を遠ざける方法とは。
認知症は生活習慣病と同じ
「認知症は生活習慣を改めれば予防できます。生活習慣病と同じで、過剰に恐れる必要はありません」
そう説くのは、長年認知症の研究に携わり、82歳の現在も新薬の開発を続けている脳科学者の杉本八郎先生。
杉本先生は、世界初のアルツハイマー治療薬「アリセプト」の開発で、薬のノーベル賞といわれる「英国ガリアン賞」特別賞を受賞した認知症研究の第一人者だ。
認知症とは、記憶力や判断力など脳の機能が低下し、日常生活に支障をきたす状態のこと。約9割はアルツハイマー病、脳血管障害、レビー小体病の3つが原因とされる。これらの疾患がなぜ、生活習慣病と同じなのか。
「アルツハイマー型認知症は、アミロイドβというタンパク質が脳内にたまることで神経細胞が傷ついて、脳細胞の活性が落ちたり数が減ったりすることで発症します。血管性認知症は、脳梗塞や脳出血、くも膜下出血により脳の血管が詰まったり破れたりして、脳細胞に酸素が送られなくなって神経細胞が死んでしまうことで起こります。
そして、レビー小体型認知症は、α―シヌクレインというタンパク質が蓄積してできたレビー小体が、脳の神経細胞を壊すことで脳細胞が減少します」(杉本先生、以下同)
つまり認知症はすべて、脳の神経細胞の活性が落ちたり、数が減ってしまったりして、神経細胞同士の情報伝達がうまくいかなくなることで引き起こされるわけだ。
ということは、認知症を予防するには、その原因となるタンパク質を脳内にためないことと、脳血管を丈夫に保つことといえる。
「この脳内のタンパク質は誰にでもあるもので、脳細胞が元気であれば、分解されて排出されます。ただし、増えすぎたり、上手に排出されなくなるとタンパク質が凝集して脳内にゴミのようにたまっていきます。
完全に原因は解明されていませんが、運動不足や偏った食事などの生活習慣が、脳内にタンパク質が蓄積する原因の一環になっていることは間違いありません。脳血管障害も、血管ボロボロ、血液ドロドロが引き起こすものなので、まさに生活習慣の悪化が認知症の引き金になっているのです」
杉本先生が「認知症は生活習慣病である」と強調する理由は、ここにあるわけだ。もちろん、生活習慣だけが認知症の原因であるとまではいえないが、少なくともその改善が認知症予防の第一歩であることは確かなようだ。
最も大事なのは『主体的に生きる』こと
では、杉本先生がすすめる認知症予防に効果的な習慣とはどのようなものか。
「まず、おすすめしたいのは運動です。特に酸素を使う有酸素運動は血行を良くする効果が非常に高い。脳に十分な血液が流れれば、栄養や酸素がたっぷり送り込まれるので脳の細胞も活性化します。気軽にできるのはウォーキング。一日の歩行時間が長いほど認知症のリスクが下がるというデータもあります」

運動のほか、脳を活性化するには生きる姿勢や考え方も重要だと杉本先生は言う。
「最も大事なのは『主体的に生きる』ことです。すなわち、誰かの言うことに従って動くのではなく、自分で決めて自分で動くことです。人の後ろについていくだけの生き方は認知症になりやすい。
高齢者が病気などで入院すると認知症になりやすいのは、病院という、ルールの決まった状況に置かれ、自分で何かを決めたり、家事をすることがなくなるため。今日は何をするか、次に何をすべきかを考えることができていたら、認知症になりにくいのです。介護施設に入所しても同様で、主体的に生きている人は友達もできます」
人との交流が多い人は、認知症になりにくいというデータは世界中で報告されている。では、主体的に生きるにはどうすればよいか。
「趣味を持つことです。例えば絵を描くとする。始めるために絵の具を買いに行きますね。名画を見に展覧会に出かけることもあるでしょう。主体的な生き方が求められるのです。音楽鑑賞であれば、コンサートに行ったり、同好の仲間ができて話をするようになったりしますね。趣味は“主体性”を必要とするのです」
運動、趣味、これらの習慣も継続しなければ意味がない。続ける秘訣は何だろう。
「覚悟を決めて真剣に取り組むことです。いいかげんな気持ちだと、忘れてしまったり、今日はいいかなと休んでしまったり。そして何より楽しくなければ続きませんね。
楽しく続けるポイントは“感謝”です。周りへの感謝を忘れずに、その気持ちを言葉で伝えること。感謝を述べられた相手は笑顔になり、そこから良い人間関係、環境が築けるでしょう。そうすれば、人との交流も生まれ、自然に継続できるのではないでしょうか」
認知症を寄せつけないためには、やはりバランスの良い食事も肝要になる。最近では、認知症を予防する効果が期待できる成分もわかってきているようだ。それらを含む食べ物を日々の食事に取り入れていくことも大事。
「体内に発生する活性酸素は、細菌やウイルスから身体を守ってくれる大事な物質ですが、過剰になると細胞にダメージを与え、老化や動脈硬化などの生活習慣病の原因となります。その活性酸素を無毒化してくれるのが抗酸化作用を持つ物質です」
抗酸化作用を持つ食品を積極的にとることで、老化が抑制され、健康な血管が維持できるというわけだ。それはすなわち、認知症の予防にもつながる。
杉本先生が実践するルーティンとは
「抗酸化作用を持つ物質として注目したいのはポリフェノール。植物に存在する苦味や色素の成分で、自然界に5000種類以上あります。種類によって独自の作用があり、カレーのウコンに含まれるクルクミンや緑茶のカテキン、シークヮーサーのノビレチンなどのように、脳内のタンパク質の凝集を抑制する作用を持つものもあります。
このほか、高い抗酸化力で知られる赤ワインや緑黄色野菜、血液サラサラ作用を持つ玉ねぎや青魚なども、認知症の予防効果が期待できます」
認知症は65歳を超えるころから発症しやすくなるが、実はアミロイドβは発症の20年も前からたまり始めているという。つまり、認知症予防に取り組むなら1日も早いほうがよい。いつまでも元気な脳を保つためにも、早速今日から実践しよう。
杉本先生が実践している毎日のこと
1・1時間のウォーキングと剣道の素振り
起床後ウォーキングを1時間、そのあとに腕立て伏せを50回、腹筋を50回、竹刀の素振りを200回行っている。「60年前から続けている剣道のトレーニングも兼ねて、実践しています」
2・現役で認知症を研究
論文や資料を読むなど、新しい学習を毎日のルーティンに。今も認知症の新薬の研究を続けている。「学生や若手の研究者たちとの交流や会話も積極的に行っています」
3・趣味は俳句
ウォーキングをしながら毎日俳句を10句作ることをノルマにしている。俳誌に投句するほか、俳句の会を主催し、選句を行う。「俳句を通じて友達がたくさんできました」
4・1日1食と晩酌
食事は毎日昼食だけにして、過食しないように。また、多品目の食品をバランス良く取ることを心がけている。「好きなお酒は我慢せず適量を、豆腐や魚などを肴に飲みます」
5・家族(妻)に感謝
家族、特に妻への感謝を忘れず、その都度「ありがとう」の言葉を伝えている。「感謝の気持ちを持てば謙虚になって相手への尊敬につながり、人間関係が円滑になります」
「脳」に良い5つの食品
・カレー ・緑茶 ・赤ワイン ・シークヮーサー ・青魚
活性酸素の害から脳の神経細胞を守る、抗酸化作用を持つポリフェノールや、血流を良くし、認知機能を高めるDHA・EPAを豊富に含む食品たち。積極的に食事に取り入れたい。
『82歳の認知症研究の第一人者が毎日していること』
扶桑社新書990円(税込み)
取材・文/桑原順子
すぎもと・はちろう 1942年生まれ。薬学者、脳科学者。エーザイ入社後、新薬開発の研究室で高血圧治療薬「デタントール」、そして世界初のアルツハイマー治療薬「アリセプト」の創薬に成功。京都大学薬学研究科教授などを経て、2025年名古屋葵大学学長に就任。