
「俳優の仕事をしているのに、どうして小学校の学習指導補助員になったのか? みなさんに不思議がられるのですが、実は私にも意外な展開だったのです」
そう話す大浦龍宇一さん。始まりは、大浦さんが大人も子どもも読める童話を出版したいと思ったことだった。
ひょんなことから始まった「二足のわらじ」生活
もともとイラストが得意で、シンガー・ソングライターとして作詞をしていたこともあり、「ある日、子どもたちがグラウンドで遊んでいる姿を目にしたとき、子どもたちを笑顔にする、しかも大人も読める童話を作ろう、と思い立ったのです」(大浦さん、以下同)
ところが、アイデアはあるものの、うまくまとまらない。そこで頼ったのが、教育関連のNPOを運営している40年来の友人。童話作りのアドバイスをもらおうと思ったのだが、返ってきた言葉は「実際に小学校で働いてみたら?」というものだった。
「予想もしなかった言葉でした。そんなことが可能なのかと思っていたら、そこから話がとんとん拍子に進み、副校長先生との面接になり、晴れて採用。学習指導補助員として働くことになったのです」
2023年から始まった学習指導補助員の仕事は、当初は週3回。いまは同校に加え、ほかの小学校で学童の子育てサポーターもしている。
「学習指導補助員の仕事が終わったあと、子育てサポーターとして晩まで働く日が週に2回。学童だけで働く日が2回なので、週に4日、小学校で過ごしていることになります。俳優の仕事もありますから、大変は大変です。時には小学校を休ませてもらうこともあり、温かく応援してくださる先生方には本当に感謝しています」
学習指導補助員として働くときは、朝5時に起き、6時には出かける。
「俳優の仕事場にはいつも車で行くのですが、小学校は電車通勤。満員電車を避けて、7時には学校近くにいます。登校が始まるまでの1時間で気持ちを整え、心の余裕を持って子どもたちに接するようにしています」
「よく聞く」「待つ」「否定しない」
学習指導補助員の仕事は、授業に取り組むのに少し時間がかかる児童のサポート。1対1の対応になるが、ほかの児童との関わりも大切で、結局はクラス全体を見守ることになる。
「授業以外の休み時間や給食の時間は短くて、子どもたちと接する時間は限定的。学童は、クラスの中ではわからなかった子どもたちの姿が見えてきます。子どもたちにより深く関わることができるので、昨年からこの仕事も始めて、やりがいもいっそう大きくなりました」
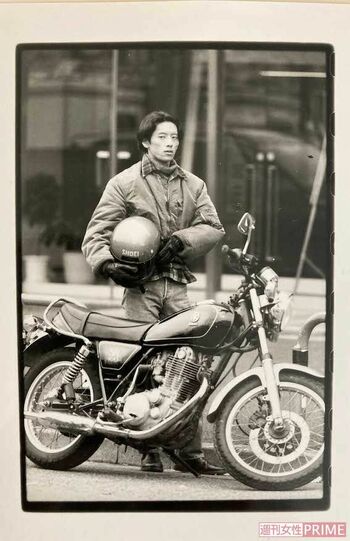
「俳優業と小学校での仕事は、まったく異なるように見えますが、実際は共通しているものがたくさんあります。俳優として生きる中で、少しずつ気づいていたことが、子どもたちとの時間を通してはっきりと自覚できるようになったのです」
大浦さんが大切にしていることは、「よく聞く」「待つ」「否定しない」の3つ。相手が大人でも子どもでも関係なく、必要なものだという。
「“よく聞く”は、単に耳を傾けるだけでなく、相手の言葉になっていない気持ちを感じとるという意味があります。大人をイラッとさせる言葉を発する子どももいますが、なぜ、そういう言い方をするのか、考えてみる。すると、その子の感情や環境が見えてくることがあります。俳優として、台本に書かれていない背景を深掘りし、監督の意図を推し量ることとつながっている気がします。
“待つ”の重要性は、子どもにも大人にも共通しています。相手の話を遮って意見を言ったりせず、最後まで話を聞く。黙って待つ、という姿勢がすごく大切なのだと思います。
“否定しない”も同様で、子どもがよくない行為をしたときは、何がよくないことなのかしっかり伝えますが、本人の人格を否定するような言い方はしません。俳優業でも同じ。自分と意見が違っても、“よく聞く”ようにしています」
「問題児だった」学生時代
言われてみると、そのとおりだと思うことばかりだが、実践するとなるとなかなかむずかしい。
「つい相手の言葉を遮ってしまったり、話をじっくり聞くことができなかったり。そのたびにハッと気づいて反省しています(笑)」
大浦さんは父親をはじめ、父方の祖父、祖母、おば、大伯母、母方の祖母が俳優という芸能一家で育った。恵まれた環境に見えるが、順風満帆ではなかったようだ。
「学生時代の自分は、かなりいいかげんで、高校2年のときに自主退学。その後、このままではダメだと奮起して再試験を受け、復学しました。いわゆる問題児だったわけです。だから、目の前の環境や問題に適応できずに苦しんでいる子どもたちの気持ちが、多少なりとも理解できます」

自分の戻る場所があるなしの分岐点は、子ども時代の経験にあると大浦さんは言う。
「私はどちらかというと家族より、つらいときにそばにいてくれた周りの人から、たくさんの愛情を受けてきたのかもしれません。その中で自分の居場所を見つけることができたし、道からはずれるたびに、戻ることができました。それは“愛されている”という実感があったからです。
子どもに愛情を注ぐことができるのは親です。その愛情を安心して受け止め、心の土台にできるのが小学生までです。その先は反抗期もあり、素直に受け入れることが次第にむずかしくなってきます。私は児童たちの親にはなれませんが、近くにいる大人として児童たちに愛情を持って接することはできます。いずれ私のことなど忘れてしまうかもしれませんが、心のどこかに愛情を注いでくれた大人がいたと、記憶してくれればいいなと思っています」
教育とは「引き出し合うもの」
大人になると感情を押し殺し、めったに涙を流すこともなくなる。それに対して子どもたちは感情が豊かで、気持ちを素直に表現する。さまざまな場面で、子ども同士が衝突し、子どもが泣いているという光景もよくあるそうだ。
「以前の私なら、すぐにどちらが悪いかという対応をしましたが、先の3つのことを大切に子どもに接していく中で、何があったのか、お互いの気持ちや状況がよく見えるようになってきました。子どもは自分を理解してほしいと願うと同時に、大人が思っている以上に、相手を受け入れることができる、やわらかい心があります。すぐに仲直りできる子どもたちを見ると、大人は素直じゃないなあと痛感します。素直じゃないから人間関係もこじれたりします。
子どもは発想が豊かで、大人の思いつかないことを考えたりもします。子どもたちといると、忘れていたことに気づくことが多いですね。今日は仕事に行くのがつらいなと思う日でも、子どもたちの笑顔を見ると元気になります」

大浦さんに、あらためて教育とは何なのかを聞くと、「大切な“いのち”を引き出すこと」と話してくれた。
英語で「教育」はエデュケーション。ラテン語の「養い育てる(educare)」と「引き出す(educere)」の2つの同音語句が語源になっている。大浦さんは、いまのエデュケーションの意味になっている“養い育てる”より、“引き出す”という意味のほうがピンとくると話す。
「大人が子どもの個性や才能を引き出す一方で、大人も子どもから大切なものを引き出してもらっているような気がするのです。教育とは、一方的なものではなく、大人と子どもの両方で引き出し合うもの。それができたら、いい関係が築けるのではないでしょうか」
これは学校の世界だけでなく、俳優の世界でも通用することだという。
「俳優同士、お互いの才能を引き出し合えれば、自分自身も成長するし、作品も素晴らしいものになります」
大浦さんの俳優業と学校教育にかける情熱は燃え尽きることなく、二足のわらじ生活は今後も続けたいと考えているとのこと。どちらの仕事もさらなる飛躍を遂げそうだ。
取材・文/佐久間真弓
