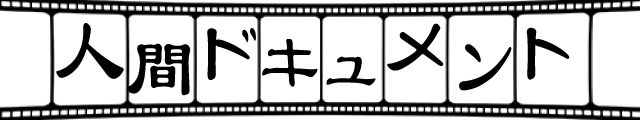女性として世界で初めてエベレスト登頂に成功したのは35歳のとき。すでに1児の母だった。その後も世界7大陸の最高峰に登頂するなど、登山家として輝かしいキャリアを持ちつつ、飾らない人柄で愛された田部井淳子さん。
その心は愛する家族、山でつながった仲間たち、生まれ育った故郷・東北と常に共にあった。
惜しくも2016年に他界したが、その生涯をモデルとした映画『てっぺんの向こうにあなたがいる』(配給:キノフィルムズ、監督:阪本順治)が10月31日(金)に公開される。
田部井淳子さんのモデル映画『てっぺんの向こうにあなたがいる』

主人公の「多部純子」役に吉永小百合。俳優・のんがエベレストに登頂した純子の若き日々を演じている。
映画の公開を記念して、週刊女性2014年2月18日号の人間ドキュメント・田部井淳子さん《「余命3か月」から生還─がんになったのも生きている証拠です》を再掲載し、追加の取材を加えてお届けします。
かつて世界最高峰のエベレストを制した田部井淳子さん(74・'14年当時、以下同)だが、自宅2階へ続く階段がとてつもなく長く感じた。

階段1段分の高さまで足が上がらない。しびれて感覚のない足を両手で持ち上げて階段に乗せる。片足に体重をかけるとフラつく。階段の真ん中まで来ると息が切れた。両手をつき、四つん這いになってなんとか上りきった─。
それまで毎月、国内外の山に登り、講演やテレビ出演、取材で多忙だった田部井さん。お腹をチクチク針でつつかれるような痛みを覚えたのは2012年の春だ。
すでに深刻な状態で、最初に診察を受けた病院では、医師から余命3か月と宣告された─。
東京のがん研有明病院に入院。お腹の中に黒い帯状のものが走り、黒い点々が散らばっている画像を見せられた。
「がん性腹膜炎です。ステージ3C。5年生存率は30パーセントです」
そう担当医に告げられると、
「チクチクしてまだ3週間なのに、もう?」と戸惑った。
「もしかして、明日の朝になったら、“あれは嘘です”と言ってもらえたらいいな」
その夜、田部井さんは一度だけそう願った……。
抗がん剤が劇的に効いたが、副作用で手足がひどくしびれる。すぐに座り込みたくなるほど、身体はだるい。
それでも、退院した日から毎日、少しずつ歩いた。近所の公園への往復から始め、退院9日後には飯能市の日和田山に登った。
通院して抗がん剤の点滴を受ける合間を縫ってだ。
「そりゃあ大変、大変。大変だけど、どうしても山に行きたかった。実際に登ってみたら、やっと一歩行けた、また一歩行けた、どこまで行けたと、一歩一歩進んでいっているという感覚が今までよりうんと強い。ベッドに寝ていたら身体は楽かもしれないけど、風景は変わらないし、風の音も聞こえない。緑の匂いもわからないじゃない。やっぱり外はいい。青空の下はいい!と思いましたね」
明るく快活な口調。会ってすぐ親しみを感じたのは、時折、故郷の福島のイントネーションがまじるせいか。
今もしびれが残る田部井さんをサポートするため、夫の政伸さん(72)がいつも横で見守っている。
政伸さんが普段の様子を教えてくれた。
「手もしびれて包丁を持つと危ないから、僕が台所に立つと横に座って、“これを切って、あれをやって”と。口は達者だから。しゃべれる病気でよかったですよ(笑)」
横で聞いていた田部井さんも笑いながら応える。
「本当にね。口先女でさ。でもねえ、夫が足をマッサージしてくれると言って始めても、いっつも3分で寝ちゃうのよ。まいっちゃうね」
献身的にサポートする政伸さんに不満をもらすのが、逆にほほ笑ましい。強く見える田部井さんも、内心ではもどかしさを押し殺しているのだと感じる。
初めて弱気になった妻

山も今までと同じペースでは登れない。ほかのメンバーに先に行ってもらい、夫と2人でゆっくりと登ることも。
昨年末から今年正月にかけて中米・ニカラグアの最高峰に登った。そこで「初めて弱気になった妻を見た」と政伸さんが打ち明けてくれた。
「ザラザラの火山で20センチ登ってもザーッと10センチ下がるから、ものすごく疲れる。“もうダメ。あなただけ頂上に行ってきたら”と言うから、“あと30分も歩けば着くから”と、だまして引っ張っていったんですよ(笑)」
連れ添って50年近く、夫にも弱音を吐かなかったというのもすごいが、2人の会話を聞いていると、悲愴感がまるでないのにも驚いた。
「まあ、起きちゃったものは、しょうがない。これが30代、40代だったら、頭が真っ白になったかもしれないけど。もう70歳過ぎで、子どもたちは大きくなったし、自分のやりたいことはずいぶんやらせてもらったし」
雪崩で死にかけたら「愛するわが子」が
がんになったのは初めてではない。2007年に早期の乳がんが見つかり、乳房温存手術を受けて完治した。'12年のがん性腹膜炎は、いわば2度目の闘いだった。
田部井さんは家族やスタッフに「騒ぐな」「オタオタするな」と言い、病気のことは伏せたまま仕事をこなした。気遣われると、余計ストレスになると思ったからだ。
夫の政伸さんは車の後部座席を倒してマットや布団を敷いて簡易ベッドにした。埼玉県の自宅から東京のがん研までの通院や山へ行くときはもちろん、講演や取材の現場まで妻が寝たまま移動できるようにした。
8か月に及んだ抗がん剤の点滴と手術を経て、がんは消え、治療は終了した。
2013年9月に、これまでの経緯をつづった本『それでもわたしは山に登る』を出版すると、みんなから驚かれた。人前に出るとシャキッとするため、ほとんど誰も気づかなかったのだ。
「病気を公表したら、みなさんに“大変だね。すごいね”と言われましたけど、私自身は“がんになったのも生きている証拠”だと。フフフフフ。そう思えたのも、山のおかげですね」
何度も死の淵から生還してきた田部井さんだから、口にできる言葉なのだろう。
1975年、35歳のとき女性で世界初のエベレスト登頂者になり、一躍有名になったが、このときも、危うく死にかけた。
第2キャンプで就寝中、真夜中にテントごと雪崩に吹き飛ばされたのだ。
「あのときは“ああ、私はこうやって死ぬのか”と思いましたね。娘がまだ3つでしたから、ママゴトしている姿が浮かんできて、ここで死んだら娘はどうなるんだ、最後の最後の千分の1秒まで頑張らなきゃと思ったんですけど。
雪に埋まったまま、だんだん意識が薄れてきて、気がついたときには、雪の上に出されていました。離れたテントに寝ていたシェルパ(高所登山を手伝う現地部族)が雪の中から掘り出して、助けてくれたんです」
「女子登攀クラブ」を結成
女性だけでヒマラヤに行こうと「女子登攀クラブ」を結成。1970年にアンナプルナ3峰の登頂に成功した後、'75年に15人の女性隊員でエベレスト登頂に挑んでいた。
全員ケガもなく予定どおり登山を続行したが、登頂できたのは田部井さんだけだ。
身長152センチと小柄で体力的にずば抜けていたわけでもない。自分が登頂できた理由を「運が良かったのと高所に強い体質だったから」と本人は説明する。
だが、次に日本人女性がエベレストに登頂したのは21年後だ。しかも、登頂した難波康子さんは、下山中に猛吹雪に遭い遭難死している。
田部井さん自身、その後、ほかの山でも2度、雪崩で死にかけた。何人もの仲間を山で亡くしてもいる。
そうした死を身近で感じた経験が、若かった田部井さんを徐々に鍛えていった。
「グチがすごく減ったと思います。あー、疲れた、もうやりたくないと思っても、子どもが言うことを聞かなくてイライラしても、生きているからそう感じられるんだから、文句を言っちゃいけない。そう考えるように変わってきましたね。もし、山でああいう経験をしていなかったら、私も文句ばかり言っているイヤなババアになっていたんだろうな、と。アハハハハ」
運動嫌いだった少女が「山」と出会って

それにしても、それほど大変な思いをしてまで、どうして山に登るのか。原点は小学4年のとき。担任教師に連れられて初めて登った那須の茶臼岳にあるという。
「茶色と白の岩がゴツゴツしていて硫黄の臭いがして、“何これ?”って、すごいビックリして。ああ、自分の知らないところって、まだいっぱいあるんじゃないかと思ったことが、原点ですね。
それまで、扁桃腺が腫れて高熱を出すことが多く、運動は嫌いだったんです。でも、山って、競争して登るわけじゃないから、体育が全然ダメな私でも、優秀な生徒と一緒に頂上に立てたという達成感がありました。はるか下に歩いてきた道が見えて、自分の足で登ってきたから、この風景が見られるんだという満足感もありましたね」
福島県三春町の生まれ。梅、桃、桜が一度に咲くから「三つの春の町」と名付けられた山間の町だ。緑の山しか知らなかった田部井さんにとって、初めて見た那須の火山は強烈だった。
旧姓は石橋。両親は印刷業を営み、田部井さんは兄2人、姉4人の7人きょうだいの末っ子だ。
地元の中学から県立田村高校に進学。兄に連れられ、県内の安達太良山、磐梯山などに登っていた田部井さんは、高校で山岳部に入ろうとしたが、「男子に限る」と門前払い。合唱部に入った。
当時は珍しかったオルガンが家にあり、姉妹の誰かが歌い始めると、たちまち二重唱、三重唱になり、歌うのも好きだった。

東京の大学に進んだ姉たちを追い、田部井さんも昭和女子大英米文学科に入学。女子寮で暮らし始めたが……。
「言葉が違うから、何度も聞き返されて傷ついたし。同じ部屋の人が湯のみを洗わないで何度も使ってるのが気になったり。あのころはすごく神経質で、それがどんどんどんどん高じて、ごはんも食べられなくなり、どんどんやせて、親が呼ばれました」
もともとは細やかな気性なのだろう。3か月休学して故郷で休養。大学に戻るとクラスメートがハイキングに誘ってくれた。
「奥多摩の御岳山に行ったら、同じ東京でも田舎じゃないですか(笑)。リヤカー引いてるおばちゃんはいるし。何だ、三春と変わらないなと」
コンプレックスが吹き飛び、忘れかけていた山への情熱が再燃した。帰りに渋谷の書店に寄り『東京周辺の山々』というガイド本を購入。自分で計画を立てて友人たちを誘っては山を歩いた。
大学を卒業して日本物理学会に就職。論文の編集をしながら週末は山に行った。山岳雑誌で見た雪山に憧れ、社会人山岳会に入会。本格的に冬山や岩登りを始めると、すぐのめり込み、それが後のヒマラヤ登山につながる。
夫のサポートで世界7大陸の最高峰に!

夫の田部井政伸さんと出会ったのも山だ。
バイクが好きでホンダに勤めていた政伸さんは、難しい岩壁を何本も登り、岩登りの世界では有名だった。同じ山で何度か出会い、話をするうちに親しくなった。
27歳で結婚、32歳で長女を出産した。
政伸さんは妻のどんなところに惹かれたのか。
「自分にないものを彼女は持っていたんです。周囲の人を大事にするとか。細やかな気遣いをするとか。僕は10代のころ、脊椎カリエスで歩けなくなり、入退院を繰り返していました。結核病棟だから人が死ぬのをすぐ隣で見てきたんですよ。人生は限られた時間しかないんだと感じ、自分も好きなことをやってきたし、彼女にもやってほしかったから、協力もしたんです」
それまで山岳会の男性や夫と山に登ってきた田部井さんが、女性だけでヒマラヤを目指したのには理由がある。
「男性とは体格も、スピードも、瞬発力も違う。肉体的構造が違う者同士がひとつのことをやるのは“フェアでない”と。それに岩場の狭いテラスで、生理的に男のすぐそばでトイレはできない(笑)。何か月もかかるヒマラヤ登山だと、よけいストレスになるでしょう」
40年前といえば、女性は家を守るのが当たり前という時代だ。エベレストに向かうときにも「女だけで登れるわけがない」「子どもを置いていく非情な母親だ」と中傷や批判もされた。
仲間同士でも、独身の隊員から「子持ちの副隊長(田部井さん)はフットワークが悪い」と嫌みを言われて、落ち込んだ。
「遠征中も“なんであなたが選ばれて、私が……”とか、人との軋轢が一番ストレスでしたね。でも、一歩一歩が大変な山を登るわけですから、登山に集中していると、イヤなことを忘れられました」
38歳で長男を出産。子どもたちが成人するまでは、夫婦2人で同じ山には行かず、必ずどちらかが家に残った。
'92年、53歳のとき7大陸最高峰の登頂を果たした。これも女性世界初の快挙だ。
海外の山に遠征すると、かなりの費用がかかる。エベレストのときは新聞社とテレビ局が後援してくれたが、それ以外は自己負担だ。
長女の出産を機に10年勤めた日本物理学会を辞めてからは、生活を切り詰め、自宅でタイプ打ちや校正の仕事をした。それでも足りないと、会社員の夫が金融機関から借りてくれた。田部井さんは帰国後に講演や原稿書きをしてコツコツ返済していった。
「いいご主人ですねぇ」
そう感想をもらすと、田部井さんはにっこり笑って、うなずいた。
「私もそう思います。やっぱり、私は見る目があったなと。アハハハハ」
だが、“有名な母”は、子どもには重荷だった。
「お母さんが山登りなんかするからだ!」
事あるごとに「田部井淳子の子ども」と言われ、興味本位の視線にさらされる子どもたちは成長するにつれ反発し始めた。特に息子の進也さんの反抗は長く続いた。学校でタバコを吸ったり、サボったり。挙げ句に、勝手に高校を中退してしまった。
「親としてずいぶん悩みましたけど、ああいう最中に親が何を言ってもダメだから、進路のことは息子が尊敬していたスキーのコーチにおまかせしました。私はお祝いのパーティーとか、息子が行きたいと言えばどこにでも連れていきましたね。“ほら見て、田部井さんの息子、茶髪にピアスだよ”とか噂されたけど、ポケットに入れて、隠しておくというわけにはいかないでしょう(笑)」
回り道をして大学院を出た進也さんは、福島県にあるロッジを両親から引き継いで切り盛りしている。今では田部井さんの登山に付きそってくれることもあるそうだ。
「間違っても死なないから!」と舞台へ

子育てが一段落すると、運転免許を取ったり、大学院で環境問題を勉強したり、山以外のことにも、次々とチャレンジするようになった。
64歳のときにはシャンソンを習い始めた。もともと医師、教師、弁護士など異業種の働く女性たちと同好会を作り、山歩きを楽しんでいた。その会の仲間に「シャンソンを習いたい」と話すと、「いいわね」と、たちまち5人が集まった。
「目標を持たなきゃダメよ」というメンバーの発案で、習い始めて1年半後にはコンサートを開いた。題して『怖いもの知らずの女たち―一度は歌ってみたかった』。
小さなホールとはいえ、初舞台でガチガチに緊張している仲間に、田部井さんは明るい口調でアドバイスした。
「山では間違うと死ぬけど、舞台では間違っても死なないわよ(笑)」
以来、「怖いもの知らずの女たち」は、毎年舞台に立っている。'12年7月には浜離宮朝日ホールで500人の観衆を前に歌った。
メンバーの1人でPR会社取締役会長の秋岡久恵さん(65)に聞くと、「一番の怖いもの知らずは田部井さん」だという。
「浜離宮ホールで歌ったときも、私たちのような素人が歌って“恥知らずの女たちになるんじゃないの”と、みんな腰が引けていたんです。でも、田部井さんは“こんな立派なホールで歌えるなんてすごいじゃない”と。抗がん剤治療で身体は非常に厳しい状況だったと思いますが、誰よりも楽しんでいましたね。
その裏にあるのは、やっぱり好奇心だと思います。仲間で集まって話すときも、違う業界の話をすごく興味を持って聞いていますし。みんなに喜んでもらうことが彼女の喜びというか。サービス精神旺盛な方なので、一緒にいると元気になれますね」
いつもは登山ズボンにリュック、帽子に眼鏡の田部井さんも、舞台に上がるときは肌もあらわなロングドレスと金髪のウィッグで登場。秋岡さんによると「舞台度胸満点、一番よかった」という。
講演も多く、人前で話すのに慣れている田部井さんは、緊張しないのかと思いきや、
「いやあ、すっごいドキドキしますよ。人前で歌うのは、緊張の度合いが違います。“あー、次だわ”とか思うと、もう、ドキドキしてダメ。だけど、舞台に出ちゃうと平気。間違っても、“あ、ごめん”で済むから。フフフフフ」
「東北復興」のため、自分に何ができるか

東日本大震災後、故郷・福島の惨状に、居ても立ってもいられなくなった。
「あのとき、すごく寒かったでしょう。うちにいっぱいあった羽毛服、帽子、手袋などを何箱にも詰めて、お金も送って……」
その後も「自分に何ができるか」と考え続け、被災者をハイキングに誘うボランティア活動を始めた。
人づてに「体育館などに避難した人たちが、朝から晩まで何もすることがないのがつらいらしい」と聞いたからだ。
田部井さんが代表を務めるNPO法人日本ヒマラヤン・アドベンチャー・トラスト(HAT―J)の中に東北応援プロジェクトを立ち上げ、2011年6月から開始。多いときは50人近い被災者が参加して、'14年1月までに33回実施した。
田部井さんの出身地、三春町には原発事故後、葛尾村、富岡町から避難してきた人が2000人弱いる。元副町長で三春まちづくり公社社長の深谷茂さん(65)が被災者との窓口になり、ハイキングにも同行してくれている。
「田部井さんは同じ高校の先輩です。山の先輩でもあるので私も喜んで手伝わせてもらっていますよ。被災者の方々と山を歩いているときの田部井さんは、とにかく明るいですね。ダジャレを言ったりして(笑)。干し柿や梅干しをベースにした手作りのオヤツを持ってきて、みなさんに配ってくれたりもします。
参加した方たちは“田部井さんは大病を患ったのに、自分たちのために一生懸命やってくれて、非常に励まされる”と話されていますよ」
ただ、ハイキングの参加者はシニア世代が多い。
「若い人たちに元気になってもらいたい」
と考えた田部井さんは、被災した東北の高校生を日本一の富士山に招待するプロジェクトも始めた。
1回目の'12年7月には60人。'13年は74人が登頂した。
「行きも帰りもつらかった!泣くほどつらかった! でも、自分が強くなれた!」
「グループで助け合うことは気持ちいいとつくづく感じた」
「自分の悩みは富士山に比べれば小さなことだと感じた」
参加した高校生たちから寄せられた手紙だ。
実は病気が見つかった2012年の春は、この富士登山プロジェクトが始動して、募金のお願いの企業回りが一段落した時期だ。
浜離宮ホールで行ったコンサートは資金集めのイベントでもあった。
自分の病気で中止するわけにはいかない、何としても富士登山を成功させたいという強い思いが、病気を克服する力にもなったのだろう。
「18歳の子どもが10年たてば28歳になって、復興の大きな力になると思うので、今年もやります! 1000人登らせるまでは続けますよ」
田部井さんのベッドの枕元には、地図帳が置いてある。
「あー、ここは行ってないなー。ここもだ」
地図帳を眺めながら、あれこれ考えるのが至福の時間だ。今の目標は世界各国の最高峰に登ること。年末年始のニカラグアを含め、66か国の最高峰に登頂した。
「ニカラグアも、行く前に一生懸命グーグルで調べたけど、エー!? こんなところだったの、と。緑の中にポコッポコッと富士山みたいな火山が連なっていて、マグマも見られるの。やっぱり、行ってみないとわからないわね。大みそかでも豪華な料理はないし、寝るのは地べただけど、満天の星を見てぜいたくだなと思うんだから、安上がりだよねー。アハハハハ」
山の楽しさを話し出したら、もう、止まらない。
「生涯最後の登山は富士山でした」病室での会話と引き継いだ遺志

この記事が掲載された2014年に田部井さんは脳腫瘍を患い、その後、腹膜がんの再発がわかる。療養を続けながら、'16年7月には富士登山プロジェクトの総隊長として富士山に向かった。
思うように動けない田部井さんに代わり、東北の高校生たちを登頂に導いたのは息子の進也さんだ。当時の田部井さんの様子を進也さんは、こう振り返る。
「病院の先生からは、バスで行ける5合目までにしてと言われたんです。でも、母は先生には黙って、親父と一緒にゆっくりゆっくり3010メートル(7合目付近)まで上がっていったので、身体は相当大変だったと思いますよ。それが生涯で最後の登山になりました」
本人の希望で緩和ケアに移り、亡くなる2、3日前のこと。進也さんが1人で付き添っていると医師から「1日単位の命だと考えてください」と告げられた。
「明日はもう話ができないかもしれない」と思った進也さん。ベッドに横たわる母親にこう声をかけた。
「今までありがとう。好きだよ」
「お母さんも好きよ。山よりも好き」
返ってきた言葉を聞いて、進也さんは「面白いな」と感じたという。
「そこも山なんだねと(笑)。でも、あのとき『好きだよ』とちゃんと伝えられたから、今こうやって、おふくろの話ができるんだと思います。弱っていく母の姿を見ているのはちょっとキツかったけど、最後にいろんな話をできたのは、本当に幸せでした。
富士登山に来る高校生の中には震災遺児の子もいて、彼らはあの朝『行ってきます』と言って、そのまま親に会えなくなった。それに比べたら、はるかに僕は恵まれているじゃないですか」
2016年10月20日。田部井さんは腹膜がんで逝去。享年77だった。
だが、進也さんは悲しみに浸る間もなく、富士登山プロジェクト存続のために奔走することになる。
「おふくろが死にましたと言った瞬間に、ブスッと(支援を)切った会社さんもいましたから。大人って、すごくわかりやすいなと(笑)。しかも、母が生きていたころより、今は経費が2倍ぐらいになっているんですよ。バス代、宿代、ガイド代とか1回で1千万円くらいかかるから、ほんと、めちゃめちゃ大変ですよ」

進也さんは一般社団法人田部井淳子基金を設立し、新たな支援先を探したり、全国に広く寄付を呼びかけたり……。2025年夏までに登頂した高校生は854人に上る。
そこまでしてプロジェクトを実施する裏には、どんな思いがあるのか。
「そもそも僕自身が被災者だったんです。経営していたロッジが地震で損壊して、現地では大変な状況が続いて。そこに原発事故があって、外で遊んじゃダメとか、避難しなきゃいけないとか、大人の都合で制限させられる子どもたちの姿を見て、申し訳ないなという気持ちがずっとあったんです。だから彼らが成長するきっかけをつくることができたらなと。
富士山に登頂して自信がつけば、何か自分がチャレンジしたいと思ったときに、一歩踏み出すハードルが下がると思うので」

そして、「あとはね……」と進也さんが続けて口にしたのは意外な理由だった。
「おふくろが亡くなったときに“このプロジェクト自体、どうせやめるんでしょ”
ってある人に言われたんですよ。その人たちを見返したいという反骨心もあります。だったら続けてやろうと(笑)」
その反骨心はお母さん譲りかと聞くと、進也さんは笑ってうなずく。
「おふくろもね、エベレストに女だけで行くのをダメって言われたら、絶対行ってやるみたいになった。同じじゃないですか(笑)」
田部井さんも、息子の奮闘ぶりを喜んでいるに違いない。
<取材・文/萩原絹代>