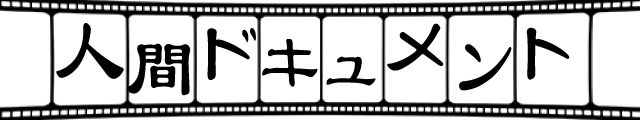「恋せよ! オトナ、オトナ世代応援ラジオ~!」
文化放送のスタジオに響くエコー付きのタイトルコール。だが次の瞬間、スタッフに笑いが広がる。力んだせいか声が裏返ってしまったのだ。「やっちゃったね」と照れ笑いする本人に、すぐさま録り直しが入り、今度は落ち着いたトーンで決めた。
この番組の主役は「深夜のラジオ王」と自称する高齢者専門の精神科医で作家の和田秀樹さん(65)。'22年に刊行した『80歳の壁』(幻冬舎新書)は年間ベストセラー第1位を獲得。話題作を次々と世に送り出し、著書は950冊を超える。
歯に衣着せぬトークを届ける和田秀樹

'24年4月に始まった当番組では、医療、政治、教育、ライフスタイルまで幅広く語り、50代以降のリスナーに向けて歯に衣着せぬトークを届けている。
この日のテーマは「女性リーダーは女性の味方か!?」
高市早苗氏の総裁就任時、女性たちからあまり歓迎されなかった背景を踏まえ、女性リーダーの理想像に鋭く迫る。
「今の女性リーダーは男性ウケを狙い、男の代弁者になっている人が多い。強い女性の味方にはなっても、非正規雇用や低賃金、シングルマザーなどの弱者には目が向いていない」
本当に求められるのは「生活者の感性を持ち、人々のニーズに敏感で、優しい“おっかさん”みたいな人」。そして「強いもん勝ちじゃなく、弱者に寄り添える女性らしいリーダーだと思う」と熱を込める。
「女性が強くなったっていうけど、強くなったのは男らしい女」
際どい発言にはフォローを挟むが、主張は弱めないのが和田スタイルだ。
「男らしいとか女らしいとか言うだけで差別発言といわれるけど、心理学上、人の心に厳然と存在すると思う。昔の女性リーダー、マザー・テレサとか、いつの時代でもすてきだと思いますけどね。高市さんは超タカ派ってイメージがあるけど、強い男にヘコヘコしないで“私はこれをやりたい”と言えるならすごい。でも、どうかな?」
テンションが上がると放送ギリギリの表現まで飛び出し、ヒヤリとする場面も。
番組を共に進行するアナウンサー・水谷加奈さん(57)は「和田さんのすごさは、私が1つ質問すると10倍の情報量で返してくれるところです!」と語る。
番組には病気や老後の悩み、薬の相談も寄せられる。
「かかりつけのラジオのお医者さんみたいですね。イベントを開けば、和田さんファンのオトナ世代の女性が集まり、教祖様みたいですよ。言いにくいことをきちんと言ってくれる、そこに惹かれるんじゃないでしょうか」
人気脚本家が明かす2つの顔

後日、東京・本郷のクリニックを訪ねると、席につくやいなや問題提起が途切れることなく続き、10分でヒートアップ。医療制度への賛否を経て、コレステロールの話へ。
「僕は日本人にはコレステロールが必要だと思ってる派。高いと心筋梗塞のリスクはあるけど、免疫細胞や男性ホルモン(男女問わず元気になる)の材料にもなる。低すぎるとがんやうつになりやすい。メリットもデメリットもあるのに片方しか言わないんだもん。だから統計で検証しなきゃいけないんだよ」
その視点は医療にとどまらず、交通安全週間中の防犯の手薄さ、スピード違反の取り締まり強化による自動車産業の競争力低下、相続税の低さが招くシニア世代の消費不況など、常識の“裏側”を立て続けに照らしていく。
「頭が良すぎるから、周りには変な人に見えるんだなって、最近思うんですよね」
そう語るのは脚本家の大石静さん(74)。和田さんとは長年の親交がある。
「映画オタクで記憶力も桁違い。言いたいことのペースに口が追いつかないほど、頭の中に思いと知識があふれている。医療制度改革への考えも明確で、困っている人への優しさも、あふれるほどあるんです。
あれだけ本が売れているってことは、共感してる人が多いんでしょうね。年寄りはすべてを諦めて静かにしてるのが美徳とされてきたけど、もっと生き生きしてていいんだよって主張に、勇気づけられた人が多かったと思います」
大石さんは精神科医としての和田さんの患者でもある。
「うつっぽいと感じて、15年前に紹介されて、診察を受けました」
以来、患者兼飲み友達としての付き合いが続いている。「映画や政治の話になると、情熱がほとばしりすぎて、頭がおかしいんじゃないかと思うときもあるんですけど(笑)、診察中は穏やかで、患者思いのいい先生です。私だけに優しいのかと思ったら、待合室でほかの患者さんとのやりとりを聞いて、誰にでもそうなんだとわかりました」
大石さんの夫も和田さんの患者だった。
「夫は晩年、老人性うつで元気がなく、遊離テストステロン(男性ホルモン)の注射をしていただいてました。打つと明らかに気力が出るんですよ。先生は夫のグダグダした話も優しく聞いて、薬についても丁寧に説明をしてくださいました」
日本で今主流の、薬で抑える精神医学とは、一線を画す。
「独自のスタンスで、今もすごく勉強されている。向き合うと心が休まる、頼れる先生です。2つの顔を持っていらっしゃる気がします」
いじめられっ子を救った母の教え
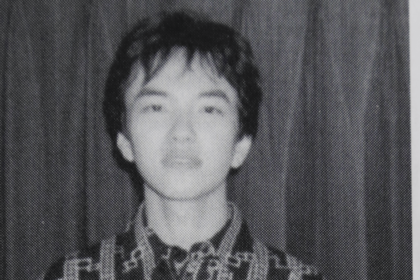
「友達なんて要らない」幼いころは、そう思っていたと和田さん。
'60年、日本が高度成長期に入ったころ、大阪・東淀川で会社員の父と専業主婦の母のもとに生まれた。年子の弟とともに4人家族で育つ。
父の転勤により少年時代に6回の転校を経験し、そのたびいじめに遭った。
「東京では大阪弁でばかにされ、大阪に戻れば東京の言葉で嫌なやつと言われた」
身体は小さく、運動もケンカも苦手。さらに「今でいう自閉症スペクトラムやADHDの傾向があった」と自己分析する。落ち着きがなく、人の気持ちがわからない子どもだったという。
それでも母は「性格を直せ」とも「みんなに合わせろ」とも言わなかった。大阪弁をばかにされたときも、「東京は田舎者の集まりやねんから、大阪のほうが歴史あんねん」と笑い飛ばし、言葉を直す必要はないと励ました。
友達付き合いには興味が持てず、兄弟の絆が深かった。弟とよく漫才ごっこをして遊んでいたという。
「みんなと同じことを言ってるやつはつまんないって、子どもなりに思ってたのね。小学生の間は、自分は天才だと思ってたからさ」
記憶力は並だったというが、知ることへの関心は尽きなかった。背中を押したのは母の一言。
「おまえは変わってるんやから、医者でも弁護士でも、なんか免状取らないと食っていかれへんよ」
個性を否定せず、生きる道を示したその言葉が、いじめられっ子の和田さんに、学問で身を立てる覚悟を与えた。「親が邪魔せず、伸ばしてくれたのはありがたかったですね。僕は今、弱者の味方になりたいとか、世の中を良くしたいとか思うようになったけどさ。人と合わせるとか、みんなが言ってることが正しいなんて考え方とは真逆だったし。それが僕の発想の基です」
挫折続きの青年を魅了した映画

名門・灘中学校に進学した。個性的な仲間に出会えると期待したが、待っていたのは頭脳明晰でスポーツも得意、礼儀も完璧なエリートたち。「俺みたいな変人ばっかりかと思ったら、全然そんなことなくてさ」と肩透かしを食らった。家庭環境にも差を感じた。
「うちは平均的なサラリーマン家庭で、父は関西の私大出身、母は高卒。同級生の親の3分の1は医者。残りも東大や京大、阪大出身の銀行支店長とかだったからさ」
劣等感と疎外感から、ラジオの深夜放送にのめり込む。あのねのねや山本コウタローの軽妙な語りに、大人の雰囲気や東京への憧れを募らせた。英語学習を口実に買ってもらった高性能ラジオで東京の電波をキャッチし、朝まで聴きふける生活を送った。
やがて、トップで入学した成績は急降下し、中学1年の終わりには173人中127位まで落ち込んでいく。
「勉強しか取り柄がなかったのに、それすらできなくなって、みじめになったね」
そんなとき、講演に訪れた灘高卒業生の遠藤周作さんの、ユーモアと挫折を交えた語りに心を打たれ、「小説家になる」と決意するも、筆は進まず、すぐに断念。ギター、生徒会選挙、留学生試験もすべて失敗に終わり、何をやってもうまくいかない日々が続いた。
転機は高校2年のとき。映画『赤い鳥逃げた?』の中で繰り返される「なんとかしなくっちゃ」という言葉が耳に残り、エンドロールを見ながら気づく。
「映画は脚本が書けなくても、音楽が作れなくても、カメラを回せなくても、監督の思いがあればできる芸術なんだ」
いくつもの挫折を経験した和田さんにとって、映画が唯一の希望になった。
「それから授業をさぼって、1年で300本見ていたよ」
日活の助監督試験を目指すが、映画不況で中止に。そこで考えた代案が、医師として働きながら映画資金を貯めるという道。
「医者になれば、映画を撮るための資金を数年で貯められるし、免状があれば再就職もできると思って、医学部志望に変わるわけ」
地方の国立大学では監督への道が遠くなると考え、東京か京都の大学を志望することに。当時の成績では届かないと察した和田さんは、独自の勉強法を編み出した。
「数学は暗記、受験は要領」と割り切り、解法パターンを徹底的に覚えた。また、灘高では東大合格日本一を守る団体戦の意識があり、参考書や模試情報を共有し、助け合う中で、仲間と協力する大切さも知る。
「へこたれちゃあかんで、と励まし合ってたのね。足の引っ張り合いより効率いいから」
そうして見事、東京大学理科三類に現役合格を果たす。
人気雑誌で磨いた要領の良さ
「有意義だと思わないですよ、まったく」
東京大学医学部での日々を、そう振り返る。授業にはほとんど出ず、履修はわずか3コマ。受講もせず、試験は過去問で乗り切った。

大学生活は映画監督になるための“ステップ”。勉強より夢に向かって現実を突破する時間だった。山口百恵さんの引退に合わせて立ち上げた「東大アイドルプロデュース研究会」では、自作映画の主演探しも兼ねて「百恵の次のアイドルは東大生が選ぶ」と打ち出し、メディアの注目を集めた。そして、2000人の応募から13歳の武田久美子をデビューさせる。
16ミリカメラを買い、衣装もプロ仕様で映画製作に挑戦。だが半年かけても撮影は半分しか進まず、「段取りを覚えてこい」と衣装会社の社長にたしなめられた。
“早撮監督”富本壮吉氏を紹介され、衣装部助手として『家政婦は見た!』第1作に参加して修業することに。撮影前の衣装を誤って返却する失敗もあり「東大生は使えない」と散々に言われたが、大女優の故・吉行和子さんだけは優しく接してくれたという。
「受験勉強だけでなく、何事もやり方を知らないとできないってことを知るわけだよ」
映画製作にかかるフィルム代は高額で、気づけば100万円の借金。そんなとき、アイドルイベントの取材で知り合った編集者たちが「家庭教師より割がいいかも」とライターの仕事をすすめてくれた。
当時、毎週100万部以上を売っていた『週刊プレイボーイ』と創刊間もない『CanCam』の編集部でアルバイトを開始。そこでも、効率重視のスタイルを貫いた。
「『CanCam』では女子大生に登場してもらう企画をやってた。取材費で週に3、4回、いろんな女の子とデートして、話を聞き出し、『週プレ』では女子大生の好きなスポットやギャル用語の記事を書いてたんだよ」
当時『週プレ』編集長だった島地勝彦さん(84)は、和田さんを「突き抜けてたね」と評する。
「女子大生10人集めてディスカッションしてくれない?って言うと、“はい、わかりました”ってすぐやってくれた。普通のやつは集められないよ。和田の最大の武器は“東大医学部という肩書”。相手は安心するしね。でも悪さはしなかった、あいつ、紳士だったから」
和田さんは編集部で働く傍ら、灘高で培った要領重視の勉強法を広めようと受験塾「鉄緑会」を立ち上げた。きっかけは、東大進学率が低い高校に通う弟が「僕の成績が悪いのは学校のせい」と漏らしたこと。そこで独自の教え方で東大文科一類合格へ導いたという。
「突破する力は根性じゃなくやり方。遺伝や家庭の収入より、効率よく努力すれば誰でも道は開けると証明したかったんだ」
塾はやがてスパルタ式に変わり、要領重視のポリシーと合わなくなった。本人は「追い出されちゃった」と笑うが、主義が違えば、きっぱり決別し、別の道へ突き進むのも和田さんの流儀だ。
受験本が大ベストセラーに!

東京大学医学部を卒業後、選んだのは精神科。「内科は無理、外科は手先が不器用すぎる」と自覚しての選択だったが、当時の所属先は東大闘争の余波で混乱していた。
「全然勉強にならないから」
と2年目には精神科医師連合とケンカ別れし、老年科神経内科へと進む。
同時期に、学生ライター時代に知り合った女子大生と結婚。妻の実家がある水戸の病院で後期研修医として働いていたころ、編集者から電話がかかってくる。
「おまえの言ってた受験勉強のやり方、面白いから、本にしない?」
こうして'87年、『受験は要領』(PHP文庫)が出版され、シリーズ累計200万部を超える大ベストセラーに。その印税でアメリカ留学を果たす。
米国カール・メニンガー精神医学校で2年半学び、フロイトの「無意識」理論を否定し、共感と対話を重視する「自己心理学」に触れた。アメリカでは精神分析は「客商売」。当時1時間200〜300ドルの対話で、患者が納得しなければ離れていく。
「あなたの無意識はこうだと言われると、日本人は素直に聞くかもしれないけど、アメリカ人は即退席。共感されるほうが大事なんだよ」
この姿勢は日本の学会では受け入れられず、「完全に干された」と笑う。
帰国後、東京・杉並区の老人専門病院「浴風会」に勤務。ここでの足かけ9年間が人生観を大きく変える契機となる。
まず衝撃を受けたのは、医療の“常識”が現場では通用しないという事実だった。
「タバコを吸う人と吸わない人の死亡率に差がなかったり、血圧が130でも150でも死亡率に変化がなかったり。高齢者の血糖値と死亡率に相関がないことも明らかになった」
教科書の理屈と、目の前の現実はまるで違う。
「日本の医者は理屈ばっかり。現実を見て、やり方を変えるべきなのに」
さらに、そこでの病室での光景が価値観を塗り替えた。かつて社会的地位の高かった入居者たちが認知症や寝たきりになっても、見舞いに来る人が誰もいない。
「上の人に媚びて出世したやつって、下に嫌われてるから、全然見舞いが来ないんだよ」
一方で、部下や後輩を大切にしていた人のもとには、見舞いが絶えなかった。
「地位とか役職なんて一過性のもの。その地位を手放した途端に、ただの人になる。それのためにガツガツするのは、やめようと思った」
37歳で常勤医を辞め、執筆や講演に専念する決断をした。非常勤で残ろうとしたが「制度がない」と断られ、「上の都合で辞めさせられた感じかな」と、また笑う。
同じころ、東京大学の教育心理学研究会に認知心理学を学ぶために参加。臨床心理士・植木理恵さん(49)が、和田さんとの出会いを振り返る。
「最初は腰が低くて、私なんかがいてすみませんと、小さくなって座っていたんです」
だが議論が始まると空気は一変。当時の東大では「ゆとり教育」が主流で、詰め込み型からの脱却が語られていた。その日も賛同者が多い中、和田さんはこう問いかけた。
「その“ゆとり”って誰のためのものですか? 先生や大人の都合じゃないんですか? 子どもが望んでるんですか?」
会場は静まり返ったという。
「ゆとり教育の本丸に、1人で丸腰で乗り込んできた感じで、相当やり合ってました(笑)。当時、お子さんが小さくて、学校がちゃんと教えてくれないと困るって本気で怒ってて、日本がダメになるぞって危機感を訴えてましたね。
怒りを原動力に社会に問いかけてて、ずっとブレてないんですよ」
ただし酒に酔うと、街の誘導員や警察官に「これ何の工事?」「ストーカー案件どうなってる?」と真顔で詰め寄る癖は、やめてほしいと植木さんは釘を刺す。
「ベルトがちぎれそうなほど止めたことがあります(笑)」
47歳で叶えた映画監督になる夢

40歳で出した『大人のための勉強法』(PHP新書)が広く読まれ、「大人こそ学び直すべき」と共感を集め、人生が再始動した。女性誌での連載をきっかけに、取材名目でワインを飲む機会が増え、次第にハマっていったという。
人の縁もワインを通じて広がった。
和田さん主催のワイン会には、パトリック・ハーランさん、鎧塚俊彦さん、吉田尚正さん(宮内庁皇嗣職大夫)ら多彩な顔ぶれが集まる。そのメンバーの一人、元「風」のミュージシャン・伊勢正三さん(73)は、和田さんの経歴を聞いて、「最初はとっつきにくい人かと思っていた」と語るが、気配りの良さと正直な人柄に触れ、印象が一変したという。そして、共感したのは“マリアージュ”的哲学。
「高級ワインはキャビアやトリュフと合わせるものと決めつけてる人が多いけど、和田さんは王将の餃子とこれが合うとか(笑)。見栄を張らず実を取る、その感じがすごくいいんですよ」
47歳でワイン仲間の支援を受け、念願の映画製作に踏み出した。初監督作『受験のシンデレラ』では、余命宣告を受けた予備校講師が貧困家庭の女子高生を東大合格へ導く姿を描いた。
作品はモナコ国際映画祭でグランプリを受賞したが、「受験がテーマだし、ヒットすると思ったら、大コケして」と興行面では苦戦した。
続く『「わたし」の人生』では、認知症の父を介護するためにキャリアを手放す女性教授を主人公に。
「保育園ばかりが話題になるけど、介護施設が足りなくて困っている人たちがいる。50、60代の女性たちがもう活躍しなくていいと世間から扱われているような現実を描きたかった」
その後も性被害など社会課題を軸に映画を撮り続ける。
「映画は“ライフワーク”だと思ってるからさ。資金さえあればもっと撮りたい。映画館はシニアで満席なのに、作品は若者向けばかりなのはおかしい。シニアに喜ばれる映画を作りたいんですよ」
近年は政党「幸齢党」の活動にも力を注ぐ。'25年6月に設立し、参院選では医療ジャーナリストの吉沢恵理氏を推薦。議席獲得には至らなかったが、年齢差別禁止法の制定やAI介護ロボット導入など独自の政策で注目を集めた。政党設立には約4500万円を投じたという。
「なんとかして日本の医療を変えたいし、高齢者には少しでも幸せになってほしいと思ってるんですよ。映画も政党も1人ではできないことだし、お金もかかる。でも、そういうことをうまく進めていきたいと思うんですよね」
その情熱と行動力に対して、周囲の反応はさまざまだ。前出の大石静さんは、映画製作について「着想は素晴らしいけど、監督術に痺れたことは、まだないです」と飾らず話す。
「幸齢党」設立時も、散財するばかりだと、灘や東大時代の友人たちは、みな心配して心から反対していた。
「選挙運動も不器用な感じでしたよね。あんなに頭がいいのに不思議です。きっと、みんなが自分と同じように理解できると思ってしまって、うまく伝わらないのかもしれません。医師としての腕も確かでいい先生なのに、映画も撮りたい、世の中も変えたいという思いを抑えきれない、むちゃくちゃな人なんですよ」
離婚後に貫く節制しない生活

最新刊『65歳、いまが楽園』(扶桑社新書)には、「簡単に言うことを聞かないシニアが社会を変える」「介護ロボットがいれば一生自宅で過ごせる」など、斬新で前向きなメッセージが並ぶ。そんな和田さん自身にとっての“人生の楽園”とは、どんなものなのか。
週4回は好物のラーメンを食べ、毎晩ワインを嗜み、時に高級ステーキも。節制よりも食の楽しみを優先する生活だという。
「シニアは我慢よりグルメ。そのほうが栄養も免疫力も上がる。僕は血圧も血糖値も“人体実験”のつもりでほったらかしにしてるからさ」
病気の不安について聞くと、「考えたってしょうがないじゃない。死ぬときは野垂れ死にだと思ってるからさ」と覚悟をにじませながら、冗談交じりに語った。
実は、10年ほど前に離婚したことも初めて明かした。

「結婚生活が苦しくなって、子どもが大きくなった後に離婚した。娘たちが弁護士や医者になったり、東大に入ったのは、僕のおかげみたいに思われがちなんだけど、それはまったくなくて、100%妻の力。僕がそもそも、ちゃんとした家庭なんて持てるはずのない人間だからさ。でも、子どももおかしくならなかったし、妻には感謝してます」
現在は1人暮らし。洗濯も掃除も自分でこなし、不便さを感じながらも「人生を楽しむほうを選んじゃってるからさ」とボソリ。恋愛については「今はしてないし、この病気(前立腺肥大)で困ってる」と苦笑いする。
そんな自由な暮らしぶりは、お金の使い方にも表れている。印税の多くをワインに、そして政党や映画にも惜しみなく私財を注ぎ込む。
「たくさん使いたいから、たくさん働くだけ。死ぬまで仕事するつもりだよ。節約するより、好きなことにお金を使うほうが経済も回るし、若々しくいられるからね。受験だけじゃなく、老後も人生も、すべては要領ですよ」

年齢にとらわれず働くことをすすめ、「レンタルおばあちゃん」のような新しい働き方も、人生を楽しむ方法のひとつとして紹介している。
現在の生き方に至るまで、孤独と向き合う時間もあった。少年時代には「友達は要らない」と、人と距離を置き、率直な性格ゆえに組織と衝突し、孤立したこともある。今では、本音で語り合える仲間がそばにいる。
和田さんが描いた“楽園”は、最新小説『新楢山考』(文藝春秋『オール讀物』'24年11・12月号掲載)に結実している。物語では、捨てられた老人たちが山で寄り添い、獣の肉を食べ、自由な性を楽しみながら、新たな世界を築いていく。亡き妻を追って死のうとしていた主人公が、そこで生きる歓びを見つける姿に、「悩まず書けた」と語る自身の思いが重なる。
今後のことに触れると、「うーん」と唸り、こう続けた。
「結局、どんな生き方をしても、一生は一度しかないし、死なない人はいない。毎日、食いたいものを食い、飲みたいものを飲むって、そういう話ですよね!」
昔のボス、前出の島地勝彦さんは言う。
「和田はね、一言でいえば、ロマンティックな愚か者なんですよ」
それは、自分自身が納得する人生を追いかけている男への、最大の賛辞なのかもしれない。
<取材・文/森きわこ>