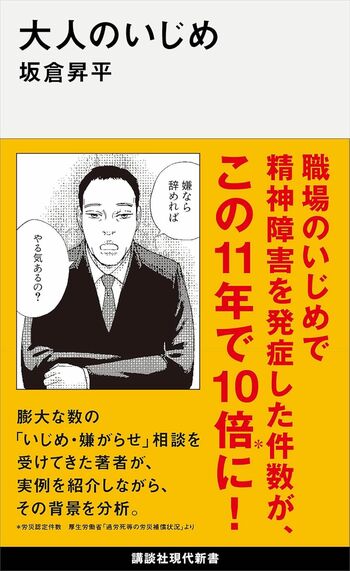労働現場での人手不足が加速している昨今。特に肉体労働や軽作業、サービス業などの職種においてはますます労働力の需要が高まり、働き手にとってはより売り手市場になる。
経済界からはそんな予測が聞こえてくるが、65歳を過ぎても働くことが当たり前となりつつある今、シニアにとってこうした職を得やすくなる状況は、本当に“渡りに船”なのか、それとも──。
シニアの労働市場、そして労働環境に詳しい専門家に話を聞いた。
シニアも多様な働き方ができる時代
「ここ数年、60代以上への求人は急増しています」
そう話すのは、『マイナビミドルシニア』編集長の三好裕さん。求人の多くを占めるのは介護や清掃といった職種で、全体の約40%だと現状を教えてくれた。
「肉体労働に近い仕事、例えば飲食店やコンビニなどでの接客といった仕事も合わせると全体の70~80%を占めます。60~70代になると事務などホワイトカラーの求人は一気に減りますが、人手不足といわれる業界がシニアへの求人に力を入れつつあり、働き先の間口は広がっています」(三好さん、以下同)
60代以上の女性への求人に多いのは、介護ヘルパーや清掃、マンションの管理人など。比較的男性の雇用が多いが警備や送迎ドライバーもシニアが活躍している現場だ。
「介護の仕事は資格の有無が賃金に影響しますが、そのほかは基本的に未経験が前提の求人です。そのため時給はそれぞれの都道府県の最低賃金、例えば東京都の場合は1163円からスタートすることが多いですが、逆に誰もがトライしやすい状況だともいえます。また、良くも悪くも人手不足の業界ゆえに、年齢による雇い止めはほぼありません」
そのなかでも三好さんがシニア層におすすめするのは、マンションの管理人だ。
「フルタイムはもちろん、週に数回、午前中だけなど自分に合った勤務時間を選びやすい上に、エリアによっては超がつくほど人手不足で時給は上り調子。採用代行業者もありますから、70歳を超えても新たに仕事を得やすいです」
また、高賃金を狙うならドライバーもおすすめ。なかでも配送ドライバーの需要は高く、高賃金の求人が多い。
また、採用されやすいのは雇用人数が多い倉庫や配送センターなどでの軽作業。検品や荷物の積み上げなど、いずれも業務が単調でマニュアル化されているため、シニアでも仕事が覚えやすく働きやすいと人気だ。
「前出のマンションの管理人以外でも、今は週に数回、1日数時間などフルタイムではない求人が増加。“この曜日のこの時間に働いてほしい”というピンポイントの求人のほうが高時給の場合もあります。自分の体力、気力と相談しながら希望する賃金を得られるように、ダブルワーク、トリプルワークをしているシニアも増えていますね」
年齢を考慮されない過酷な労働現場も!
一方、働くシニアが増えて新たな問題も生まれている。
「2020年前後から、65歳以上のシニア世代からの労働相談が増えました」
そう指摘するのは、労働問題に取り組むNPO法人「POSSE」理事の坂倉昇平さん。特に多いのは、若い世代が敬遠しがちで職場のシニア割合が高い介護や清掃、警備などでの労災相談だ。
「ほぼシニア層が担っているといっても過言ではない新聞配達員の交通事故なども少なくない。いずれにしろ、人手不足が心配されている仕事ばかり。いかに高齢労働者がエッセンシャルワーカーとして社会を支えているかわかります」(坂倉さん、以下同)
人手が足りない現場ゆえに、無理をして働かざるをえない場合も多く、勤務中の事故やケガのほか、病気などの労働災害に関する相談もあると坂倉さん。シニアの労働者は「シワ寄せを受けている」と危惧する。

例えば、清掃業で働く70代の女性は、人手が足りないからと勤務時間をどんどん増やされ、清掃作業中に階段から落ちて骨折し相談に訪れた。
「転落事故は勤務過多のせいではなく“年齢のせい”で起きたことだと決めつけられ、労災保険の休業補償給付の申請をさせないために出勤までも強要されるという状況でした。
ここまで悪質でなくとも、体調を崩したら“何とか頑張って”と断れないように迫ったり、退職を口にすると“○○さん(同僚)が困るよ”と責められたという話はよく耳にします。さらに、同じ業務でも若者よりシニア世代のほうが低時給ということも起きています」
加えて、肉体労働や単純作業、軽作業の仕事自体が軽んじられているという現実もある。夜間の施設警備を行う60代後半の男性は、見回り時の懐中電灯すら会社が用意してくれず、ケガを防ぐために自腹で用意した。
「“高齢者がする簡単な仕事”だと過小評価され、安心安全な仕事環境を提供してもらえないケースも。シニア世代は転職がしづらい、労働環境が多少悪くても若者のように声を上げたりSNS等で拡散することがないので“足元を見ている”と感じることが多いです」
シニアが働くことは、お金を稼ぐためだけでなく、社会とつながりが持て、体力維持にも役立つとして奨励されているが、根本的な問題が隠されているのではと坂倉さん。
「健康や社会貢献は大事ですが、低年金による経済的な不安定さや、シニアの労働環境に対する配慮のなさを覆い隠すための建前になってはいないか。危険な職場でも我慢して働かないと生きていけないような社会は、変えていかなければならなりません」
巷に蔓延る過酷なシニア労働の実情
CASE1:Aさん(60代・女性)「訪問介護の掛け持ち詰め込みでキャパオーバー」
在宅介護を行う事業所で訪問介護員(ホームヘルパー)として週5日働き、勤務日は担当する家を自転車で何軒もはしごしていたAさん。
事業所は介護報酬を増やすべく1軒でも多く被介護者宅を訪れる予定を組むため、シフトの移動時間は常にギリギリだった。
ある日、前の現場で少し時間超過してしまい、いつにも増したスピードで次の現場へ向かっていたところ、思い切り転倒。腕と足を骨折して入院し、リハビリを含め半年も休職となった。
CASE2:Bさん(70代・女性)「高齢者だからヒマでしょ?」とハードなシフト
近所のスーパーで働くBさんは、早朝からの品出しが主な仕事。
他の30~40代の同僚より比較的時間に余裕があるという自覚はあるが、週末や年末年始などの繁忙期は「どうせ予定なんてないだろう」と思われているのか都合を聞かれることなく勝手に勤務日にされることが続き困惑している。
さらに、他の人が敬遠する倉庫の整理を1人で担当させられ、無理がたたって転倒し負傷。年齢的に転職は難しいので我慢しているが、ぞんざいな扱いをされてつらい。

教えてくれたのは……坂倉昇平さん●ハラスメント対策専門家。労働問題に取り組むNPO法人「POSSE」の理事として、年間約5000件の労働相談に携わる。著書に『大人のいじめ』(講談社)ほか。
取材・文/河端直子