日本社会の現状に、「遅れてる! 海外ではありえない!」なんて目くじらを立てている人もいますが……。いえいえ、他の国の皆さんも基本は一緒!「衝撃」「笑える」「トホホ」がキーワードの世界の下世話なニュースを、Xで圧倒的な人気を誇る「May_Roma」(めいろま)こと谷本真由美さんに紹介していただきます。当事者だったはずなのに……イギリス人は、中東問題に無関心!?
発端は“三枚舌外交”
私が暮らすロンドンでも、連日のようにイスラエルとイランの交戦が伝えられています。イスラエルと中東の問題は、もともとイギリスが異なる相手と交わした3つの協定を発端としています。1つが、イギリスが第1次世界大戦に勝ったらパレスチナという土地にアラブ人の国をつくるという、アラブ人との約束である「フサイン=マクマホン協定」(1915年)。2つ目が、イギリスがロシア、フランスと約束したもので、戦争に勝ったらオスマン帝国のアラブ人地域をこの3国で分けるという「サイクス・ピコ協定」('16年)。最後が、イギリスが勝ったら、イスラエルというユダヤ人の国をつくるという約束─「バルフォア宣言」('17年)です。世界史の教科書にもありましたよね。
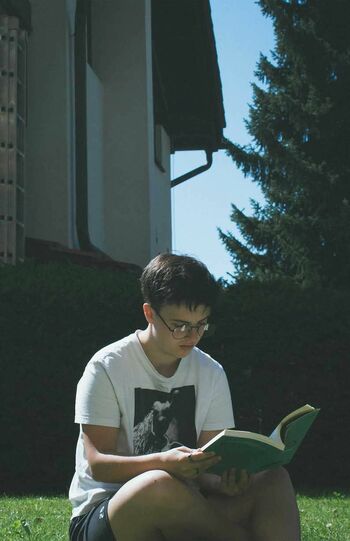
この“三枚舌外交”の結果、今日までパレスチナ問題は続いているわけですが、火種の当事者であるイギリス国民の多くが、実はこの事実を理解していません。というのも、イギリスの学校教育ではパレスチナの歴史について、ごく軽くしか触れないからです。イギリスの歴史教育は、歴代の国王がどのような実績を残したか、イギリスが第2次世界大戦でいかにナチスを打ち破ったかといった「正」の側面は繰り返し教えるのですが、自国の植民地支配をはじめとした「負」の側面については、ほとんど触れられないんですね。
'70年代までイギリスは、労働党政権の影響が強く、左翼的な教育が行われていたため、負の歴史も伝える教育をしていました。ところが、'79年にサッチャー保守党政権が成立すると、イギリスの伝統や誇りを再評価する愛国的な教育方針に転換。そのため、'80年代以降に教育を受けてきたイギリス人は、先の三枚舌外交をよくわかっていないというわけです。
こんな調子ですから、南アフリカの支配をめぐって、イギリスとオランダ系移民(ボーア人)が戦ったアングロ・ボーア戦争も理解していません。実際には、イギリスが侵略を行ったにもかかわらず「相手が攻撃してきたから戦った」といった内容で伝えられ、敵が槍などで戦う中、イギリスは近代的な武器で勝利したという偏向的な教育に。イギリスが南アフリカの覇権を握ることで、その後、アパルトヘイト政策の成立に大きな影響を与えることになるわけですが……。どこの国でも、自国を礼賛するのは同じなんですね。



















