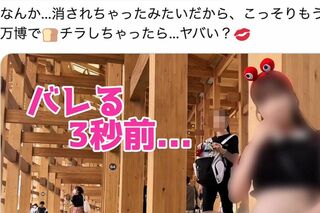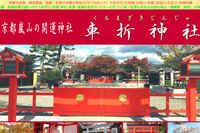人の命を奪ってまで家を出たかったはずの少年は、逃走せず自宅に戻るしかなかったとみられる。凶行の背景には何があったのか。
心の中に踏み込まないのが現代の“親友”
『誰でもいいから殺したかった!』(ベスト新書)などの著書がある新潟青陵大学大学院の碓井真史教授(社会心理学)は、思春期の少年少女についてこう指摘する。
「中学生ぐらいの少年少女にとっては、学校と家庭が世界のすべてなんです。その生活に不満があると、すべてがうまくいかないと思い込みやすい。周囲の大人は客観的に見て“理解者がいるはずだよ”などと諭しますが、響かない。
また、思春期に家庭に不満を持つのは不思議なことではありませんし、親を口汚く罵ることもあります。小学生までは父親や母親のあとをついていたのが、中学生ぐらいで友達を優先して大事にする転換期を迎えます。親のことをグチり合い、ストレスを発散するんです。その発散ができないと不満はどんどんたまります」
時代の流れで、少年少女の世代が築く交友関係にも変化がみられるという。
「以前は“親友”といえば、心の中にまで深く入り込んでくる存在でした。今は逆に、心の中には踏み込んでこない人が親友なんです。互いにそれがマナーであるかのように一線を引くんです。ネットなどで交友関係は広がり、軽い話はいくらでも楽しくできますが、深い悩みほど話せなくなります」(碓井教授)
若者は衝動性が高く、短絡的で、思い込みが激しいという。それでも犯罪に走るくらいならば家出したほうがよかったと思える。
「中学生にとって、家出は現実的な選択肢ではありません。まとまったお金を持っていませんから、友達宅に2泊程度のプチ家出がいいところで、お腹がすいたら家に戻るしかなくなります。見知らぬ土地で新生活を始めようにも、身分証なしに雇ってはくれません。ただ、中学3年生は高校受験を控えていますから、全寮制の高校に進学して家を出る道もあったはずです。
犯罪心理学で『ソーシャル・ボンド』という言葉があり、こんなことをしたら親が悲しむとか、友達を失うなどと考える社会的接着剤を指します。何かしら夢中になれるものや仲間がいれば、歯止めになった可能性もあるのですが」(碓井教授)

殺害された高橋さんは、夫と息子と暮らし、気さくで優しい人だったという。
現場にはたくさんの花が手向けられ、いなり寿司の供物も。お茶にようかんを供えて手を合わせていた市内の50代女性は言う。
「近所で起きた、こんな事件で亡くなって痛ましい。ご冥福をお祈りしました」
事件が起きた日は『母の日』。同世代の少年少女が少し照れくさそうにカーネーションを買って自宅に帰る中、逮捕少年は現場付近を歩き回って殺害相手を物色していたとみられる。
事情があったにせよ、奪った命は戻らない。