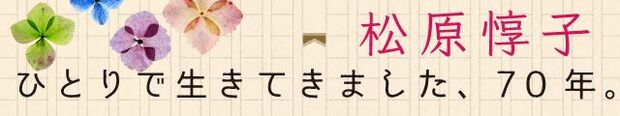1986年『女が家を買うとき』(文藝春秋)での作家デビューから、71歳に至る現在まで、一貫して「ひとりの生き方」を書き続けてきた松原惇子さんが、これから来る“老後ひとりぼっち時代”の生き方を問う不定期連載です。

第10回「母親と娘の微妙な関係」
今年10月に海竜社から『母の老い方観察記録』を出させてもらった。うちの92歳の母は、人生100年時代の生き方モデルのような人だ。外見は足も悪く、れっきとした老人だが、「もしかして、老人の袋をかぶったゼンマイ仕掛けの人形か」と思うほどよく動く。
この調子でいったら、母110歳、娘の89歳の老老母娘になってしまいそうで怖い。恐れるわたしを友人たちは「あなたのお母さんは絶対100歳越えはするわよ。日本一の長寿で国から表彰されるかも。アベが来るわよ」とおちょくる。そのころは誰が首相かしらね?
うちの両親の子育ては放任主義。戦争を体験している父は、“人間にとり自由ほど素晴らしいものはない”と、痛感したからだそうだ。
だから、わたしは誰からも束縛されずに気ままな人生。大学卒業とともに、結婚。離婚。その後、ひとり暮らしで生計をたて、27歳で息苦しい日本にさよならしてニューヨークに渡る。帰国してからは貧乏生活。もし、本を書く機会がなかったら、今頃、ホームレスになっていたかもしれない。
その自由に生きてきたわたしが、65歳で母と住むことになるとは……詳しいいきさつについては『母の老い方観察記録』にしっかりと書いたので読んでいただけたらと思うが、まさに青天の霹靂(へきれき)で、まったくわたしの予定表にはなかったことだ。
43年ぶりに、母の家に住んでみてわかったことは、今まで母を知らなかったことだ。「えっ、お母さんって、こんなにきつい人だったの? えっ、何で不機嫌なの?」
年に何回か会う母は、おしゃれで料理上手で友達も多く、素敵なお母さんだった。ところが、毎日顔を合わすようになり、素の母に愕然(がくぜん)とする。
ドアを閉める音まで気になる。そのうち気配まで気になりだした。生まれて初めて母に支配されている気がした。母と娘の場合、母が上なのだ。母も92歳なので「老いては子に従え」で、わたしが面倒を見るつもりだったが、その考えは間違っていたようだった。
母も同じで、どう接していいかわからず、苦しんだようだ。