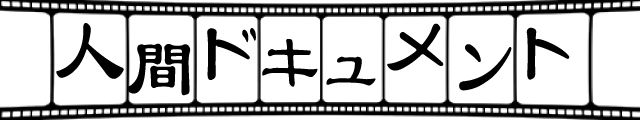ヤクザに拉致されても、怖くはない
「実況見分してくれたのが不良刑事で、友達みたいになったんです。その人に『俺たちはタダで撃てるから』と連れて行ってもらったポリス・アカデミーの射撃場で、『お前、防弾チョッキ着て撃たれたことないだろ』と言われて。なぜか防弾チョッキを着て、至近距離から銃で撃たれたんです。一瞬で人生観が変わるぐらいの衝撃でした」
こうした出来事が重なり、帰国した鈴木さんは暴力を取材テーマにしたいと考えた。
そして、ヤクザ専門誌『実話時代』編集部の扉を叩く。
「編集部に連絡したら、カメラマンは募集していないというので、とりあえず編集部員として入りました。すぐ辞めようと思っていたのですが、2か月ぐらいで『実話時代BULL』って雑誌の編集長にさせられて。編集長といっても要はクレーム担当で、若いやつにやらせるわけです。そこからずるずる今に至ります」
仕事内容は急変したが、少しずつヤクザの流儀を覚えていった。例えば、名前や組織の間違いなら、人間なら誰でもあるケアレスミスなので、謝れば許してもらえる。一方で、間違えられないのがケンカの勝ち負けだ。

「彼らはいかにケンカが強いかという表看板をしょっているから“負けた”はタブーだし、匂わせてもダメ。間違えたら訂正文を出すしかないんですけど、ヤクザは前例より大きい訂正文を出させたがるんです。1回やるとキリがないので、いかに小さなスペースに収めるかが勝負でした」
携帯電話がまだ普及していない時代。編集部に呼び出しの電話がかかってくることもあった。とはいえ、恐怖心はなかった。会って話せば仲よくなって人脈を広げられるし、根性を見せておかないと、「お前、あのとき来なかったよな」と、なめられるからだ。わかる気もするが、さらりと、「拉致されたこともあります」と聞いたときは耳を疑った。
「彼らはプロだから、殺人に見合うだけの利益がなければ殺さない。こちらも書いてはいけないラインがわかっているから、拉致されても怖くはないんです」
ほどなくしてフリーライターに転向し、精力的に暴力団関連の取材を続けた。そのころ、こんなアドバイスを送ってくれたヤクザがいた。
「『フリーになった以上、数年に1度はヤクザに襲撃されるようなことを書かないと、お前の名前が高まっていかないぞ』と言われたんです。それも一理あるなと、山口組があまり東京に進出していなかったころに、彼らが嫌がるようなことを10個ぐらいまとめて書いたんです。クレームもあったけど、無視しました」
自宅がバレるのを懸念した鈴木さんは、歌舞伎町に事務所を借りていた。ある朝5時ごろ、そのドアを叩く音がする。ハッと思うや室内に目出し帽をかぶった男が5人ほどなだれ込んできて、パソコンや備品を破壊された。
「顔を絨毯(じゅうたん)に押しつけられて引きずられたので、擦過傷みたいなものもできました。でも、痛いのなんて一瞬で、渦中にいる間は何も感じないんです。ギャングに襲撃されたときも同じで、恐怖は後からやってくる。ある程度、落ち着いて、庭の暗闇とかを見ているときに、今ここにヤクザが潜んでいたらどうしようと怖くなるんです」