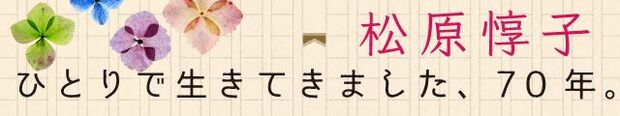老老介護の現実
「トイレに連れて行くのが一番大変。わたし40代じゃないのよ。70代よ。そのわたしが90代の母を引きずって、トイレまで行く。トイレにたどり着くまでに、私のほうが倒れそうになる。母の体重が軽くなったとはいえ、力が抜けている人の身体は重いのよ」
老女二人で真夜中の廊下にへたり込む時、悲しくなり涙が止まらなかったと正子さんは言うが、これが老老介護の現実だろう。
老いた自分が老いた母親の介護をすることも大変だが、老いて生きなくてはならない老いた母親のほうも大変だろう。このことを考えると、頭の中が出口のないトンネル状態になるのでやめる。
命は自分ではどうすることもできない。寿命を操作することはできないのは、頭ではわかっているが……。
7年間の介護の末に、母親が101歳で亡くなった時、ほっとしたと正子さんは語った。そう、ほっとしたのは母親も同じはずだ。
わたしの友人たちはひとり者が多い。そのせいか、よく、友人たちが集まると、「100歳まで生きたくないわね」という話になる。100歳までもどこまでも、どんな状態でも生きたい人もいるが、わたしは正直、そういう気持ちにはなれない。
わたしが「身体の限界だ。もう、これで十分。我が人生悔いなし」と思う時が来た時、死なせてほしいと思っている。これは本音だ。
幸せは個人により違う。幸せはこういうものだと決めつけることはできない。自分が幸せだと感じることだけが、幸せの真実ではないだろうか。
「自分にそんな時が来た時に、医者から合法的に薬をいただける世の中にならないかしらね」
笑いながらも本気で語り合うことが多くなった昨今だ。
※記事の内容を一部修正して更新しました(2018年9月3日14時58分)
<プロフィール>
松原惇子(まつばら・じゅんこ)
1947年、埼玉県生まれ。昭和女子大学卒業後、ニューヨーク市立クイーンズカレッジ大学院にてカウンセリングで修士課程修了。39歳のとき『女が家を買うとき』(文藝春秋)で作家デビュー。3作目の『クロワッサン症候群』はベストセラーとなり流行語に。一貫して「女性ひとりの生き方」をテーマに執筆、講演活動を行っている。NPO法人SSS(スリーエス)ネットワーク代表理事。著書に『「ひとりの老後」はこわくない』(PHP文庫)、『老後ひとりぼっち』(SB新書)など多数。