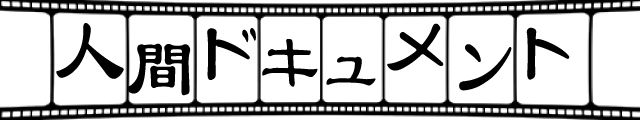それでも、気持ちを立て直し、前を向いてこられたのは、自分を頼る患者がいたからだ。
「八田先生が外来の日は、待合室が妊婦さんでいっぱいでした」、そう話すのは、宮内初子さん(59)。現在は、更年期障害でクリニックに通っているが、当時はお産を控えて、市立病院に通っていたという。
「八田先生に初めて診てもらったのは、妊娠後期で帯状疱疹になったときです。赤ちゃんに影響が出ないか心配する私に、丁寧に説明してくれて、すごく心強かったですね。産後も、“宮内さん、どうですか?”って何度も病室をのぞいてくれて。先生の人気の理由がわかりましたね」
医師として、全力を尽くす。その姿勢は、患者はもちろん、上司にも認められていた。しかし、評価が上がるほど、病院内では孤立していったと話す。
「市立病院の医師や看護師は公務員なので、できるだけ勤務時間内に仕事を終えるよう指示されていました。でも、私は時間を忘れて患者さんを診ていたので、多くのスタッフの方に迷惑をかけましたね。夕方になっても外来が終わらない。具合が悪くて、オペが必要と判断した患者さんがいれば、すぐに手術室を開けてほしいと掛け合った。
“先生の病院じゃないんだから!こんな時間に、今やらなくちゃいけない?明日じゃダメなの?”と、厳しい言葉を言われたことが何度もありました」
それでも、患者ファーストの姿勢を貫けたのは、数少ない理解者もいたからだ。当時の手術室の看護師長が、「患者さん思いの先生だから、何とかしてあげる」と、看護師を集めて時間外に手術室を開けてくれたときは、自然と涙が出たという。
体調を崩し父のもとへ
だが、ちょうど仕事も楽しくなってきたころ、激務がたたり、体調を崩した。
「朝、突然、嘔吐と下痢が止まらなくなり、最後は吐くものもなくなってのどから血が出て、血便になり、意識が遠のいて。それまで大きな病気をしたことがなかった私は、あぁ、こうやって人って死んでいくんだ、とぼんやり思ったものです」
すぐに市立病院へ救急搬送された。原因はウイルス性胃腸炎。救急病棟に5日間入院し、すっかり元気になったが、一緒に仕事をしていた仲間の先生からは、「そら見たことか」と、冷たい目を向けられた。
「そのころですね、潮時を感じたのは。父からも“戻ってこい”と言われていたし、自分の目指す医療をするためにも、父のもとで働こうと」
こうして、市立病院での5年間の勤務を終え、実家に戻る決意をした。
八田先生、31歳のときだ。