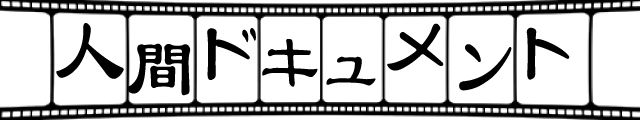父が最後に見せた医師の情熱
「この研ぎ澄ましたナイフのような腕で、バンバン患者さんを診るぞ!」、自信満々で実家に戻ったものの、「すぐに鼻をへし折られた」と笑う。
「もう鬼か!って思うほど、父にダメ出しされました」
勤務医時代の習慣で、ガーゼや綿球を使ったそばから捨てていると、「おまえ、それいくらすると思ってるんだ!」と叱られ、鉗子(かんし)を使えば、「こうやって持つんだ」と、細かく直された。
「開業医は経営者でもあるので、ものを大切にしなくちゃいけないし、医学書には載ってない、父ならではの指導も勉強になりました」
とはいえ、八田先生にも開業医としての理想があった。
「最新の医療機器を入れて、内視鏡手術をしたいとか、新しい風を吹かせたかった。でも、片っ端からダメだと言われ、“お父さんは古い!” “おまえは、危なっかしい!”と大ゲンカ。それこそ、世間を騒がせた家具店の父娘バトルみたいでした(笑)」
そんな父娘が、文句を言い合いながらも、あうんの呼吸で協力できるようになったのは、1~2年が過ぎたころ。
「父は昔の人なので、口数は多くなかったけど、『人思い』でした。診察時間が過ぎても、患者さんが来れば嫌な顔ひとつせずに診ていたし、治療費が払えなくても、“お金はいつでもいいよ”って。鷹揚(おうよう)な性格で、患者さんにも慕われていました。そんな父を見て、開業医として本当に大切なことに気づけたんですね」
当時を知る、元患者の野首久美子さん(76)が話す。
「50代だった当時、真理子先生の医院で子宮筋腫の手術を受け、退院後に腸閉塞で市立病院に入院したんです。子ども2人を帝王切開で産んでいたことが原因でした。
そうしたら、真理子先生が心配して、お見舞いに来てくれたんです。夜、仕事が終わってからわざわざ。で、私の元気な姿を見て、“よかったあ”って安心してくれて。息子が驚いてました。“母さん、ここまでしてくれる先生、見たことないよ”って」
親身で腕のいい女医がいる、評判は口コミで広がり、患者は日増しに増えていった。
開業医になって2年後の1998年には、『ジュノ・ヴェスタクリニック八田』と名称を変更。2008年に、お産の入院施設を閉鎖し、女性のヘルスケアを中心とした形へ舵を切った。

「おまえに、すべて教えたよ」やがて父親は娘を一人前と認め、診察のほとんどを八田先生に任せるようになった。
その矢先だった。父親に深刻な病が見つかったのは。
「膀胱がんでした。気づいたときは、腫瘍が5センチになっていました」
母親と八田先生は、セカンドオピニオンを求め、いくつもの病院を回った。しかし、回復は難しいと医師たちは口をそろえた。
「父も医者ですから、余命はわかっていたと思います。それでも、取り乱すことなく、身体が動くうちは診療を続け、医療ボランティアや、手術もしていました。
父は中絶手術が本当に上手で、亡くなる2か月前まで完璧にこなしました。術後、ソファでぐったり休む父の姿に、最後の最後まで医師としてまっとうする、情熱の魂を感じました」
2017年、3年にわたる闘病の末、父親は80歳で旅立った。立派な後継者を残し、満足したように──。
父親と娘、2代にわたって、看護師として支えてきた、今井よし子さんが話す。
「真理子先生が戻ってきたときは、正直、心配でした。お嬢様育ちなので(笑)。でも、大先生に鍛えられ、見違えるように成長しました。それを実感したのは、私が胃がんになったときです。
真理子先生に、退院の翌日から復帰してと言われたんです。早すぎるって思われるかもしれないけど、私は必要とされてうれしかった。早期といえどもがんになり、職場を失う不安がありました。真理子先生は、それに気づいて“早く戻ってきて”と言ってくれたんです。本当に情に厚くて、最近ますます大先生に似てきましたね」