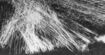国内で唯一、一般住民を巻き込んだ地上戦が行われた沖縄では、県民の20万人以上が亡くなっている。
元沖縄県立看護大学教授(精神保健看護学)の當山冨士子さんは、保健師を経て、大学の教員として長く学生の教育や研究に携わってきた。
「保健師は、受け持ち地域住民の健康管理をはじめ、個々の家族の相談にも関わっていきます。そのため家族の心身の健康だけでなく、背景や経済状況なども把握し、必要な支援をします」
當山さんは保健師のころ、戦争は過去の出来事としてしかとらえていなかった。しかし激戦地であった沖縄本島の南部の村から大学に移り、沖縄戦と精神保健についての研究を始めると「沖縄戦はいまだ終わっていない」と実感した。
そのため當山さんは、担当した事例を丹念に見ることにした。すると戦争を意識しないまま書いた支援記録から、沖縄戦の影響が見えてきたことに愕然とした。
沖縄戦のトラウマ反応は、ベトナム戦争の帰還兵の心理的な影響では言われていたが、沖縄戦では、なかなか認知されてこなかった。
精神的な影響として、まるで目の前で体験しているように昔の記憶が思い出されたり、興奮状態に陥ったり、発作が起きたりする。沖縄戦の話題を必要以上に避けることもある。あるいは、思い出すことで眠れなくなる。命日などの特定の日時や場所、時間、環境、匂いなどによって思い出し、不快な感情が出て、日常生活に支障をきたす。
同じく沖縄戦のトラウマを研究している精神科医の蟻塚亮二さんは、「トラウマを抱えた体験者の場合、掃除機の音が機銃掃射の音に聞こえたり、音が怖いので花火大会を見れなかったり、火薬の匂いがするのでマッチがすれなかったりもします」と指摘している。
前出の當山さんが以前、保健師をしていたのは離島と沖縄本島南部。本島南部のある村は人口約7000人。推定戦没者は当時の村の人口の約40%と県平均の25%を上回った。
この村で保健師が把握した精神疾患の患者は96人。支援し記録が残っていたのは40人だった。この40人に1990年、あらためて『沖縄戦と精神保健』の問題を中心に面接調査を行った。40人のうち、沖縄戦の影響が把握できたのは34人(男性20、女性14)。年齢は33歳から86歳で、平均57・3歳となっていた。
沖縄戦の影響(重複)は、大きく4つに分類。身内の死亡などの直接的影響が30人。死亡の内訳は、配偶者3人、両親4人、両親のいずれかは10人、長兄や長男9人、その他の同胞22人だった。また負傷は7人で、頭部の負傷は5人、このうち外傷性テンカン(疑いを含む)3人。精神疾患の発病等への直接的・間接的影響は10人。戦争そのものが誘因になったと思われるグループと、戦後の家庭問題が誘因になったと思われるグループに分けられた。
例えば、ヨシオさん(仮名=当時40歳)は戦時中盗みの疑いで、隣の壕に入り込んで来ていた日本兵に、頭や身体を殴打され半殺しの目にあい意識を失った。家族や周りの人たちは止めることができず、黙って見ているしかなかった。
「盗みもしていないのにあの兵隊が憎らしい」と、妻は顔をこわばらせて怒りをぶちまけた。命は取りとめたものの、終戦後から1日数回の発作が出ていた。
ヨシオさんの手足には農作業中の発作の際に作った生傷が絶えない。部屋には発作時のケガを予防するため、家具もろくに置けない。ストーブもない部屋は、冬には一層寒々としている。
PTSD様反応や不快な感情などがあったのは19人だった。マキコ(仮名=当時19歳)は当時のことが鮮明に脳裏に残っている。戦闘協力者として飛行場作りなどの作業をさせられていたが、「軍人に殺されはしないか」「周囲の人に軍人との関係を噂されるのではないか」と作業中も終始心の休まる時はなかった。