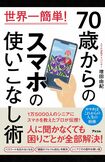自分に関するあらゆる情報が詰まったスマホ。でももし、自分が倒れてしまったら、困るのは家族。「本人のSNSにアクセスできなくて交友関係がわからない、ネット銀行や証券にいくらあるかもわからない……家族に迷惑をかけないため、60代になったらスマホじまいを意識して」と専門家は強調する。
シニア世代にとって必ずや“頼れる相棒”に
「“何これ?”って画面になったり、“入力内容が違う”といわれて先に進めなかったり。スマホはわけがわからないことだらけ。もう嫌になっちゃいました」
と、こぼすのは、70代のA子さん。シニア世代でスマホを持つ人は増えているが、A子さんのように操作に苦手意識を持つ人は多い。
「シニア世代がつまずくポイントはだいたい同じ。逆にいうと、そこさえクリアすれば、スマホはシニア世代にとって必ずや“頼れる相棒”になります」
と太鼓判を押すのは、スマホ活用アドバイザーで、1万5000人を超えるシニアをサポートしてきた増田由紀さん。
「スマホに蓄積された膨大な個人情報は、本人が亡くなった後の“スマホじまい”で家族を困らせる要因にもなってしまいます。いざというときにも備えて、スマホに慣れてもらいたいですね」
会員登録したサイトやネットショッピングでは、IDやパスワードなどの入力を求められるが、これがシニアのつまずきになる場合が多い。
「時間をかけて入力したのに、“入力内容に誤りがあります”といったメッセージが出るのは、文字の打ち間違いと入力もれが原因。数字の半角と全角、アルファベットの大文字と小文字などを間違えているケースが多いんです」
パスワードが思い出せないのも、あるあるパターン。
「安全面を考えれば同じものにすべきではありません。とはいえ、アカウントごとに違う数字や文字の組み合わせで、しかも大文字や小文字、記号の有無などの違いがあるわけですから、すべてを記憶するのはほぼ無理です」
そこで増田さんがすすめるのが「パスワード記録ノート」の作成だ。スマホ内ではなく、ノートに書いて保存するもの。
「スマホ内だと、スマホの故障や紛失時に見ることができないのが難点。そんなときにもノートに記録しておけば、パソコンから手続きするなど、何らかの対処ができます」
自分自身はもちろん、家族のためにもなる。実際、増田さんの講習を受けて作成したパスワード記録ノートが役に立った例は数多くある。
「他界された生徒さんの奥様から“お父さんがきちんと残してくれたから、助かりました”とお礼を言われたこともあります。パスワード記録ノートは、“家族への愛ある遺産”になるのです」