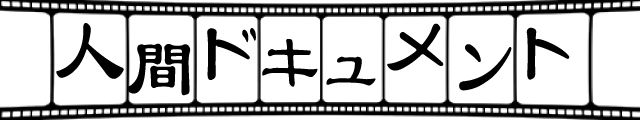「元祖イルカ遊び」で観光客が殺到
サーフィンを始めたのは20代半ば。旅先のセイシェルでサーファーに出会った。映画『ビッグ・ウェンズデー』にも影響を受けた。友人に湘南でサーフィンを教わってサーフボードをもらい、島に持ち帰ってから世界は変わった。店を細々と続けながら港の荷役の仕事も始め、自分で探索して作った地図を頼りにサーフポイントを探した。
「板の上に立つと海、波のエネルギーが足裏から全身に伝わってくる。サーフィンを始めて島に住む意味、自分の軸ができた。海、地球、宇宙のおかげで信じるものを見つけられた。何者かになりたかったけど、求めるものはどこか遠いところじゃなく海にあった。自分の中にあったんだ」
自分の住む場所に誇りを持ったとき、外の世界の人たちも、そこに集まってくることに気づいた。
’82年ごろ、内地や海外からサーファーがやってくるようになった。フランス海軍が使っていた「ゾディアック」というゴムボートを購入し、サーフボードをのせて誰も知らないサーフポイントに案内することも増えた。
イルカとの出会いも、サーフィンがきっかけだった。
「俺たちサーファーは、移動中にイルカを見つけるとボートを止めて一緒に遊び泳ぐようになった。イルカの邪魔をしないように静かに海に入りぐるぐる身体を回すと、イルカもまねをする。イルカがこちらを向くと、眉間がチクチクして、何かメッセージを送ってきた。サーフィンをしたときの地球と交信しているような感覚。ものすごい快感だった。ボートに這(は)い上がって気絶したよ」
宮川さんは、野生のイルカと遊ぶように泳ぐ「ドルフィンスイム」のパイオニアでもある。
「イルカと泳いだときに感じたあの感覚、素晴らしさを多くの人に知ってほしい。サーファーだけでなく、旅行者や観光客、通勤電車や雑踏から逃げてきた人たちに、素敵な気分になって帰ってもらいたい」そう思った。
’92年から「元祖イルカ遊び」と命名してツアーを始めると、その未知の体験はじわじわと口コミで広がり、ブームとなっていった。
火がつくと認知は爆発的に広がる。そのころから新聞や雑誌の取材も殺到。撮影コーディネートやクジラの生態調査などの協力も頼まれるようになった。世界では環境破壊が問題になり、エコブームに突入していた。研究者や著名人が小笠原を訪れ、テレビ番組や映画も作られた。
20年以上の仕事仲間であり友人でもある編集者・作家の森永博志さん(68)は、宮川さんとの出会いをこう語る。
「’96年、写真家の関口照生さんと製作した小笠原のドキュメンタリー映画の撮影をコーディネートしてくれたのが典継です。僕はそれまで世界中の島をいくつも訪れていたけど、小笠原ほど雄大な海は初めてで、圧倒されました」
そのころ、日本はオウムのサリン無差別テロや世紀末の空気に包まれていた。
「小笠原に来ると、解放されるような感覚になりました。真っ黒に日焼けした典継は、まさにアイランドって感じなのに、’60年代のカウンターカルチャーに傾倒していて、とても先端的だった」
撮影の合間にたくさんの話をした。アートや音楽、文学、話もアイデアも尽きない。宮川さんはジャンルを超えて幅広い知識を持っていた。
「カルチャーだけじゃない。宇宙、科学、禅─。すべてにおいて好奇心旺盛だった。島にいるから流行に影響を受けない。僕たちより何事においても一歩早い感じがした。まさに開拓者のイメージです」
森永さんは、宮川さんを島に住むシャーマンとして登場させた小説『PLANETIST NEVER DIES』を雑誌に連載したことも。
「海に出たら頼るものは何もない。サーファーでありボートを操る典継は身体ひとつで自然と対峙している。精神的・肉体的にも超人的な賢者。まさにプラネティストです」
惑星ボニンの住人。地球という小さな惑星の小さな父島には、ひとつの惑星に匹敵する世界が広がっている。