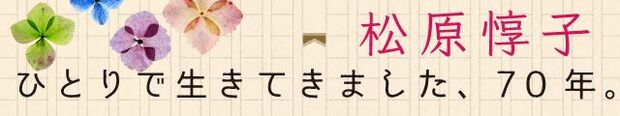1986年『女が家を買うとき』(文藝春秋)での作家デビューから、71歳に至る現在まで、一貫して「ひとりの生き方」を書き続けてきた松原惇子さんが、これから来る“老後ひとりぼっち時代”の生き方を問う不定期連載です。

第12回
がんとともに生きる人を支える
「マギーズ東京」を訪問
水泳の池江璃花子選手の白血病報道に驚いていると、今度はタレントの堀ちえみさんの舌がんのニュースが飛び込んできた。2人に1人はがんになる時代と言われているが、まだ若くて活躍中のおふたりだけに、「がんってやつは一体、何なの?」「なぜ、彼女たちを襲うのか?」と、怒りさえ湧いてくる。
本人もつらいだろうが、同じくらい家族や周りの人もつらいだろう。わたしにも経験がある。最も親しい友人から子宮頸がんで手術をすると聞いたときは、涙が止まらなかった。「神様、彼女を死なせないで!」と叫びたかったが、黙って聞いていただけだったように記憶している。
その友人は術後、5年生存率の危険ラインを見事にクリアし、今ではわたしよりも元気だが、いつも死を意識している、この気持ちは経験者にしかわからないと話す。
彼女が言うには、がんの人に「がんばってね」は禁句だという。なぜなら、もう十分に頑張っているからだ。
先日、わたしが代表理事を務める、おひとりさまの老後を応援するNPO法人『SSSネットワーク』の会員で、末期がんの女性を訪ねた。4年前にすい臓がんの手術をし、奇跡的に回復した彼女は、「ついに、観念するときが来たのね」と笑った。手術は成功したものの、そんなに長くは生きられないと察知した彼女は、残りの人生を悔いなく生きると決め、ピースボートで世界一周もした。貯金のほとんどは旅に費やした。
すっかり弱ってしまいベッドに横たわる彼女は、わたしの顔を見ると、わたしより明るく元気にこう言った。「わたしには、がんばれ!って、言ってくださいね。わたしはがんばりたいの!!」
それを聞いて「がんばれ! 負けるな!」とわたしが大声で言うと、「がんばるわよ!」とさらに大きな声で返してきた。
がん患者にとり“がんばって”の受け取り方が違う。患者のつらさは人それぞれであり、患者への対応やケアは本当に難しい。