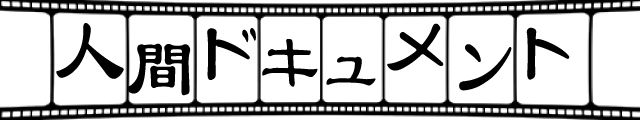「生まれてこなければ……」
ココさんは5歳のころに母親から言われた言葉を忘れられないでいる。
「あなたが生まれてこなければ、こんなに不幸な子(弟)は生まれてこなかった」
ココさんには3つ上の姉と3つ下の弟がいた。弟は生まれつきの難病で、入退院を繰り返していた。子どもは男女1人ずつが理想で、2人目が男の子なら3人目は産まなかったという意味だったとココさんは理解している。

「最初は意味がわからなかったけど、自分のせいで母がひどく悲しみ、自分を快く思っていないことはわかった。だから、私は悪い子なんだと途方に暮れていました。母はことあるごとに弟が可哀想だと泣いていた。私から見れば弟はそれなりに幸せに暮らしていたのに、どうして目の前で本人に向かって可哀想って言うんだろう、そんなことを言う母親は歪んでるって子どもながらに思ってた」
父親がいるときは偽の家族団欒が繰り広げられた。銀座で画廊をしていた父は家を空けることも多かった。母親と2人きりになると肉体的な虐待もあった。言葉による心理的な虐待に加え、洋服で見えないところにあざができるほどに叩かれ、倒れると蹴られた。母の気持ちを察した姉に、風呂場で浴槽に沈められたこともある。
「私、姉よりも何事も要領よくできたんです。勉強もできたし、絵も好きだった。広い家だったのでなるべく母や姉と顔を合わさないように、父の書斎の机の下や、螺旋階段の下の小さなスペースで過ごしていました」
螺旋階段の上のステンドグラスから差し込む光でホコリがチラチラと光る様子をじっと見つめているのが好きだった。どこで知ったかは忘れてしまったが、死のうと思って布団をかぶり、鉛筆を削るナイフで手首を切ったのも5歳のときだ。怖くて悲しくて、ほんの少し傷をつけることしかできなかった。
「小中学校の友達とも話が合わないし、することがないから本を読んだり勉強したりしてました。私にとって楽しかったのは、お絵描き教室とファッションだけだった」
家に仕立て屋さんが来て、生地を選び、母や姉と3人おそろいの服を作る。
「お仕立て屋さんがそこにいるから、そのときは自分の意思を出せる。この柄がいいって言えたんです」
高校生のころは画家を目指したが、父に「絵の才能はない」と言われ断念。デザインの専門学校に進んでファッションデザイナーになった。
20代後半、バブルの時代の3年間、ファッションの現場でチーフデザイナーとパタンナーとして、ともに駆け抜けた仲間が天野泉さんだ。仕事が別々になっても、互いに飾ることなく話すことができる長年の友人だ。
「ココさんは人の力を見抜く力があると思います。ココさんと組んでいたパタンナーは当時3人いてみんな個性的でしたが、得意なことややりたいこと、仕事のこだわりを見抜いて的確に仕事を依頼してくれました。それに、話すのも上手だけど、それ以上に聞き上手。サバサバしているようで優しいから、とても話しやすい。人間的にも総合力の高い人ですね。私にとっては、ともに戦った同志です」
隣で聞いていたココさんのファッション魂に火がつく。
「私ね、あのころの服も捨てられないものをたくさんとってあるんだけど、がっちゃんに着せると似合うんだ。私の服が私より似合うのよ(笑)。がっちゃんの宣材写真を撮影したときも、家にある服を持っていってスタイリングしたの。がっちゃんも、今まで無頓着だったのに今では取材が入る日は自分で洋服を選ぶようになったんです。
ファッションで自分を表現する素晴らしさを知ってくれたんだと思います。大好きだったファッションや絵が今の仕事でパズルのようにつながって、すごく楽しいし幸せ。人生で無駄なことは何もなかった。人間、長くやってみるもんだよね」
楽しそうに話すココさんを見て、泉さんが口を開く。
「第二の人生、さらに輝く場所を見つけてる。がっちゃんもがっちゃんの描く絵も、ココさんも、アトリエや個展で会うたびにどんどん進化してる。20代とは違う充実感が全身からあふれてて、同世代の女性としてうらやましい」