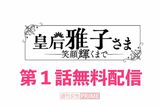生徒と一緒に土下座したことも

義家弘介さん。'99年に教員として母校に赴任し「ヤンキー先生」として慕われる。同校退職後、政治家に転身し文部科学省副大臣に就任するなど、教育現場に携わる。2025年3月に政界を引退。
平成に入ってから水を飲ませずに練習をするリスクや、体罰に対する問題意識も高まっていく。しかし平成も、いわゆる強豪校では厳しい指導がまかり通っていた。
「2010年代は“部活動のあり方”の根本的転換期でした。私が文部科学省の大臣政務官に就任した'12年、桜宮高校のバスケットボール部のキャプテンが顧問から受けた暴行や叱責を苦に自殺してしまった事件がありました。
このような悲劇を二度と繰り返してはならない、そう考えた私は、全国実態調査を指示しました。平成の後期でも無意味な正座を長時間させるケースや、1人が失敗したら連帯責任で全員がグラウンドを10周走る、なんて指導が多く残っていたんです」(義家さん)
その後、文部科学省は「運動部活動での指導のガイドライン」を作成。教育現場での周知に務め、今日に至っている。
ちなみに、義家さんが母校の北星学園余市高校で教壇に立っていた際には放送局、サッカー部、横ノリ部(サーフィン・スケートボード・スノーボード)の顧問を務めていたという。
「北星余市には個性的な生徒が多く通っています。当時はかつての自分のようなヤンチャな生徒やアクの強い生徒が多く、顧問としては公式戦以外の対外交流は極力避けたいと思っていたんですが、力を持て余している彼らの強い熱意にほだされて……しかし、案の定、乱闘騒ぎになってしまって、生徒と一緒に土下座して謝ったこともありました。私にとっての部活動顧問経験には、苦い思い出のほうが圧倒的に多いですね(苦笑)」(義家さん)
と、苦笑する義家さん。近年は教員不足の影響で部活動が廃止になる例もあり、活動の“維持”が難しくなっているという。教員の負担にならず、子どもたちが心から部活動を楽しめる仕組みづくりが必要なのかもしれない。