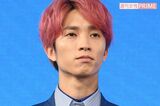「ずっと夫の不満を口にしながら別れようとしなかったり、金銭トラブルに巻き込まれているのにどうしようと言うだけで放置していたり。頭の中がこんがらがってしまい、整理できず、決められない人がすごく増えています」
そう話すのは、中島心理相談所所長の中島美鈴さん。公認心理師・臨床心理士・心理学博士として日々カウンセリングを行い、認知行動療法にまつわる多数の著書を持つ。
間違えたくないから決断を先延ばし
カウンセリングに訪れる人の悩みは、結婚や離婚、転職など人生の岐路だけではなく、例えば家電一つ買い替えるのも「決められない」のだという。そこには現代ならではの背景が。
「今の世の中、ネット社会でどんどん選択肢が増えていますよね。いざ情報収集をしようとすると、情報の海に溺れてしまう。それで結局選びきれず、面倒になって挫折してしまう。あと、絶対に失敗したくないから選べない、決められない、という人も。一つに決めてダメなら次の経験に生かそうという余裕がなく、選べないんです」
選択肢を目の前に、迷いに迷い、袋小路に入り込み、決めずに終わる。けれどそれは問題を先延ばしにしているだけ。放置していたぶん、問題がさらに膨らんでしまうこともある。
では、どうしたら頭の中を整理して、「決められる人」になれるのか。中島さんが提唱するのが『もじせか』。『も問題の明確化』『じ情報収集』『せ選択肢の作成』『か価値判断』の4つのステップだ。
ステップ1『問題の明確化』
頭の中でモヤモヤさせているだけでなく、「これは問題なのだ」とまずは自覚すること、と中島さん。
「モヤモヤしている人は、一つの問題だけでなく、いくつもの悩みでぐちゃぐちゃになっていることがあります。例えば、夫に対する不満に、嫁姑問題、子どもの悩みもあって、こんがらがっている。
まずはその中でどれが解決すべき問題なのか整理していく。そこに優先順位をつけ、問題を明確化する。頭の中だけで考えず、書き出してみるとわかりやすいでしょう」
問題を明確化したら、実際に自分はその問題を解決したいのか、解決するために自分で動くつもりがあるか、問題の解決像がイメージできるかどうかを見極めていく。
「ここで大切なのが、自分が主体になって考えること。家族や身近な人の意見は聞いても、最終的には本人が決める。自分はどうなりたいのか、具体的かつ現実的なゴールを思い描けるといいですね」