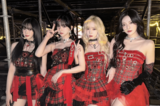育児との両立では夫や周りとの交流が支えに
ショートステイを利用するようになってからは、土日は友達と遊びに行ったり、楽しみができたことで岩佐さん自身、心に余裕ができた。
「離れた分、母のことを愛おしく思えるようにも。息抜きは必要だと痛感しました」
その後、岩佐さんが37歳の時に、中学の同級生だった男性と結婚。
「母の介護も一緒に支えると言ってくれた人でした。母は自宅で転倒して大腿骨を骨折し、車椅子生活となっていましたが、同居も受け入れてくれて。結婚を機に、母とともに大阪に引っ越しました」
そして一昨年長男が誕生。
「出産後は、自分の身体も万全ではない状態で、寝たきりになっていた母の介護と新生児の育児の両立は本当に大変で。気合で乗り切ろうとしましたが、心身の負荷が大きく血圧がどんどん上がってしまって。そこで、ケアマネジャーさんから言われたことを思い出しました。自分に余裕がないと無理がくるのは介護も育児も同じ。それからは素直に助けを求め、夫に力を借りるようにしました」
夫は、仕事が忙しいなかでも育児も介護もサポートしてくれている。
「今ではおむつ交換も喀痰吸引も、すべてできます。母と子どもを夫に任せて私が一人で買い物に行く時間もつくってくれるので、その時間を大切にしています」
桂子さんは今、歩くことも話すことも、食べ物を飲み込むこともできなくなり、現在は直接、胃に栄養剤を流し込んで命をつないでいる。
「大変なことはたくさんありましたが、私は介護をして本当によかったと思っています。できるなら、あと何十年でも介護を続けたいぐらい。そう思えるのも、いろんな方に支えてもらったから。介護したからこそ見えてきたものもたくさんあって、世界がぐっと広がりました。ただ、経験して感じたのは、介護の悩みを個別に相談できる場所があるといいなと」
その第一歩として、岩佐さんは現在、認知症の親を介護する子ども同士がオンラインで集まり、交流できる場をつくり、活動している。
「利用できるのに知られていない制度も実は多いんです。そんな情報も共有できたら。制度やサービスを利用することで、心の余裕にもつながりますから」
取材・文/當間優子