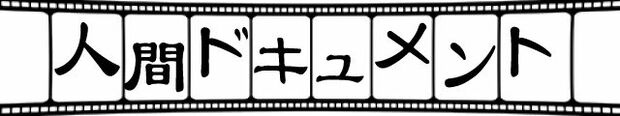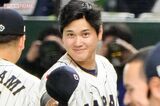大学病院に「メイク外来」を新設

2000年、かづきさんは精神科医や形成外科医などと連携した多角的な研究を進めるため、「顔と心と体研究会」を設立。2014年には公益社団法人となった。
活動を共にしてきた日本医科大学形成外科学教室主任教授・小川令さん(51)は、「リハビリメイクは医療の限界を補う重要な存在」だと話す。
「医療の進歩で手術によって命が救われても、外見の傷に悩み、人前に出られず、社会から孤立する患者さんは少なくありません。まさに“生き地獄”ともいえる状況です。かづき先生は、外見に悩む患者さんの生きる意欲や、再び社会とつながる力を引き出してこられました」
設立当初は、「化粧が医療になるのか?」という懐疑的な声も多かったそうだ。
「先生は逆風にも一切ブレず、現場で患者さんと丁寧に向き合い、“結果”で示し続けてこられました。例えば、熱傷で顔に瘢痕が残った患者さんが、リハビリメイクによって外出する勇気を得て笑顔を取り戻した姿は、医師や医学生に強い感銘を与えました」
こうした実績が評価され、日本医科大学付属病院など複数の大学病院で「リハビリメイク外来」が新設されていく。かづきさんは、日本形成外科学会や日本美容外科学会などでも研究成果を学会や論文で発表。メイク外来の増設や保険適用化なども目指している。
「リハビリメイクを求めて来る患者さんと向き合う時間こそ、自分らしくいられる瞬間。肩書のない私に悩みを打ち明け、傷を見せ、顔を触らせてくれた患者さんから、今の技術や考え方が生まれました。だから患者さんこそが、私の先生なんです」
高齢者の笑顔を生むボランティア
梅雨入り前の休日、神奈川県横浜市の特別養護老人ホーム「緑の郷」には、入所者の笑顔があふれていた。かづきさんが8人のボランティアとともに訪れ、高齢者にメイクをしていたのだ。
脳の病を乗り越え、最近入所した頼明美さん(88)を見るや、「あら、肌きれい! 明美ちゃん? よろしくね」と瞬時に緊張を解く声かけをしたかづきさん。まずハンドマッサージを行い、手のシミをカバー。丁寧なスキンケアのあと、ファンデーションを塗り、仕上げにチークとピンクオレンジの口紅を塗ると、鏡を見た頼さんは「あら~すごいわね。別人! 帝国ホテルに行かなきゃ!」と華やいだ笑顔を見せた。そばにいた娘さんが「昔、父とデートでよく行っていたのを思い出したのかな? 今日は頭がはっきりしていて、笑顔が違う」と驚いた。
施設の理事・古川幸子さん(75)はこう話す。
「先生が温かい声かけをしてくださるので、会話も弾んで、先生に会えるのを楽しみにする方が増えていきました」
1992年、40歳のときからこの活動を始めたかづきさんも、今では入所者の世代に近づいてきた。
「老人同士のメイクになってきたねって笑っています。私の母は56歳のときに亡くなったので、高齢の方を見ると、生きていたらこのくらいだったかなと思って。『してあげたいと思ったときに、その人はいない』っていうじゃないですか。だからこちらでのメイクは、母にできなかったことをしているようで、私も幸せな気持ちになるんです」