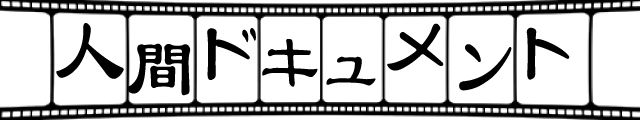「赤デメキン」と言われないための厚化粧
小学生のころのあだ名は、「赤デメキン」。この名に深く傷ついた経験こそが、かづきさんの原点である。
1952年7月、大阪府に生まれた。銀行員の父と専業主婦の母のもと、何不自由ない家庭で育ったが、身体が弱く、運動するとすぐ息が苦しくなった。冬は血流が滞り、顔が赤くむくんだため、悲しいあだ名がつけられた。
「今では笑って話せますが、当時は本当に嫌でしたね」
思春期になると、悩みはさらに深刻に。春から夏は元気に過ごせるのに、冬になると顔の赤みが強くなるとともに気分も沈み、成績も落ち込んだ。まるで二重人格のようだったという。
高校2年のある日、赤い顔を隠そうとファンデーションを塗って登校したところ、教師に「すぐ落としなさい」と叱られた。「みんなと同じ肌色に近づけたかっただけなのに」と心の中で叫んだが、思いを言葉にできなかった。
母のすすめで短大へ進学。肌の赤みを隠すメイクに夢中になる。
「周りから、厚化粧だとか白すぎると言われても、赤い顔を見せるよりは、ずっと心が楽だったんです。外見のコンプレックスが性格や体調、社会生活にも影響すると身をもって知りました」
21歳で内科医の夫と結婚し、2年後には長男を出産。育児に追われる中でも、冬になると厚化粧をする習慣は変わらなかった。
転機は30歳。母の死と夫の開業が重なり、過労で倒れてしまう。検査の結果、心臓に穴があいている「心房中隔欠損症(ASD)」と判明。緊急で受けた手術は無事成功し、血流が改善されて、長年悩んできた顔の赤みも消えた。
「真っ赤な顔から解放されて、今なら何か始められるかもしれない、と思いました。それまで、母の望んだ“良き妻、良き母”としての人生を歩んできたけれど、母の死をきっかけに、初めて“自分の人生を生きたい”と思ったのかもしれません」
素人主婦の“当たって砕けろ精神”

進む道に迷いはなかった。苦しかった時期に自分を支えてくれたメイクの力を信じ、本格的に学ぶ決意をする。
大阪の美容学校に入学し、10代の若者たちと机を並べた。しかしそこで教えられていたのは、女優やモデル向けの華やかなメイクばかり。
「きれいな人のためのメイクは世の中にあふれていました。でも、肌にトラブルを抱えた人が元気になれるメイクを学べる場所は、どこにもなかったんです。それなら自分で始めようと思いました」
地元の兵庫県芦屋市のカルチャーセンターに電話をかけ、無謀にも、メイク講座を開きたいと申し出た。
「前向きに生きる力になる“普段着メイク”を広めたい」
そう熱弁したが、「無名の主婦に講座を任せるのは難しい」とあっさり断られて落胆。しかし後に、「1日限定なら」とチャンスが舞い込む。
「私はがぜん張り切って、全力で準備をして臨みました」
講座は大好評で、翌期から正式に開講されることに。
「この“当たって砕けろ精神”で、ずっとやってきたんです。素人のくせにずうずうしいとか、断られたらみっともないなんて考えずに、やりたいことがあるならまず動く。それが私のやり方なんです」
講座には20代から70代まで、幅広い年代の女性が集まった。小さい目、低い鼻、ニキビ痕、アトピー、加齢によるシミやたるみなど、それぞれに悩みを抱えていた。かづきさんは顔立ちやライフスタイルに寄り添い、「その人らしさ」を大切にするメイクを提案した。
当時の受講生で現マネージャーの渡辺聡子さん(55)はこう振り返る。
「派手な神戸ファッションで、いつも明るくて元気なんです。講座の半分以上、世間話や冗談ばかりで、『先生、そろそろメイクを』って言われるほど(笑)。『思い切り笑いたくて来てる』という人もいましたね」
受講生たちの心をほぐし、前向きな気持ちを鼓舞する。そんな笑顔あふれる講座はたちまち評判となり、2年後には東京でも開講が決まる。
青山にスタジオを開設すると、次第に顔の傷痕に悩む人の受講も増え、「誰もが安心して学べる場所をつくりたい」と、地方からもアクセスしやすい四谷へ移転した。