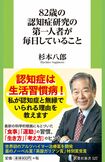現在、65歳以上の4分の1が認知症とその予備群とされる。誰もが発症しうる身近な病に不安を抱える人も多いが、実は予防することも可能だ。アルツハイマー治療薬「アリセプト」の開発者であり、82歳の今もなお第一線で認知症研究を続ける杉本八郎先生が実践する、認知症を遠ざける方法とは。
認知症は生活習慣病と同じ
「認知症は生活習慣を改めれば予防できます。生活習慣病と同じで、過剰に恐れる必要はありません」
そう説くのは、長年認知症の研究に携わり、82歳の現在も新薬の開発を続けている脳科学者の杉本八郎先生。
杉本先生は、世界初のアルツハイマー治療薬「アリセプト」の開発で、薬のノーベル賞といわれる「英国ガリアン賞」特別賞を受賞した認知症研究の第一人者だ。
認知症とは、記憶力や判断力など脳の機能が低下し、日常生活に支障をきたす状態のこと。約9割はアルツハイマー病、脳血管障害、レビー小体病の3つが原因とされる。これらの疾患がなぜ、生活習慣病と同じなのか。
「アルツハイマー型認知症は、アミロイドβというタンパク質が脳内にたまることで神経細胞が傷ついて、脳細胞の活性が落ちたり数が減ったりすることで発症します。血管性認知症は、脳梗塞や脳出血、くも膜下出血により脳の血管が詰まったり破れたりして、脳細胞に酸素が送られなくなって神経細胞が死んでしまうことで起こります。
そして、レビー小体型認知症は、α―シヌクレインというタンパク質が蓄積してできたレビー小体が、脳の神経細胞を壊すことで脳細胞が減少します」(杉本先生、以下同)
つまり認知症はすべて、脳の神経細胞の活性が落ちたり、数が減ってしまったりして、神経細胞同士の情報伝達がうまくいかなくなることで引き起こされるわけだ。
ということは、認知症を予防するには、その原因となるタンパク質を脳内にためないことと、脳血管を丈夫に保つことといえる。
「この脳内のタンパク質は誰にでもあるもので、脳細胞が元気であれば、分解されて排出されます。ただし、増えすぎたり、上手に排出されなくなるとタンパク質が凝集して脳内にゴミのようにたまっていきます。
完全に原因は解明されていませんが、運動不足や偏った食事などの生活習慣が、脳内にタンパク質が蓄積する原因の一環になっていることは間違いありません。脳血管障害も、血管ボロボロ、血液ドロドロが引き起こすものなので、まさに生活習慣の悪化が認知症の引き金になっているのです」