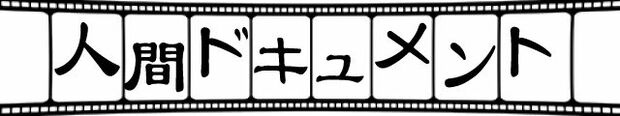「女子登攀クラブ」を結成
女性だけでヒマラヤに行こうと「女子登攀クラブ」を結成。1970年にアンナプルナ3峰の登頂に成功した後、'75年に15人の女性隊員でエベレスト登頂に挑んでいた。
全員ケガもなく予定どおり登山を続行したが、登頂できたのは田部井さんだけだ。
身長152センチと小柄で体力的にずば抜けていたわけでもない。自分が登頂できた理由を「運が良かったのと高所に強い体質だったから」と本人は説明する。
だが、次に日本人女性がエベレストに登頂したのは21年後だ。しかも、登頂した難波康子さんは、下山中に猛吹雪に遭い遭難死している。
田部井さん自身、その後、ほかの山でも2度、雪崩で死にかけた。何人もの仲間を山で亡くしてもいる。
そうした死を身近で感じた経験が、若かった田部井さんを徐々に鍛えていった。
「グチがすごく減ったと思います。あー、疲れた、もうやりたくないと思っても、子どもが言うことを聞かなくてイライラしても、生きているからそう感じられるんだから、文句を言っちゃいけない。そう考えるように変わってきましたね。もし、山でああいう経験をしていなかったら、私も文句ばかり言っているイヤなババアになっていたんだろうな、と。アハハハハ」
運動嫌いだった少女が「山」と出会って
それにしても、それほど大変な思いをしてまで、どうして山に登るのか。原点は小学4年のとき。担任教師に連れられて初めて登った那須の茶臼岳にあるという。
「茶色と白の岩がゴツゴツしていて硫黄の臭いがして、“何これ?”って、すごいビックリして。ああ、自分の知らないところって、まだいっぱいあるんじゃないかと思ったことが、原点ですね。
それまで、扁桃腺が腫れて高熱を出すことが多く、運動は嫌いだったんです。でも、山って、競争して登るわけじゃないから、体育が全然ダメな私でも、優秀な生徒と一緒に頂上に立てたという達成感がありました。はるか下に歩いてきた道が見えて、自分の足で登ってきたから、この風景が見られるんだという満足感もありましたね」
福島県三春町の生まれ。梅、桃、桜が一度に咲くから「三つの春の町」と名付けられた山間の町だ。緑の山しか知らなかった田部井さんにとって、初めて見た那須の火山は強烈だった。
旧姓は石橋。両親は印刷業を営み、田部井さんは兄2人、姉4人の7人きょうだいの末っ子だ。
地元の中学から県立田村高校に進学。兄に連れられ、県内の安達太良山、磐梯山などに登っていた田部井さんは、高校で山岳部に入ろうとしたが、「男子に限る」と門前払い。合唱部に入った。
当時は珍しかったオルガンが家にあり、姉妹の誰かが歌い始めると、たちまち二重唱、三重唱になり、歌うのも好きだった。

東京の大学に進んだ姉たちを追い、田部井さんも昭和女子大英米文学科に入学。女子寮で暮らし始めたが……。
「言葉が違うから、何度も聞き返されて傷ついたし。同じ部屋の人が湯のみを洗わないで何度も使ってるのが気になったり。あのころはすごく神経質で、それがどんどんどんどん高じて、ごはんも食べられなくなり、どんどんやせて、親が呼ばれました」
もともとは細やかな気性なのだろう。3か月休学して故郷で休養。大学に戻るとクラスメートがハイキングに誘ってくれた。
「奥多摩の御岳山に行ったら、同じ東京でも田舎じゃないですか(笑)。リヤカー引いてるおばちゃんはいるし。何だ、三春と変わらないなと」
コンプレックスが吹き飛び、忘れかけていた山への情熱が再燃した。帰りに渋谷の書店に寄り『東京周辺の山々』というガイド本を購入。自分で計画を立てて友人たちを誘っては山を歩いた。
大学を卒業して日本物理学会に就職。論文の編集をしながら週末は山に行った。山岳雑誌で見た雪山に憧れ、社会人山岳会に入会。本格的に冬山や岩登りを始めると、すぐのめり込み、それが後のヒマラヤ登山につながる。