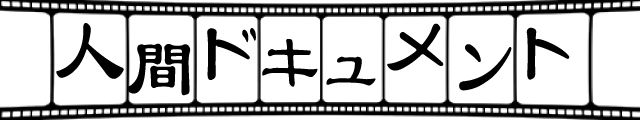山中温泉で知った商売の面白さ
道場さんが石川県の山中温泉で生を享けたのは1931年のこと。両親が40歳のときにできた6人兄姉の末っ子で、上には2人の兄と3人の姉。6人兄姉の3番目の男子だから六三郎というわけだ。
「うちは茶道具の棗なんかに漆をつける家業でね。兄貴と2人で京都や大阪の取引先に商品を届けに行ったものです。終戦後は本当に食べるものがなくてね。それでも石川県はお米があったから、1升90円の米を棗に詰めて持って行けば、120円ぐらいで売れたのかな。兄貴は恥ずかしがっていたけど、僕は“お米を持ってきましたけどいりませんか?”“じゃあ、もらおうか”ってなもんでね。そうすると、汽車賃ぐらいは賄えたんです」
15、16歳で商売の面白さに目覚めると、17歳のとき地元の鮮魚店で働き始めた。そこで初めて包丁を握り、仕出しを旅館に届ける際は時に皿洗いや盛りつけを手伝った。
忙しい日々だったが、気持ちよく挨拶をするというので、周りから可愛がられた。
「あのころは街中に料理屋はなくて、ほとんど旅館でした。そこに納める仕出し料理や各家庭の祝い事の膳を拵えるのが主な仕事で、結構忙しかったんですよ。手取り足取り教えてもらえる時代じゃなかったから、鯛の串打ちやなんかは見て覚えてね。余った魚のアラを持って帰って、鰤大根にしたり、鯛の潮汁にしたり。うちの親父は食べることが好きで、喜んでくれることがとにかくうれしかった」
両親は熱心な浄土真宗の信者。食事は家族みんなでいただき、その際に父親が親鸞聖人や蓮如の話をしてくれるのが常だった。また、兄弟同士が同じ職に就くと、取引先の取り合いなどで仲が悪くなるから、同じ道に進まないようにというのも父の教えだ。
「だから、いちばん上の兄が家業を継いで、2番目が建具屋になって、僕は料理人になった。だけど、魚屋で働き始めたころは特に料理人になろうとは思っていなかったんです。一方で、料理人なら今後食べるのに困らないだろうという思いもあって、そこに2、3年はいたかな」
父の教えもあってか、家族仲のよさは第三者の目にもはっきり映った。現在『銀座ろくさん亭』で総料理長を務める田中由示さん(58)は語る。
「初めておやっさんと出会ったのは、『ろくさん亭』の面接のとき。今でも鮮明に覚えています。鋭い眼光というか、とにかく目に惹きつけられて、その場で“この人についていこう”と思いました。
縁を結んでいただいて、山中温泉にあるホテルで働いていた時期があるのですが、おやっさんのご兄姉が本当によくしてくださって。特にお姉さん方は、おやっさんが子どものころの話なんかもしてくださって、可愛くて仕方がないというのがありありと見えるようでした。聞いていて、私も幸せでしたね」
世間では1948年に発表された笠置シヅ子の『東京ブギウギ』が大ヒット。戦後の開放的な気分は、山中温泉にも伝わっていた。
どうせ修業に出るなら、歌にもある東京にしようと軽く考えた道場少年だったが、当時、石川県出身の料理人が和食の修業をするといえば京都や大阪がほとんど。
「東京に出るのは大学に行くからなんてのがちょっといたぐらい。当時は汽車も常に満員だから切符を買うのもひと苦労でね。朝早く起きて、まだ寒いなかマントを羽織った母が、切符を買うため駅に並んでくれたんだよ。
あの光景は、いまだに覚えてるね」
1950年5月、道場さんは東京行きの汽車に乗った。
花の都・大東京でカルチャーショック
道場さんの東京生活が始まった。東京全体が舟運の街だった時代だ。銀座8丁目の少し先、現在の首都高速の下を汐留川が流れ、その川を両国まで行く船がポンポンポンと音を立てて運航していた。もちろん、今のような高層ビルは影も形もない。その日々は、驚きの連続だった。
「まず驚いたのはガスがあること。山中では薪と炭の生活だったから、ボッと火がつくのにびっくりしてね。しかも、山中で魚といえば野締めしか入ってこなかったから、活けのフッコ(成長魚のスズキが35センチサイズのときの呼び名)がビビビッとはねるのを見て、またびっくり」
最初の修業先は銀座『くろかべ』。当時、国民的人気を誇った雑誌『ロマンス』を出版していた会社の重役が開いた店だったこともあり、多くの文化人やスターが訪れた。
「『二十四の瞳』の高峰秀子はお母さんと一緒に来てたね。『ひめゆりの塔』の津島恵子に高峰三枝子、龍崎一郎、僕は高田稔って人に可愛がられて、靴や白い背広をもらったんだけど、向こうは身体が大きいからサイズが合わない。だから、靴に中敷きを入れて履いていたんだよ」
上京してから独立するまでの10年間、道場さんは複数の店で修業を重ねている。そのうちのひとつが、現在の新神戸駅の近くにあったホテル。
ある日、こんなことがあった。薔薇の入れ墨を入れた料理長が、「全員、同じ時間に調理場に入る」と言い出したのだ。その日は50人の宴会が入っていて、道場さんは3匹付けのアマゴ(鮭の仲間の淡水魚)を50人分串打ちする必要があった。早く調理場に入って準備をしたいと気持ちは急くのに、それが叶わない。
「どうしてそんなことを言うんだろうと思ったよ。どうも、“あいつを目立たせたくない”という嫉妬心だったみたいだね。ギリギリの時間に調理場に入って、だーっと鯛をおろして、焼き物を作って、串打ちをして、必死だった。
制限内に料理を作ることは『料理の鉄人』のときにも鍛えられたけど、人間って追いつめられると何かひとつ抜け出すことができるんだね。いまだに調理場に入ると、キレイに、早くと思うのはそのときのことがあったから。今では、その料理長がいたから今の僕がいると思ってる。感謝だね」