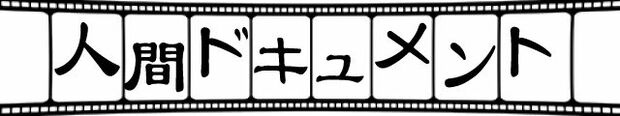家族や職場の人たちに支えられたのだが─
しかしそれからはどん底だった。どうしてもインターネットで「認知症」を検索してしまう。すると「徘徊」「寝たきりになる」「何もかもわからなくなる」「家族に迷惑をかける」「寿命は数年」といった怖くなる情報ばかりが目に飛び込んできた。
たまらず涙を流しながら「忘れたくないリスト」を作った。まず書いたのは、わが子の名前と誕生日だった。
もし仕事ができなくなったら女手ひとつで子どもを育てられるのか。不安は増すばかりだった。その気持ちを察して、数か月後に大学入学を控える蓮さんが言ってきた。
「大学に行くのやめるき、おかあと一緒におる」
それに対ししのぶさんは、
「いや、蓮の人生やき。大学は行きたくて志願しちゅうき、行きや」
しかし先々のことを考えれば考えるほど不安になる。うつ症状も出てきて、夜、生命保険の証券を見ては、自殺でも保険金が下りるのかを確認することがあった。
そんな苦しい状況でありながらも仕事は続けた。直属の上司の協力もあったからだ。認知症になったことを報告したとき上司はこう言った。
「俺は認知症のことは知らんけど、仕事は続けてほしい。カバーするから何でも言ってくれたらいい」
仕事には厳しく、普段は怖いが、気持ちに熱いものがある上司はこう続けた。
「(認知症になったからと)色眼鏡で見られとうないき、ほかの部署には言わんといてほしい。もしヘンなことを言われたら俺が我慢できんから」
しのぶさんを必死で守ろうとしてくれる気持ちがうれしかった。同僚の中には、認知症になったことを自分のことのように受け止め、涙を流す女性もいた。
ありがたいことに周囲は快くサポートをしてくれた。
上司はまず、しのぶさんが担当していた約200ある得意先をほかの社員に振り替えた。さらに電話をかける予定を聞き、かけたかどうかを確認する。仕事を終えて日報を書いているときに、上司が仕事の進捗状況を確認する。
ほかの同僚数人も、例えば「今日持っていった充電器、売れた?」などと確認してくれた。捜しものをしている様子を察したら、「何、捜している?」と声をかけてくれる。とはいえ、完璧なフォローは難しい。顧客への訪問アポを忘れ、得意先から契約を解除するとクレームが来たことがあった。それでも仕事を続けさせてくれた。
「みんなさりげないサポートで、助けてくれました。認知症サポーター養成講座を受けたこともない、それほど認知症について知っているわけでもない人たちです。でも私の周りには一人も悪い人がいない。そんなお花畑があるのかと疑われるかもしれんけど」
子どもの学校の担任もさりげないサポートをしてくれた。例えば中学校から来る便り。さほど長い文章が書かれているわけではないのに、文意が頭に入ってこなくなったのだ。
「改行がない文章を読むのがしんどくなったんです。このころはうつ症状がひどくて、不安とか怒り、焦りが強かったので、毎日、頭がパニック状態ということもあったのだと思います」
担任に認知症であることを打ち明けた。するとその先生、「明日はお弁当の日です」とか「三者面談の日はどの日がいいですか?」と、重要なメッセージだけを選んで、ショートメールで送ってくれるようになった。
「これはすごく助かりました。先生もたぶん認知症の理解はない方です。でも認知症を理解するというよりも、私や家族が置かれている状況を理解しようとしてくれた。“認知症の私”ではなく、困っている私に“人として”対応してくれた。もし“認知症の人”扱いで“大丈夫ですか?”だけ言うような先生だったら、傷ついていたと思います」
家では、大阪の大学に行った蓮さんに代わり、修矢さんが母親をフォローした。
炊事をすると火が危ないけれど、炊事全般を奪ってしまうと母親は何もできなくなると修矢さんは考えた。そこで火は消しているか、冷蔵庫のドアを閉めたか、風呂の栓をしないまま湯をためていないかなどを、あるときはテレビを見ながら、また、トイレに行くふりをして確認していた。
認知症の診断後もしばらくは仕事を続けられた。が、職場で無理に明るく振る舞う分、家ではその反動でドッと疲れが出て苦しくなった。「どうして私ばっかりこんな思いをせないかんが」と泣いたこともあった。診断から数か月すると、出社できない日が増えていく。蓮さんに弟・修矢さんから電話があった。
「コンビニで、支払いを済ませていない商品を店内で食べようとしたり、虫を見ては、“私はこの虫のようにつぶされるがや”とつぶやいたりしていると。当時はうつ症状も強かったので布団から出てこない日が多くなっていたんですが、その電話を受けてすぐに高知に帰りました」