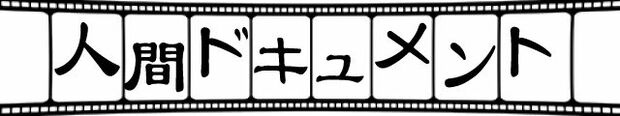「笑顔で生きる」この言葉に助けられて
そんな状態がしばらく続いたあと、しのぶさんはネットの記事で、一人の若年性認知症の男性を知ることになる。宮城県に住む丹野智文さんである。自動車のトップセールスマンだったが、39歳でアルツハイマー型認知症と診断。絶望するが、職場の理解を得て仕事を続け、認知症本人たちとの出会いや、自身の工夫により日常生活を送り、著書を出版したり、講演活動をしたりしていた。
しのぶさんはSNSで丹野さんにメッセージを送った。
《今の私は嫌いです》
《なんとかしたいです》
すると著書を送ってくれ、すぐに読んだ。自分と同じような失敗に笑え、「笑顔で生きる」という丹野さんの姿勢に勇気づけられ、自分も笑顔になりたいと思った。
もうひとつ役立ったのは、スマホの活用法だ。丹野さんの方法を参考に、冷蔵庫の中の写真を撮れば、買うべきものがわかった。
客先でスマホの操作手順や設定画面を説明するときに備えて、説明画面を写真に撮っておくこともあった。記憶代わりにほぼ毎日撮り続け、スマホに残る写真枚数だけで、今年6月段階で3万4000枚を超えていた。
グーグルカレンダーも活用した。日程を書きアラーム設定しておけば、予定を忘れることはない。
乗り換え案内とマップ機能を使えば、知らない場所でも、目的地さえ決めておけば進むべき方向を示してくれて、迷わずに移動できた。
「スマホは自分の脳の一部ですね。自分の代わりに記憶してくれる機械。自分が足りない部分をうまくサポートしてくれる存在でもある。これを使いこなすことで、仕事も生活もしやすくなりました」
ただ、襲ってくる「孤独感」はスマホでは解決しなかった。親思いの子どもたちがいるのになぜかと思うが……。
「家でいるとね、子どもたちは学校に行き、バイトに行き、友達と遊びに行くから、家で一人になるんです。その時間がすごい孤独やった。仲のいい家族がおるから大丈夫という問題でもないんです」
そのころからしのぶさんは、自身が感じる孤独感を何とかできないかと考えるようになった。そして、「認知症であることを隠さずに生きる」のが最善だと思うようになる。助けてほしいとき「助けて」と言えないのも不安だった。しかし認知症であることをオープンにしたら、会社に迷惑がかかる。ここが潮時と'21年6月、退職を決意した。
学校に通う子どもがいる中で、仕事を辞めるのは勇気がいるが、前年3月に母校の同級生と再婚したことが決断をしやすくした。