
猛暑となった今年の夏は、クエン酸配合の商品が好調な売れ行きを見せた。中でもクエン酸飲料の需要は右肩上がりで、ここ4年で約5倍に増えているともいう。
「疲労感軽減などをうたう機能性表示食品も増えたため、コロナ禍以降、免疫力を高めたい人や、後遺症で倦怠感が残った人など、健康志向の方に刺さったのだと思います」
そう分析するのはフードアナリストの吉岡杏奈さん。実は、日本人ははるか昔から経験的にクエン酸の効果を体感し、生活に取り入れてきた。
クエン酸が栄養変換の“着火剤”に
「クエン酸を含む食品のひとつに梅がありますが、奈良時代の終わりに大陸から伝わると、解熱や鎮痛などの薬として用いたと書物にあるくらいです。その後、梅干しや梅酒などに加工され、庶民にも広がっていきますが、令和のいま、改めてクエン酸食品が見直されていると実感しています」(吉岡さん)
ここ数年、“クエン酸配合”と表示する食品も増えたが、クエン酸とはそもそもどんな働きがあるのだろうか。
「クエン酸は、梅干しや、レモンなどの柑橘類など、果物系に多く含まれる有機酸の一種で、クエン酸回路というエネルギー回路の主役になるものです」
そう教えてくれたのは、総合診療医の伊藤大介先生だ。
「簡単に言うと、摂取した炭水化物や脂肪、タンパク質などの栄養をエネルギーとして変換する“着火剤”の働きを持つ栄養素です」(伊藤先生、以下同)
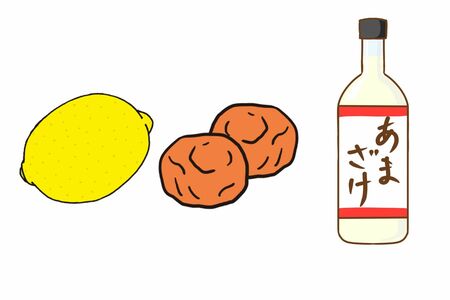
いくら栄養を取り込んでも、クエン酸が不足すれば効率よくエネルギーを作り出せず、疲れを感じやすくなる。加えて、もうひとつ大事な役割が「キレート作用」だ。
「鉄分やカルシウムと一緒にとると、クエン酸がそれらミネラルをガッチリつかんで身体に吸収されやすい形に変換してくれるのです。ミネラルを無駄なく摂取するという意味でも重要な役割を持っています」
実際に疲労をやわらげる効果はあるのだろうか。
「小規模な研究ではありますが、1日2・7gのクエン酸を8日間とったグループととらないグループで、運動後の疲労回復効果に差が認められたというデータも。効果は期待できると思います」


















