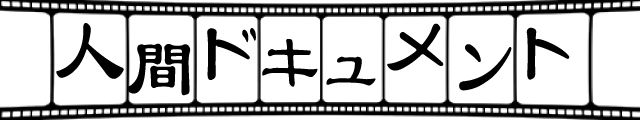東京の演劇界に失望
「考えさせられる芝居がなくなっていったんですよ」
’80〜’90年代にかけ東京を中心に巻き起こった“小劇場ブーム”により、劇場の数、演劇に関わる人口こそ増えたが、次第に演劇自体は娯楽志向を強めることに。これに強い違和感を抱くようになったのだ。
「Imagination(想像)とCreation(創造)を作動させて、作品と自分とのあいだを往復し、自分だけの物語を作るところに、知的スリルや鑑賞の面白さはあるわけですよ。だけど、観客の“目”の欲望に従順な作品を作りすぎた結果、考えさせられる芝居が減っていったんです」
娯楽志向を強めた東京の演劇界の荒廃ぶりに失望を隠せなかった。そんな衛さんのなかに、ある決意が芽生える。
「地方から東京を包囲してやろう」
さっそく思い切った行動に出る。テレビやラジオをすべて降板、12本あった雑誌連載も1本に減らしたのだ。
「編集者とケンカしながら無理やりやめました(笑)。収入は10分の1以下になりましたよ。確定申告に行くと、税務署の職員から気の毒がられました(笑)」
40歳を過ぎてから10数年にわたり、およそ400もの劇場ホールを来訪。そして、ひとりの少女に出会い、衝撃を受ける─。
’90年代初め、出会いは長崎で待っていた。「あゆみちゃん」という名の小学4年生だったその少女は、知覚過敏と自閉症スペクトラムのため学校になじめずにいた。だが、それぞれの子どもの障がいに合わせた芝居を作る『のこのこ劇団』に通い、前向きに生きる希望を見いだしていたのだ。
「僕は上演される舞台を見て評価をするのが仕事だったんだけど、それは演劇の機能のほんの一部分でしかなかったことに気づいたんです」
そこには、いままで自身が携わってきた演劇とは異なる、もうひとつの“演劇”の形があった。
「芝居としては面白くないし、芸術的価値や評価はゼロに近い。だけど、社会的価値にあふれている芝居でした。そこにこそ光を当てなければ、演劇人としては貧しいんじゃないかと思ったんです」
それまでの自分は「演劇愛好者だった」と、衛さんは自らを評する。同時にそれは、明確な課題が生まれた瞬間でもあった。
「一部の愛好家による“芸術の殿堂”ではなく、すべての人間にとって心の拠(よ)りどころとなる市民劇場を作りたいと思いました。誰しもが自らの家と呼べるような、社会的価値のある劇場、“人間の家”をね」
実際、’95年の阪神・淡路大震災の時には、仮設住宅で孤立してしまった高齢者や障がい者がコミュニケーションをとる機会を持てるようにワークショップを開催。社会的価値を模索していった。
そして、北海道・札幌駅前の劇場プロジェクトに携わることに。ついに夢が実現すると意気込んだが、知事の交代などにより、計画は志半ばで頓挫してしまう。大きな挫折だった。
「もうこれで一生、劇場に関わることはないだろうなと思いました」
自身の手で実現することは、もはや難しいかもしれない─。
’97年からは大学で教鞭を執り、次の世代にバトンを託そうと一線を退いた。