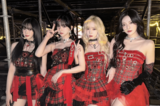唯一のつまずきがあった
順調に進む中で、唯一あったつまずきを明かしてくれた。
「あの~、留年してます。6年生のとき、1年間だけ」
6年生のとき、伊藤さんは医師国家試験対策委員長を引き受けていた。それは同級生たちのために予備校や模擬試験の計画やアレンジをする役だった。しかし、この任務に熱心に取り組むあまり、自分の勉強時間を確保できなくなり、留年してしまったというのだ。
「人生、ままならないなと思いました。同級生のために自分の時間を使ったら、自分は留年という、お人よしな感じですよね。
自分のことだけ考えてやれば、そうはならなかったと思うので。でもね、同級生には感謝されたし、留年で1学年下の子たちとも親しくなれて、友達が増えたのはよかったかなと思います(笑)」
“誰ひとり置き去りにしない”の精神で
帝京大学医学部卒業後、東京大学病院の小児科の医局に入局した。研修医のとき、難病で次々と亡くなっていく幼い子どもたちを看取るたびにつらい思いに苛まれ、小児科入局を悩んだが、先輩医師から「今後の医療の改善のために力を尽くすことが自分たちの使命だ」と諭されて、入局を決意。2013年4月には、東大大学院の公衆衛生学コースに進学する。
「公衆衛生学というのは、地球に住むすべての人たちの健康を考えるという学問なんです。“Leave No One Behind(誰ひとり置き去りにしない)”という精神に基づいているんですね。データや根拠を持って、みんなが健康に生活するための条件を提示するという手法を学びました」
前出の大学院教授の元秘書は、伊藤さんは院生のころからほかの医師とは異なる独自のスタイルを持っていたと話す。
「伊藤先生は誰に対しても物怖じしないんですよ。メールの書き出しにしても、“こんにちは”から始まって、“お世話になっております”みたいな堅苦しいのはないんです。教授にも気負ったりしないで話しかけられるので、教授もそれを嫌とは思われずに、接していらっしゃるようにお見受けしました」
研究室の特任研究員になってからは、セミナーの企画も積極的に提案していたという。脳障害児の機能回復に関するセミナーを開催したときは、アメリカから人間能力開発研究所の所長を招聘し、同時通訳に入るなどして、すべてを取り仕切っていたそうだ。
「雑務もサクサクと効率よく回していらっしゃいましたね。私も傍らでお手伝いをさせていただいたんですが、あ~もうスーパーウーマンだなって! 通訳が必要なイベントなどでは、とにかく伊藤先生にお願いするという感じでした。やはり教授の信頼が厚かったからだと思います」
同じ大学院で学び、現在は赤坂ファミリークリニックに勤務する小児科医で、公衆衛生学博士の山本恵美子さん(41)も伊藤さんのユニークな診療方法について語る。
「患者さんの、病名のつかない、あるいはつきづらい不調に対して、病気として診断できないと切り捨てずに、何らかの対策ができないか、いつも考えていらっしゃるんですよ。いわゆる医学部でメインに学ぶ西洋医学を超えて、健康関連の幅広い知見を持たれているので、栄養学やサプリメント、東洋医学的な漢方薬を使ったり、認知行動療法を用いたりして、常に患者さん目線でアドバイスされるんですね」
そもそも山本さんが公衆衛生の道へ進んだのは、8年前、知人に紹介された伊藤さんの助言があったからなのだとか。
「迷う前に挑戦してみればいい! 楽しいですよ! と背中を押してくださったんです。その言葉どおりになって感謝しています。現在、私も1歳児の子育て中で、自分の研究に時間を割けないことに不安を感じることもあるんですが、40代で医師になられた明子先生が、今もどんどんやりたいことを臆せずやっていらっしゃるので、いつまでも挑戦し続けることは可能なんだと、とても励みになっています」