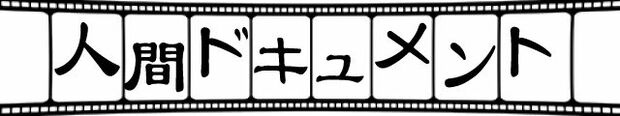梅雨明けしたばかりの空を、入道雲が立ち上っていく。国道134号線。長者ヶ崎のカーブを左にハンドルを切ると、大きく視界が開ける。風を孕んで帆走するヨット。早くも夏の訪れを告げるダブルレインボーが真っ青な空にかかっている。
『夏のクラクション』

稲垣潤一の新曲のタイトルはすでに決まっていた。ところが歌詞を書くために必要なストーリーがなかなか思い浮かばない。葉山から西海岸通りへ、佐島マリーナに向かう道行きを愛車の白いクーペで駆け抜ける。
そんなとき、
「すべての海沿いのカーブにはドラマが潜んでいる」
ふと、そんなフレーズが売野雅勇の脳裏に浮かんだ。
白いクーペ、まぼろしの天使のシンボルとして描かれる女性、無垢なる夏の終わり、遠ざかるクラクションの響きが、ガラス窓に遮られて聴こえない世界が始まる……。
避暑地の別れを切なく描いたラブストーリーである。
この歌詞を見た筒美京平は、
「なんて音楽的な詞なんだって思った。音楽が聴こえてくるから、そのままメロディーを書けばよかった。だから、すぐにメロディーをつけられたよ」
歌謡界のレジェンドに褒めてもらったことがうれしくて、雅勇はそれを昨日のことのように覚えている。
今再び、世界的なブームを呼び起こしている「シティ・ポップ(city pop)」。
1970年代から1980年代にかけて日本で流行したニューミュージックの中でも、洋楽志向の都会的に洗練されたメロディーや歌詞を持つ音楽。その中でもイタリアンジゴロを思わせるおしゃれなファッションに身を包んだ雅勇は、一世を風靡した。
「スタイリッシュで時代を背負った売野さんの登場は衝撃的でした。お互いに地方都市の出身だけに、アメリカや東京への憧れが強かったね。そのエネルギーがシティ・ポップを生んだんじゃないかな」
そう語るのは、雅勇と共にシティ・ポップ界を牽引した作曲家の林哲司である。
2人の共作で忘れられないのが、稲垣潤一の『P.S.抱きしめたい』。カルロス・トシキ&オメガトライブの『be yourself』。そして杉山清貴の『真夏のイノセンス』雅勇の詞と林の曲が絡み合い、今もファンから神曲として語り継がれている。さらにもう1曲挙げるなら、稲垣潤一の『思い出のビーチクラブ』だと話すのが、売野雅勇作詞活動35周年記念CD―BOX『Masterpieces~PURE GOLD POPS~』などでライナーノーツを執筆したライター兼編集の速水健朗。この曲の“聖地巡礼”に行った日のことを、今も思い返すという。
「油壺の閉鎖されたビーチクラブは、まさに兵どもが夢の跡。売野さんが愛するシティ・ポップの原点を見る思いがして、それから何度も足を運んでいます」
しかし雅勇が手がけた歌は、決して「シティ・ポップ」だけではない。
作詞家デビューのきっかけとなった、シャネルズの『星くずのダンス・ホール』や後のラッツ&スター『め組のひと』。『少女A』『1/2の神話』『禁区』といった中森明菜の“ツッパリ三部作”も忘れることはできない。さらに、自ら手紙を書き、
「書かせてほしい」と訴えた矢沢永吉の『SOMEBODY'S NIGHT』『PURE GOLD』。そして、坂本龍一の楽曲まで手がけた作品の守備範囲の広さは超人的といってもいい。
例えてみれば、アップタウンの華やかな“酒とバラの日々”から、ダウンタウンに生きる人たちの生きざままで見事に描き切ってしまうマエストロといえるだろう。
昼下がりのパレスホテル東京にやってきたマエストロは、穏やかな笑みを浮かべ、取材に訪れた筆者においしいコーヒーを振る舞ってくれた。
クラスメートを従えるガキ大将

1951年2月22日。雅勇は「源氏の棟梁」と呼ばれた足利氏の発祥の地・栃木県足利市で生まれた。驚くなかれ、売野雅勇はペンネームではない。祖父が命名、父が寺の住職に相談して漢字を選んでいる。身体こそ大きくなかったが小学3年生のころから、雅勇はクラスメートを従えるガキ大将だった。
「通っている小学校で両親が教えていたこともあり、成績の良かった私は先生からの覚えもめでたく、天狗になっていたのかもしれません。ある日、身体のデカい上級生から“おまえ威張ってんだってな”“偉そうにしてると俺たちも黙っちゃいないぞ”と胸ぐらをつかまれたこともありました。そのときは怖かったな」
放課後になるとそんなことも忘れて、雅勇はクラスの男子を引き連れ、街の高島屋やほかの小学校へ自転車で繰り出した。彼の居場所は、いつも友達の輪の中心。言ってみれば放課後のエンターテイナー。しかし小学5年生のとき。そんな雅勇に心境の変化が訪れる。
「クラスの男子生徒を毎日怒鳴り散らして、子分のように扱ってきました。きっと中学・高校に行ったら、僕から受けた屈辱的な思いを忘れられないだろうな」

そんな思いに駆られたのは、学芸会で演じる芝居の役どころがきっかけだった。雅勇が演じるのは、王様のワシに媚びへつらい弱い鳥たちには威張り散らす、嫌われ者のハゲタカだった。
「これはまるで、俺のことじゃないか」
まさにブーメラン。因果応報というべきか。ガキ大将の雅勇が陰でいつも偉そうにしているのを、先生は気がついていて、ハゲタカ役を雅勇に「当て書き」したに違いない。
そう気がついて、
「今から考えても泣きたくなるくらい恥ずかしくなった」
ところがインフルエンザが流行って学芸会は運のいいことに中止。悪夢は去った。しかしこのときのショックが忘れられなかった。
「その反動もあってか、中学に進学するとバスケ部や陸上部に入って、あり余るエネルギーを発散。高校時代も練習の厳しいハンドボール部に入部して汗を流しました」
いつしか明るくひょうきんな雅勇は、クラスや部活の人気者になっていた。
しかしその反面、部活のない日は地元の悪ガキたちともつるんでいた。
「作詞家の出発点がシャネルズだから、京浜工業地帯のティーン・エイジャーの青春。土曜の夜だけが俺たちの生きがいみたいな世界が僕にはすごく合っている。
そういう人たちの生き方に真実を感じる感性が、生まれつき備わっていたんじゃないかな」
生まれ育った足利市もまた京浜工業地帯と同じ工場街。こうした日々こそ、作詞家・売野雅勇のもうひとつの原点なのかもしれない。