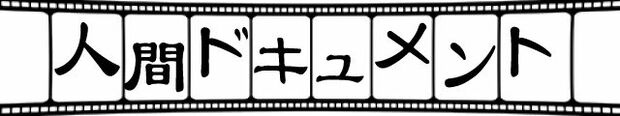暴力のサバイバーであり、摂食障害や引きこもりも経験したエッセイストの石田月美さん(42)は、主治医の助言をきっかけに婚活し、結婚した。そして出産し、現在2人の子どもを育てている。彼女の家には近所の子どもたちが遊びに来る。主婦として忙しい一方で、自身の生きづらさの話を中心に執筆活動をしている。
引きこもり時代から一転して婚活をし、結婚するまでの話として、デビュー作『ウツ婚!!─死にたい私が生き延びるための婚活』(晶文社)を執筆した。「ビョーキ」のまま社会とつながることが、「ビョーキ」からの回復に有効として、「ウツ婚!!」というセミナーも立ち上げ、精神科病院の施設で講座を開いた。
自伝的エッセイ『まだ、うまく眠れない』で綴った滑稽さ

自伝的エッセイ『まだ、うまく眠れない』(文藝春秋)でもシリアスな状況を明かしながらも自身の滑稽さも綴った。生きづらさの回復と恋愛や結婚、家族という物語を結びつけるのは、福祉や医療の支援の現場ではなかなか肯定されない話だ。ただ、石田さんは作品で挑戦をしている。
「私が婚活セミナーをしていたときも、さまざまなシンポジウムや学会に行きましたが、支援者たちと話すと、鼻で笑われました。『変なことやっていますね』って。婚活や恋愛って、(生きづらさが)ひどくなるイメージがあって。でもセミナーに来てくれる彼女たちは私の話を求めてくれたんです」
精神科に行くと、こころの話ばかりになるが、生活の立て直しが先ではないかとも感じた。
「精神科の患者仲間と話していると、“暑くても生活保護なのでエアコンをつけちゃダメ”とか言う人が多いんです。布団乾燥機を持っているのに、“(自分には)使う資格がない”と思ってしまうんですね。そういう話を聞いていると、日常生活を見直すことが、こころ(の回復)につながるんじゃないかと思ったんです」
そうした思いもあって、恋愛や結婚を回復の手段として考えたものが、『好きで一緒になったから』(晶文社)にまとめられた。福祉の現場では、恋愛や結婚を回復の手段として位置づけるのはタブーな面がある。そんなテーマの本を、これまでに『家のない少女たち』などを書き、高次脳機能障害があるライターの鈴木大介さんと共に出した。鈴木さんは石田さんのことを、
「これまで取材してきた人と時期が違いますが、“取材してきた子たち”の延長線上にいる人だなと思いました。それに、僕自身が高次脳機能障害の当事者で、妻も障害があります。だからか、石田さんには学ぶことが多いんです。(困難な道を)先に行った人という意味で、『月美先輩』と呼ぶことがあります」
アルコール依存症の父。暴力を必死に止める母
石田さんはフランスで生まれた。両親は現在、共に翻訳業だが、石田さんが幼いころの父は、ドーバー海峡のトンネルまで行き、通訳をして出稼ぎをした。小学校に入学する前に日本に越してきたという。
「多忙だったこともあり、父はほとんど家にいませんでした。東京に住むようになっても父は海外で単身赴任でした。両親2人で翻訳会社を営んでいて、母は東京の事務所で、父から上がってきた通訳の原稿を手直しして校正をかけるということをしていました。
小さいころ、父が日本に戻ってくると、トランクの中にたくさんのお土産が入っていたのを覚えています。ただ、逆に、父との毎日の思い出はないですね」
父親はずっとお酒を飲んでいる人だった。
「お土産と父の帰りはうれしかったです。でも落ち着いた後で飲酒が始まります。それはつらいですよね。暴力もありますから。殴られますよ、普通に。私、前歯のほとんどが入れ歯なんです。殴られてうずくまると蹴られます。『巨人の星』を読んでいましたが、まさに、ちゃぶ台がひっくり返る家でした。広い家ではなかったので、テレビの画面が割れるんですよ。
今考えれば、父はアルコール依存症だったんですよね。暴力を母は必死に止めていたという印象があります。それが当たり前でした。教育面でもしつけが厳しい。覚えているのは5歳のとき、それまでフランスでの生活だったんですが、お箸が持てないと、朝まで指導されるということもありました」
また、父は幼いころから将来について訓示をしてきた。
「『頭の中に不動産を持て。それがおまえたちの身を助ける』と言われていました。簡単に言うと、勉強が大事だということでした。父はユダヤ人を尊敬していて、自分がフランス圏ではマイノリティーで、そのなかを転々としていったのです。だから『おまえたちもいつそうなるかわからないから、きちんと勉強をしておけ』と言っていました」
そんな父からの言葉を苦に思わずに聞いていた。
「私は『へえ』と思っていました。人間関係は苦手ですが、勉強は得意でしたから。だって、私にとって勉強はすごく楽なんです。ドリルは何も言わないですから。『おかしくない?』とか『もっと好きでいてよ』とか言わないじゃないですか(笑)。それに勉強は練習法が決まっている。どうすればいいのかは明確です。しかも、努力が報われます。でも、人間関係は何を求められているのかわからない」
母親とはずっと一緒だった。厳しい父と反対に優しく、4歳上の姉と2歳下の弟と、3人の子どもを育てるパワフルママだったという。
「母は子どもが大好きでしたが、ワンオペで子育てをしていたので、ものすごく忙しかったんです。よく料理を作っていました。覚えているのは餃子です。3人きょうだいで、1人30個くらい食べていました。
家にあるものでパッと作るような、時短料理が得意でした。(子どもの身体を)大きくするのが好きなんです。大きい人が好きみたいで」
家族の思い出というと、'90年代に放送されていた、フジテレビ系のクイズ番組『平成教育委員会』だ。
「テレビのチャンネルを選ぶ権利は父親にあったんです。ただ、番組が始まると、親から裏が白色のチラシが配られました。みんなで解いて、チラシの裏に解答を書いたんです。めちゃくちゃ楽しかったです。きょうだい3人で解いていました。
それを見ていた父はお酒を飲み、母はつまみを出していました。解ければ父親に褒められました。当時の父はお酒が入らないと一言も話しませんでした」