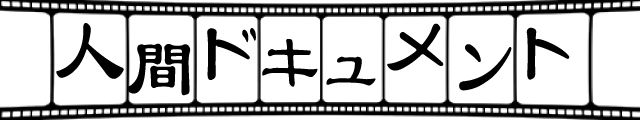いじめで知った“心の痛み”
1975年、沖縄県那覇市で生まれた。父親は土地開発の会社を経営し、母親は専業主婦。裕福な家庭でひとり娘として育った。
「母は、私を産む前に流産と死産を経験していて。やっと授かった子どもなので、父は超過保護で、母はかなり教育熱心でしたね」
早くも3歳で医師を志し、小学生時代は塾やお稽古ごとをいくつも掛け持ち。成績は常にトップクラスで、小学5年生のときには、東京女子医科大学に行くと決めていた。
「たまたま書店で手にした本に、沖縄出身の女の子がアメリカで肝臓移植手術を受けて生還した記事が載っていて。当時の日本では脳死が認められていないから、技術はあっても手術ができないという東京女子医大の医師のコメントを読んで、心を打たれたんです。よし! 将来はこの大学に入って、肝臓移植ができる医師になろうと」
もともと、こうと決めたら突き進むタイプ。
いい教育を受けさせたい両親の希望とも重なり、中学からは母親と上京。名門私立の女子中高一貫校に入学した。
ところが、期待に胸を膨らませていたものの、待っていたのはいじめだった。
「音読の時間に、沖縄の方言を笑われたことはあったけど、なぜターゲットにされたのかは今もわかりません。何かがみんなの気に障っちゃう子だったんでしょうね」
今でこそ笑って振り返るが、「トイレの水を飲め」と首根っこを押さえつけられたこともあった。
「さすがに抵抗して、トイレの水は飲まなかったけど、そういう嫌がらせをされるほうがマシだと思えるほど、本当にきつかったのは無視されることでした。じきに、自分は人に好かれることが難しい人間だと思うようになっていましたね」
教師はまったく気づかなかった。母親にも心配をかけたくないから言わなかった。
「しょうがない。しょうがない」、自分に言い聞かせながら、淡々と学校に通った。
投げやりにならず、勉強もコツコツと続けた。
「医者になる目標は持ち続けていたから。別に医学部に合格していじめっ子たちを見返そうって思いもなかったですね。当時、バブルがはじけて父の事業が苦しくなっていたので、負担をかけないよう、できれば国立に行きたいと考えていたくらいです」
結局、初志貫徹とばかりに東京女子医科大学に入学。
長いトンネルから抜け出した。
過去に受けたいじめの傷は、すっかり風化しているという。
しかし、「影響は残ってるんじゃないかな」、25年来の友人で、向日葵クリニック事務長の堤円香さん(45)が話す。
「明澄が医師国家試験を受験する時期、私の実家で2か月暮らしたことがあったんです。そのとき、うちの母が『明澄ちゃんは本当の親に育てられてないの?』って聞くほど、彼女すごく気を遣ってきて。いじめから身を守るために、相手の気持ちを読む癖がついていたのかな。つらい経験だったと聞いていますが、医師になった今、患者さんの心の痛みをすっと酌み取れるのは、彼女自身が痛みを経験してきたからだと思います」
研修医時代に流した涙
初めて在宅医療に触れたのは、大学2年生のとき。地域医療を学ぶため、新潟県の山村に暮らす高齢の夫婦を訪ねたことが始まりだった。
「そこはご近所もないような孤立した家で、ご主人は脳梗塞でベッドから動けず、奥さんも耳が遠くて電話に気づけない。安否確認できないことが問題点でした」
打開策は容易に見つからず、どうにも心配になった中村先生は「私がここに住み込みます!」と宣言し、同行していた保健師に止められたほど。
それほど当時から、患者を思う気持ちが強かった。
しかし、それは「医師に向かない自分」を浮き彫りにしたと振り返る。
学生時代の臨床実習で担当した70代の女性患者が、抗がん剤治療後に発熱。立て続けに検査に回されたときは、「なぜ、高熱が出てつらいのに検査をしなくちゃいけないの」と、憤りを感じた。
20代末期がんの男性患者が危篤になり、延命処置のために家族や婚約者が病室から出され、亡くなってから呼びもどされたときは、「大切な人に手を握ってもらいたかったのでは」と、思わずにいられなかった。
「抗がん剤治療中の患者さんが高熱を出したら、検査をするのは当然だし、延命治療が優先された当時、家族が病室から出されるのも間違ったことではありません。だけど、医者ではない私の感情が、それを受けつけないというか。これでいいのかっていう思いが込み上げてしまって」
2000年、研修医として国立病院機構東京医療センターに就職。晴れて医師として患者を受け持つことになってからは、治らない病気の多さを改めて知り、自分の無力さを痛感した。
「患者さんを助けたくて医者になったのに、実際は助けられないことも多い。打つ手がなくなれば、入院患者は病院にいられなくなる。そこから先、患者さんに何もできないジレンマがありました」
医師には割り切りも必要なのだろう。しかし、中村先生は割り切れなかった。
「患者さんの役に立てないことが悔しくて、情けなくて、研修医用の寄宿舎の裏庭で泣いたこともあります」
ままならない現実にもがきながら、自分に何ができるかを考えた。やがてたどり着いたのが、在宅医療だった。
「医療は病院だけのものでなく、家庭でも点滴や採血など医療行為はできます。ティッシュの空き箱でガーゼ入れを作ったり、針金のハンガーを折り曲げて点滴棒にしたり、暮らしの中に医療が溶け込んでいる光景も大学時代の実習で見てきました。病気を治すことができなくても、患者さんがその人らしく生きるために、医療が関わり続けることはできる。その受け皿になれないかと考えたんです」
研修医を終えるころには、心が決まった。
その後、筑波大学附属病院を皮切りに、勤務医として臨床経験を積むこと10年。
向日葵クリニックの前身となる向日葵ホームクリニック(千葉市)で、訪問医として第一歩を踏み出したのは、36歳のときだ。