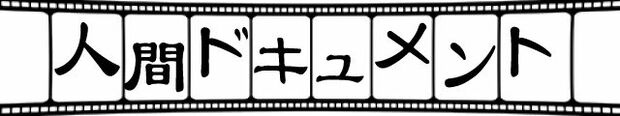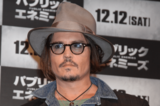芸能界には80歳を過ぎても驚くほど若々しく元気な人がいる。うつみ宮土理もその一人だ。舞台で主演を務め、テレビの散歩番組ではゲストを迎えて軽やかな足取りで街を歩く。ニット帽にパーカ、ダンスパンツというヒップホップのファッションをかわいく着こなせる81歳はそうそういない。約60年前の『ロンパールーム』の“先生”のときから変わっていない、チャーミングな笑顔も健在だ。
10年前、夫の愛川欽也さんを亡くしたときは悲しみに打ちひしがれていたが、2年が過ぎたころから立ち直り、本来のパワフルさを取り戻していった。「同年代の人たちはどうしたのかしらと思うくらい、みんなどこか痛いと言っているし、病気の人や亡くなった人も多いの。だからクラス会もできなくなったわね」と、うつみは嘆く。
80歳を過ぎても元気でいられる秘訣はどこにあるのだろうか。昭和から平成、令和とテレビ業界を軽やかに駆け抜けてきた、うつみの人生を振り返る。
小4で母を亡くし伯母に育てられる

東京・世田谷の造園業を営む家に生まれ、5人きょうだいの次女として育ったうつみ。同居する姑から母がいじめられているのを見て育ったせいか、幼いころは無口で暗かったという。一家で引っ越しが決まり、ようやく意地悪な姑から解放された矢先、母は突然この世を去った。
「学校から帰ってきたら、母が真夏なのに『寒い、寒い』と言って寝ていて。布団をかけてもガタガタ震えていて、布団の上からも母の熱さが伝わってきました。急いで医者を呼びに行ったけれど、戻ってきたときには母はもう危篤状態でした」と、うつみは悲痛な体験を語る。当時小学4年生だった。
母が亡くなって家族が呆然とする中、部屋に飛び込んできて、まだ小さかった妹や弟の世話をし、ごはんを作ってくれたのが母の姉である伯母のハナさんだった。
「伯母は夫が戦死し、近くの病院で雑用をして生計を立てていました。『おばちゃんが来たからもう大丈夫』と言ってくれ、それからは困ることなく、普通の生活に戻っていったんです」
その後、伯母は父と結婚し、自分の一人娘と、うつみを含む5人の子どもの母親となった。暗かったうつみが明るく前向きな性格に変わったのは、この2番目の母のおかげだ。
「母は『小さい声の人は出世しない』という考えで、『ただいま』を大きな声で言う練習も何度もさせられました。そうやって大きな声が出せるようになると、顔つきまで変わって、明るい性格になっていったんです」

母から学んだ教えは、今もうつみの道しるべになっている。
「人の役に立つこと、喜んでもらえることをすれば、人生はうまくいく。明るい笑顔は100万ドルの価値があるというのが母の教えでした。何かしてもらったら、ありがとうとお礼のハガキをすぐに出すように言われ、それも守ってきました。今になってみると、母の言うことは何ひとつ間違ってなかったと確信できます」
褒め上手だった母のおかげで、成績もぐんぐん伸び、大学は実践女子大学の英文科に入学。ところが大学4年生のときに、父ががんで亡くなってしまう。
「家族を支えていかないといけないので、就職先を探し始めました。当時、芥川龍之介の写真のような、ほっそりとした知的な男性に憧れていたんです。新聞社に入れば、ああいう人がいっぱいいるんじゃないかと思って朝日新聞社を受験しました(笑)」
応募したのは英字雑誌『ディス・イズ・ジャパン』の欠員募集だった。英語を勉強し、大学を首席で卒業したうつみだったが、ハーバード大学を卒業した人も受験する難関だ。そのとき母が「面接官は年配の人が多いから礼儀作法も重視するんじゃないか」とアドバイスをくれたのが功を奏した。
「面接では丁寧に挨拶し、『政治経済は全然わかりません。入ってから勉強します』と正直に答えました。すると『あの子はかわいくて癒される』という理由で採用してもらえたんです」
そのとき同期として入社したのが、ジャーナリストとして活躍する下村満子だった。うつみは下村のアシスタント的な立場で、お茶くみや掃除がメインの仕事だったが、会社の偉い人たちにかわいがられた。
「テニスに誘われ、3時のおやつに呼ばれ、おじさまたちとの食事でスケジュールが埋まっていきました。高いお寿司屋さんや、有名人が集まるサロン的な場所として有名だった、銀座の『マキシム』などに連れていってもらって、食事のマナーが身についたのもこのころのおかげです。『君は本当においしそうに最後まで食べる』と食べっぷりをみんなが喜んでくれて。若い人には全然モテなかったけど、年上のおじさまたちからはモテモテでした」